�R���p�X�����w�m�d�q�ŕt�n������3��

| �ҏW | : �O�c���m/���^�i |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-40447-6 |
| ���s�N�� | : 2025�N3�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 496 |
��
�艿6,050�~(�{��5,500�~ �{ ��)
����\
-
2025�N05��26��
��1��
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

�u�킩��₷���E�~�j�}���G�b�Z���X�v���R���Z�v�g�̐����w�̋��ȏ��D��{�������킩��₷��������邾���łȂ��C�w�ւ̂Ȃ���C���a�Ƃ̂��������R�������ő����Љ�D�������ł͊e������ŐV�̂��̂ɍX�V���C�S�̂ɂ킽��\���̌��������s�����ق��C�d�q�ŕt�Ƃ����D��w���烂�f���E�R�A�E�J���L�������i�ߘa4�N�x�����Łj�Ή��D�d�q�Ō���t�^�Ƃ��āC�����w�̈�̖�t���Ǝ����ߋ����W�Ɠ���̃����N�W�����ځD
�T���@�����̂̐��藧��
�P�́@�זE�E�g�D�E�튯
�`�@�זE�F�����̊�{�P��
�@�@�ׁ@�E
�@�A���j�����Ɛ^�j����
�@�B�זE���튯
�@�@���@�זE��
�@�@���@�j
�@�@���@�~�g�R���h���A
�@�@���@���E��
�@�@���@�S���W��
�@�@���@���\�\�[��
�@�@���@�G���h�\�[��
�@�@���@�y���I�L�V�\�[��
�@�C���\���������Ȃ��זE���\��
�@�@���@���{�\�[��
�@�@���@�זE���i
�@�@���@���S��
�@�D���F��
�a�@�q�g�̑̂̐��藧��
�@�@�q�g�̑̂̊K�w��
�@�A�g�@�D
�@�@���@���g�D
�@�@���@�����g�D
�@�@���@�ؑg�D
�@�@���@�_�o�g�D
�@�B��@��
�@�C�n
�@�@���@�O��n
�@�@���@���i�n
�@�@���@�@�n
�@�@���@�_�o�n
�@�@���@������n
�@�@���@�S�����njn
�@�@���@�����p�n�E�Ɖu�n
�@�@���@�ċz��n
�@�@���@������n
�@�@���@��A��n
�@�@���@���B��n
�@Exercise
�U���@���̐����̍\���E�@�\
�Q�́@���̐���
�@�@���̐���
�@�@���@���̐���
�@�@���@�����v�C�I���̑̓����z
�@�@���@���t�̊ɏՍ�p��CO2�̉^��
�@�A�q�g�̑̂��\�����錳�f
�@�B��Ȑ��̕��q
�@�@���@���@��
�@�@���@�^���p�N��
�@�@���@�j�@�_
�@�@���@���@��
�@�@���@�~�l����
�@Exercise
�R�́@���@��
�`�@�����̍\���ƕ���
�@�@�����Ƃ�
�@�A�P�@��
�@�B�����̖��̂̕t����
�@�C�A���h�w�L�\�[�X
�a�@�O���R�[�X�F�ł���ȓ���
�@�@d-�O���R�[�X
�@�A���n�t���ł�d-�O���R�[�X�̍\��
�b�@�O���R�[�X�ȊO�̑�\�I�ȒP���C��
�@�@d-�O���R�[�X�ȊO�̑�\�I�ȁ@�@
�A���h�w�L�\�[�X
�@�A��\�I�ȃP�g�[�X�Cd-�t���N�g�[�X
�@�B���̑��̑�\�I�ȒP��
�@�C�P���U����
�@�@���@�A�~�m��
�@�@���@�E�����_
�@�@���@���A���R�[��
�@�D��\�I�ȓ�
�@�@���@�X�N���[�X�i�V�����j
�@�@���@���N�g�[�X�i�����j
�@�@���@�}���g�[�X�i���蓜�j
�@�@���@�g���n���[�X
�@�E���̊Ҍ���
�c�@��\�I�ȑ���
�@�@�z������
�@�@���@�f���v��
�@�@���@�O���R�[�Q��
�@�@���@�Z�����[�X
�@�@���@�L�`��
�@�@���@���̑��̃z������
�@�A�w�e������
�@�@���@�O���R�T�~�m�O���J��
�@�@���@�A�K���[�X
�@�B��������
�@�@���@���^���p�N��
�@�@���@ABO�����t�^����
�@�@���@�v���e�I�O���J��
�@�@���@�y�v�`�h�O���J��
�@�@���@GPI�A���J�[�^�^���p�N��
�d�@�����̒萫����ђ�ʎ����@
�@�@�����̒萫�����@
�@�@���@�t�F�[�����O����
�@�@���@�g�����X�i�⋾�j����
�@�@���@���E�f�E�f���v������
�@�A�y�f��p�����O���R�[�X�̒��
�@Exercise
�S�́@�A�~�m�_�E�y�v�`�h
�`�@�A�~�m�_�̍\���Ɛ���
�@�@�A�~�m�_�̊�{�\��
�@�A20��ނ̕W���A�~�m�_
�@�@���@�����A�~�m�_
�@�@���@�_���A�~�m�_
�@�@���@����A�~�m�_
�@�B�A�~�m�_�̎��
�@�@���@�K�{�A�~�m�_
�@�@���@��K�{�A�~�m�_
�@�@���@���̑��̃A�~�m�_
�@�C�A�~�m�_�U���̃z������
�@�D�A�~�m�_�̓H��Ȑ�
�a�@�A�~�m�_�̒萫����ђ�ʕ��@
�@�@�A�~�m�_�̒萫����
�@�A�A�~�m�_�̕����E���
�b�@�y�v�`�h�̍\���Ɛ�������
�@�@�y�v�`�h�ƃy�v�`�h����
�@�@���@�y�v�`�h
�@�@���@�y�v�`�h����
�@�A�O���^�`�I��
�@�B�y�v�`�h���z�������Ɛ��������y�v�`�h
�@�@���@�C���X����
�@�@���@�O���J�S��
�@�@���@�A���W�I�e���V���U
�@�@���@�u���W�L�j��
�@Exercise
�T�́@�^���p�N��
�`�@�^���p�N���̍\��
�@�@�^���p�N���̊K�w�\��
�@�A�^���p�N���̈ꎟ�\��
�@�B�^���p�N���̓\��
�@�@���@���փ��b�N�X
�@�@���@���V�[�g
�@�C�^���p�N���̎O���\��
�@�D�^���p�N���̎l���\��
�@�E�^���p�N���̍����\���̌`��
�@�F�^���p�N���̕ϐ��ƍĐ�
�@�G�^���p�N���̖|���C��
�@�@���@�y�v�`�h�����̐ؒf���|���C��
�@�@���@����̃A�~�m�_�c��ɉ��炩�̕t���������N����ꍇ
�@�H�^���p�N���̍זE���Ǎ�
�@�@���@�^���p�N�������E�̖��Ɍ����킹��V�O�i���z��
�@�@���@�j�C�~�g�R���h���A��y���I�L�V�\�[���ɋǍ݉�������V�O�i��
10
�^���p�N���̕i���Ǘ�
�a�@�זE���v���e�A�[�[�̖���
�@�@�^���p�N���̐��n�ƃv���e�A�[�[
�@�A�A�~�m�_�̍ė��p�ɓ����v���e�A�[�[
�@�B���r�L�`��–�v���e�A�\�[���n
�@�@���@�W�I�^���p�N���̃|�����r�L�`����
�@�@���@�v���e�A�\�[���̍\���ƐG�}����
�@�@���@�v���e�A�\�[���ƍזE�@�\
�@�C�J�X�p�[�[�ƃA�|�g�[�V�X
�b�@�^���p�N���̕��ނƋ@�\
�@�@�^���p�N���̋@�\�ɂ�镪��
�@�A�^���p�N���̉��w�g���ɂ�镪��
�@�@���@�P���^���p�N��
�@�@���@�����^���p�N��
�@�B�זE���i���`������^���p�N���̎�ނƖ���
�@�@���@�A�N�`���t�B�������g
�@�@���@���Ԍa�t�B�������g
�@�@���@������
�@�C�Ɖu�O���u�����̍\���Ƌ@�\
�c�@�^���p�N����͂̊�b�Z�p
�@�@�^���p�N���̕����E�����ƕ��q�ʂ̑���@
�@�@���@�^���p�N���̎�舵����
�@�@���@�^���p�N���̕����E�����̗���
�@�@���@�N���}�g�O���t�B�[�ɂ�镪��
�@�@���@�d�C�j��
�@�@���@�^���p�N���̒E���ƔZ�k�@
�@�@���@�Ɖu�w�I����@
�@�A�^���p�N���̃A�~�m�_�z��@
�@�@���@N���[����̃A�~�m�_�z��@
�@�@���@���ʕ��͖@�i�}�X�X�y�N�g�����g���[�j�ɂ��A�~�m�_�z��@
�@�@���@cDNA����̃A�~�m�_�z��@
�@�B�^���p�N���̒萫�E��ʎ����@
�@�@���@�^���p�N���̒萫�i���o�j����
�@�@���@�^���p�N���̒�ʎ���
�@Exercise
�U�́@�y�@�f
�`�@�y�@�f
�@�@�y�f�Ƃ�
�@�A�G�}�ɂ�銈�����G�l���M�[�̒ቺ
�@�B�y�f�̕��ނƖ���
�@�@���@�_���Ҍ��y�f�iEC1�Q�j
�@�@���@�]�ڍy�f�iEC2�Q�j
�@�@���@���������y�f�iEC3�Q�j
�@�@���@�E���y�f�iEC4�Q�j
�@�@���@�ِ����y�f�iEC5�Q�j
�@�@���@�����y�f�iEC6�Q�j
�@�@���@�A���y�f�iEC7�Q�j
�@�C�y�f�Ǝ����E��
�a�@�y�f�̐G�}�����̃��J�j�Y��
�@�@�y�f�̊�������
�@�A�Z�����v���e�A�[�[�̐G�}�@�\
�@�B��y�f
�@�C���y�f������
�@�D�y�f�̍œK����
�b�@�y�f�̔������x�_
�@�@�~�J�G���X�E�����e���̎�
�@�A�~�J�G���X�E�����e���̎�����킩�邱��
�@�B���C���E�B�[�o�[�E�o�[�N�v���b�g
�c�@�y�f�����̑j�Q
�@�@�s�t�j�Q
�@�A�t�j�Q
�@�@���@�����j�Q
�@�@���@���j�Q
�@�@���@�s�����j�Q�i�������j�Q�j
�d�@�y�f�����̐���
�@�@�������x���̒���
�@�A�����ɂ�钲��
�@�B�^���p�N���ԑ��ݍ�p�ɂ��y�f�����̒���
�@�C���蕪���ɂ��y�f�����̐���
�@�D�ᕪ�q�̋��L�����ɂ�鐧��i�|���C���j
�@�E�A���X�e���b�N����
�@�@���@�z���g���s�b�N����
�@�@���@�w�e���g���s�b�N����
�e�@��\�I�ȍy�f�̊�������@
�@Exercise
�V�́@�j�_�E�k�N���I�`�h
�`�@�j�_�̍\������
�@�@���@��
�@�A��
�@�B�k�N���I�V�h
�@�C�k�N���I�`�h
�@�@���@���{�k�N���I�`�h
�@�@���@�f�I�L�V���{�k�N���I�`�h
�@�D���̑��̓���ȉ���C�k�N���I�V�h���܂ޏd�v�ȉ�����
�@�@���@����ȉ���
�@�@���@�k�N���I�`�h�\����L���鉻����
�@�@���@���`�B���q�Ƃ��Ẵk�N���I�`�h�C�k�N���I�V�h
�a�@DNA�CRNA�̍\���Ƌ@�\
�@�@DNA�̊�{�\���Ɛ���
�@�@���@DNA�̊�{�\��
�@�@���@DNA�̐���
�@�@���@DNA�̒��点��\��
�@�@���@�j���ɂ�����DNA�̍\��
�@�ARNA�̊�{�\���Ƌ@�\
�@�@���@RNA�̊�{�\���Ǝ��
�@�@���@���{�\�[��RNA�irRNA�j
�@�@���@���b�Z���W���[RNA�imRNA�j
�@�@���@�g�����X�t�@�[RNA�itRNA�j
�@�@���@���̑���RNA
�@Exercise
�W�́@�r�^�~���E����
�`�@�r�^�~���Ƃ�
�a�@���n���r�^�~��
�@�@�r�^�~��B�Q
�@�@���@�r�^�~��B1
�@�@���@�r�^�~��B2
�@�@���@�i�C�A�V���i�r�^�~��B3�j
�@�@���@�p���g�e���_�i�r�^�~��B5�j
�@�@���@�r�^�~��B6
�@�@���@�r�I�`���i�r�^�~��B7�j
�@�@���@�t�_�i�r�^�~��B9�j
�@�@���@�r�^�~��B12
�@�A�r�^�~��C
�b�@���n���r�^�~��
�@�@�r�^�~��A
�@�A�r�^�~��D
�@�B�r�^�~��E�i�g�R�t�F���[���j
�@�C�r�^�~��K
�c�@�K�{���ʌ��f
�@Exercise
�X�́@���@��
�`�@�����̓����ƕ���
�@�@�����̓����Ɩ���
�@�A�����̕���
�@�B���b�_
�@�@���@���b�_�̊�{�\��
�@�@���@�O�a���b�_�ƕs�O�a���b�_
�@�C�������b
�@�D��@��
�@�E��������
�@�@���@�O���Z����������
�@�@���@�X�t�B���S��������
�@�F������
�@�@���@�X�t�B���S������
�@�@���@�O���Z��������
�a�@�C�\�v���m�C�h
�@�@�e���y��
�@�A�X�e���C�h
�@�@���@�X�e���[��
�@�@���@�X�e���C�h�z������
�@�@���@�_�`�_
�b�@�G�C�R�T�m�C�h
�@Exercise
10�́@���̖��ƗA��
�`�@���̖��̍\���Ɛ���
�@�@���̖��̋��ʐ���
�@�A�����̑��ݏ�ԂƖ���
�@�@���@������d�w�̌`��
�@�@���@������
�@�@���@�������t�g
�@�@���@��Ώ̐�
�@�B���^���p�N���̑��ݏ�ԂƖ���
�@�@���@���ݐ����^���p�N��
�@�@���@�\�ݐ����^���p�N��
�@�@���@���^���p�N���̋@�\
�a�@���̖�������n���̗A��
�@�@�A��
�@�@���@�O���R�[�X�A����
�@�@���@�`���l��
�@�A�\���A��
�@�@���@�ꎟ���\���A��
�@�@���@���\���A��
�b�@�����A���i���E�A���j
�@�@�G���h�T�C�g�[�V�X
�@�@���@����p�i�s�m�T�C�g�[�V�X�j
�@�@���@�N���X�����ˑ����G���h�T�C�g�[�V�X
�@�@���@�J�x�I���ɂ��A��
�@�@���@�H��p�i�t�@�S�T�C�g�[�V�X�j
�@�A�G�L�\�T�C�g�[�V�X
�@�B�I�[�g�t�@�W�[
�@�@���@�}�N���I�[�g�t�@�W�[
�@�@���@�~�N���I�[�g�t�@�W�[
�@�@���@�V���y������ݐ��I�[�g�t�@�W�[
�@�C���E�̍זE���^���@�\
�@Exercise
�V���@��@��
11�́@�ى��Ɠ���
�@�@���R�G�l���M�[
�@�A�G���^���s�[�ƃG���g���s�[
�@�B�W�����R�G�l���M�[�ω�
�@�C�ى��Ɠ���
�@�D�G�l���M�[�ʉ݂Ƃ��Ă�ATP
�@�@���@�z�G���S��������ATP���������Ƃ̋���
�@�@���@���G���S��������ATP���������Ƃ̋���
�@�E�����A����ATP
�@�FADP��ATP�̗ʔ�͍זE�̃G�l���M�[��Ԃ�����
�@�GATP�����G�l���M�[�������ł��鍪��
�@�H�H�����̉h�{�����̏����E�z���E�̓��^��
�@Exercise
12�́@�������
�`�@�����̏����E�z���E�̓��^��
�a�@�n
�@�@�n�̔���
�@�@���@�n�̏�����
�@�@���@�n�̕�V��
�@�@���@�n�̍ŏI�Y���̍s��
�@�A�n�̃G�l���M�[���x
�@�B�n�̒��ߋ@�\
�@�C�O���R�[�X�ȊO�̒P���̉n�ւ̃G���g���[
�@�D���_���y�ƃA���R�[�����y
�b�@�N�G���_��H
�@�@�s���r���_����A�Z�`��CoA��
�@�A�N�G���_��H�̔���
�@�B�N�G���_��H�̒��ߋ@�\
�@�C�A�~�m�_�E���b�_�̑�ӂƃN�G���_��H
�c�@�d�q�`�B�E�_���I�����_��
�@�@�d�q�`�B�n
�@�A�_���I�����_���ɂ��ATP�̍���
�@�B�זE��NADH�̃~�g�R���h���A�ւ̗A��
�@�C�O���R�[�X�̑�ӂɂ��ATP�����̎��x
�@�DATP�����̑j�Q��
�d�@�y���g�[�X�����_��H
�@�@�y���g�[�X�����_��H�̔���
�@�@���@�s�t�I�_������
�@�@���@�t�I��_������
�@�ANADPH�̖���
�e�@�O���R�[�Q���̋@�\�Ƒ��
�@�@�O���R�[�Q���̋@�\�E�\��
�@�A�O���R�[�Q���̐������E����
�@�@���@�O���R�[�Q���̐�����
�@�@���@�O���R�[�Q���̕���
�@�@���@�O���R�[�Q���̐������E�����̒���
�f�@���V��
�@�@���V���̔���
�@�@���@�s���r���_����z�X�z�G�m�[���s���r���_�ւ̔���
�@�@���@�t���N�g�[�X1,6-�r�X�����_����t���N�g�[�X6-�����_�ւ̔���
�@�@���@�O���R�[�X6-�����_����O���R�[�X�ւ̔���
�@�A���V���Ɖn�̃G�l���M�[���x�̔�r
�@�B���V���̊
�g�@�C���X�����ƃO���J�S��
�@�@�C���X�����ƃO���J�S��
�@�@���@�C���X����
�@�@���@�O���J�S��
�@�A�����l�̕ϓ��Ƃ��̒���
�@�B �C���X��������уO���J�S���ɂ���Ӓ���
�@�C�O���R�[�Q����ӂ̒���
�@�D���V���̒���
�h
�G�l���M�[�Y���o�H�̒��߂Ɠ��A�a
�@�@�ېH�E�z�����Ƌ��E�Q���Ԃ̃G�l���M�[���
�@�@���@�ېH�E�z�����̃G�l���M�[���
�@�@���@������ыQ�쎞�̃G�l���M�[���
�@�A�P�g���̂̐������Ɨ��p
�@�@���@�̑��ł̃P�g���̂̐�����
�@�@���@�P�g���̗̂��p�i�A�Z�`��CoA�ւ̕ϊ��j
�@�@���@�P�g���̂ɂ��A�V�h�[�V�X�@�@
�i�P�g�A�V�h�[�V�X�j
�@�@���@�����Q���Ԃɂ�����G�l���M�[���
�@�B ���A�a�Ɠ����
�@�@���@���A�a�̕a��
�@�@���@���A�a�̑�ӂ̓���
�@Exercise
13�́@�������
�`�@���b�_�̐������E�����ƃG�l���M�[���
�@�@���b�_�̑�ӂɂ�����ʒu�Â�
�@�A���b�_�̐�����
�@�B�s�O�a���b�_�̐�����
�@�C���b�_�̕���
�@�D���b�_�̉^��
�@�E���_���ɂ��G�l���M�[�Y������
�a�@�R���X�e���[���̐������Ƒ��
�@�@�R���X�e���[���̑��
�@�A�R���X�e���[���̐�����
�@�B�_�`�_
�@�C�X�e���C�h�z������
�@�@���@�X�e���C�h�z������
�@�@���@���z������
�@�@���@���t�玿�z������
�b�@�����̋z���Ɖ^��
�@�@�������|�^���p�N��
�@�A��������̎����̋z��
�@�B���|�^���p�N���ƃR���X�e���[���̉^��
�@�@���@�L���~�N����
�@�@���@VLDL�CIDL�CLDL
�@�@���@HDL
�@�C�R���X�e���[���ʂ̃t�B�[�h�o�b�N����
�@�D�����ُ��
�@�E���n���r�^�~���̋z���Ɖ^��
�c�@���������̐������Ƒ��
�@�@���������̐�����
�@�A�����������q�̕��q�퐧��
�@�B����������ӎY���Ɛ�������
�@�@���@�C�m�V�g�[��1,4,5-�g���X�����_�ƃW�A�V���O���Z���[��
�@�@���@�������������q
�d�@�G�C�R�T�m�C�h
�@�@�A���L�h���_�J�X�P�[�h
�@�A�v���X�^�O�����W���ƃg�����{�L�T��
�@�B���C�R�g���G��
�@Exercise
14�́@�A�~�m�_���
�`�@�A�~�m�_�̋����Ɨ��p
�@�@�̓��ł̃A�~�m�_�̖����Ɨ��p
�@�A�A�~�m�_�̋���
�@�@���@�K�{�A�~�m�_�Ɣ�K�{�A�~�m�_
�@�@���@�H�����̃^���p�N���̕����ƃA�~�m�_�̋z��
�a�@�A�~�m�_�̒��f�̑��
�@�@�A�~�m��]�ڔ���
�@�@���@�A�~�m��]�ڔ����Ƃ�
�@�@���@�A�X�p���M���_�̃A�~�m��]�ڔ���
�@�@���@�A���j���̃A�~�m��]�ڔ���
�@�A�_���I�E�A�~�m����
�@�B�A�f��H
�@�@���@�̑��̃~�g�R���h���A�ł̔���
�@�@���@�̑��̍זE���ł̔���
�@�C�A�~�m��̉^��
�b�@�A�~�m�_�̒Y�f���i�̑��
�@�@�A�~�m�_��ӂƃN�G���_��H
�@�A�P�g�����A�~�m�_�Ɠ������A�~�m�_
�@�B��ȃA�~�m�_�̕����o�H
�@�@���@�`���V���C�t�F�j���A���j���̕����o�H
�@�@���@���}�A�~�m�_�̕����o�H
�@�@���@�q�X�`�W���̕����o�H
�@�@���@���`�I�j���̕����o�H
�@�C�A�~�m�_�̑�ӈُ��
�c�@�A�~�m�_��ӂɂ�鐶�����������̐�����
�@�@�E�Y�_�����ɂ�鐶�������A�~���̐�����
�@�@���@�A�~�m�_�̒E�Y�_�����Ɛ��������A�~��
�@�@���@�q�X�^�~���̐�����
�@�@���@��-�A�~�m���_�iGABA�j�̐�����
�@�@���@�Z���g�j���̐�����
�@�@���@�J�e�R�[���A�~���̐�����
�@�A�|���t�B�����ƃw�����
�@�@���@�w���̐�����
�@�@���@�w���̕���
�@�B���̑��̐�����������
�@�@���@�N���A�`���̐�����
�@�@���@�k�N���I�`�h�̐�����
�@�@���@�j�R�`���_�C�j�R�`���A�~�h�̐�����
�@�@���@�^�E�����̐�����
�@�@���@�O���^�`�I���̐�����
�@�@���@�|���A�~���̐�����
�d�@��_�����f�iNO�j�̐������Ɩ���
�@�@��_�����f�iNO�j�̐�����
�@�ANO�̍�p�@��
�@�BNO�̐�����p
�@Exercise
15�́@�k�N���I�`�h���
�`�@�k�N���I�`�h�̐�����
�@�@�v�����k�N���I�`�h�̐�����
�@�@���@�f�m�{�����o�H�i�V���o�H�j
�@�@���@�ė��p�i�T���x�[�W�j�o�H
�@�A�s���~�W���k�N���I�`�h�̐�����
�@�@���@�f�m�{�����o�H�i�V���o�H�j
�@�@���@�ė��p�i�T���x�[�W�j�o�H
�@�B���{�k�N���I�`�h����f�I�L�V���{�k�N���I�`�h�ւ̕ϊ�
�a�@�k�N���I�`�h�̕���
�@�@���@�v�����k�N���I�`�h�̕���
�@�@���@�s���~�W���k�N���I�`�h�̕���
�b�@�Z�J���h���b�Z���W���[�Ƃ��ẴT�C�N���b�N�k�N���I�`�h�̐������ƕ���
�@�@�T�C�N���b�N�k�N���I�`�h�̐�����
�@�A�T�C�N���b�N�k�N���I�`�h�̕���
�c�@�זE�������q�j�_�̍����ƕ���
�@�@�זE�������q�j�_�̍���
�@�A�זE�������q�j�_�̕���
�@Exercise
16�́@��`���
�`�@�Z���g�����h�O�}
�@�@�Z���g�����h�O�}
�@�A�Z���g�����h�O�}�̏C��
�@�B��`�q�ƃR�h��
�a�@���@��
�@�@�����J�n����
�@�A�V�����̍���
�@�@���@�v���C�}�[�̍���
�@�@���@DNA���̐L��
�@�@���@DNA�|�������[�[�̍Z���@�\
�@�@���@����t���O�����g�̘A��
�@�B���F�̖̂��[�������
�b�@�]�@��
�@�@�]�ʂɊ֗^���镪�q
�@�@���@RNA�|�������[�[
�@�@���@�]�ʈ��q
�@�@���@�]�ʋ������q�i�R�t�@�N�^�[�j
�@�A�]�ʊJ�n����
�@�@���@�^�j�זE�̃v�����[�^�[�Ɠ]�ʊJ�n����
�@�@���@�咰�ۂ̃v�����[�^�[�Ɠ]�ʊJ�n����
�@�B�]�ʐL�������Ɠ]�ʏI������
�@�@���@�]�ʐL������
�@�@���@�]�ʏI������
�@�C�]�ʂ̒��ߋ@�\
�@�@���@�^�j�זE�̓]�ʒ���
�@�@���@�ЃT�u���j�b�g�ɂ��咰�ۂ̓]�ʒ���
�c�@�|�@��
�@�@�|�u���{�\�[��
�@�A�A�~�m�A�V��tRNA�̍���
�@�B�|��J�n����
�@�C�|��L������
�@�D�|��I������
�d�@�ψقƏC��
�@�@�ψق̋N����DNA�̕���
�@�A�R�h���̕ω����A�~�m�_�z��ɋy�ڂ�����
�@�BDNA�����̏C���@�\
�@�@���@���ڏC��
�@�@���@�����C��
�@�@���@�������̑����C��
�@�@���@�ؒf���ꂽDNA���̑����C��
�@Exercise
17�́@��Ӓ���
�`�@��ӌo�H�̑S�̑�
�a�@�זE���זE�O����̏��ɉ������郁�J�j�Y��
�@�@�זE�̏��`�B�̊�{�l��
�@�A���`�B�Ɋւ�镪�q
�@�@���@���`�B����
�@�@���@G�^���p�N�������^��e�́iGPCR�j�Ə��`�B�o�H
�@�@���@�y�f�A���^��e��
�@�@���@�C�I���`���l���A���^��e��
�b�@�z�������ɂ�钲��
�@�@�z�������̕��咲�߂Ƃ��ُ̈�
�@�A��`�q�����߂���z������
�c�@�A�|�g�[�V�X�̗U��
�@�@�C�j�V�G�[�^�[�J�X�p�[�[�ƃG�t�F�N�^�[�J�X�p�[�[
�@�A�������o�H�i�~�g�R���h���A�o�H�j
�@�B�O�����o�H�i���̎�e�̌o�H�j
�@Exercise
�@Exercise��
�{���őΉ������w���烂�f���E�R�A�E�J���L�������i�ߘa4�N�x�����Łj�ꗗ
���@��
�R�����ڎ�
�����m��
�P�́@�S���W�̂̔����҃S���W
�@�זE���튯�̖��O
�@���Ȃ��ȏ������זE
�@�A�h���i�����ƃG�s�l�t����
�@�X���͓�����n���O����n��
�@����ӊO�D����ȂƂ��납����z�����������傳���
�Q�́@���t����
�@�J���V�E���F�זE�łł��g��������
�R�́@�Â��Ȃ���
�@�J�����[0�i�[���j�̓���
�S�́@D�̂̃A�~�m�_
�@�A�~�m�_�̎G�w
�@�Z�����ܗL�A�~�m�_���܂ރ^���p�N��
�@���̓��z�������ŁC�����l�~���������̂͂Ȃ��C���X���������Ȃ̂��H
�@�u���W�L�j���̗R���Ƃ�
�T�́@�h���b�O���|�W�V���j���O
�@�^���p�N���̍\���ɂ����郂�`�[�t�ƃh���C��
�U�́@�Đ����Ȃ��y�f
�V�́@�V�����K�t�̖@��
�W�́@�r�^�~�������̗��j�i�r�^�~��B1�ƍ����a�ł���r�C�j
�@�r�^�~���Ɍ��Ԃ����闝�R
�X�́@���b�זE
10�́@�������U�C�N���f��
11�́@1���ɕK�v��ATP�ʂ͑̏d���݂̗�
�@ATP�̂���3�̊�
12�́@�w�L�\�L�i�[�[�ƃO���R�L�i�[�[
�@�W���Ҍ��d�ʁiE���j
�@�p�X�c�[������
�@�O���R�[�X-6-�����_�f�q�h���Q�i�[�[�iG6PD�j�����ǂƃ}�����A�ϐ�
13�́@LCAT�CACAT�ƃR���X�e���[���G�X�e��
�@�@���b�_�g���ƃG�C�R�T�m�C�h
14�́@�O���^�`�I�������Ɖ��
16�́@�G�L�\�\�[��
17�́@���`�B�����̕��ނ̞B����
�@�j����e�̂͑�ӃZ���T�[
�����i�̒m��
�R�́@���i�w�p����
�@�w�}�O���`�j���^���p�N���ƃm�C���~�j�_�[�[�j�Q��
�S�́@���j���E�A���W�I�e���V���n�j�Q��
�@�k�A���W�I�e���V���ϊ��y�f�iACE�j�j�Q��ƃA���W�I�e���V���U��e�̝h�R��iARB�j�l
�T�́@�I��I�G�X�g���Q����e�̕����
�@�v���e�A�\�[���j�Q��
�@�����ǂƐA���A���J���C�h
�U�́@�y�f��
�@���E�
�V�́@�������������Ƃ��Ẵk�N���I�V�h�E�k�N���I�`�h
�@�j�_�A�i���O�ł�����i
�W�́@���J�����[�A�t�ɂ��A�V�h�[�V�X��������邽�߂̃r�^�~��B1�⋋
�X�́@�v���X�^�O�����W������
�@�A�i�t�B���L�V�[�̒x�����������ƋC�ǎx�b���̎��Ö�
10�́@���A�a���Ö�SGLT2�j�Q��
�@�����ǃR���X�e���[���A����NPC1L1�Ǝ����ُ�ǎ��Ö�
12�́@���V����}���铜�A�a���Ö�F�r�O�A�i�C�h��ƃO���~����
�@��`�q�g�����C���X��������
�@�C���N���`���ɂ��C���X��������̑��i
13�́@�זE�̂���LDL��e�̐���n�𗘗p���������R���X�e���[���ቺ��
�@��X�e���C�h�R���ǖ�iNSAIDs�j
14�́@L-�h�[�p
�@�R����
�@���S�ǎ��Ö�
15�́@���A�_���ǁE�ɕ����Ö�
�@�R������ᇖ�
�@�R�ۖ�
16�́@DNA�g�|�C�\�����[�[��W�I�Ƃ�����i
�@�]�ʂ̑j�Q��
�@���{�\�[����W�I�Ƃ���R�ۖ�
�����a�̒m��
�R�́@���A�a�̍����ǂƃ\���r�g�[��
�@�|���y�a
�T�́@����Ԍ����n���ǂƃw���O���r���̗��̍\��
�@�����\���̕ω��Ǝ����F�v���I���a�ƃC���t���G���U
�@�T���h�}�C�h�ى��
�@��_���Y�f��V�A���������̓w���O���r���ɓ������ł��N����
�@���Ԍa�t�B�������g�ƕa�ԁE�����Ƃ̊֘A
�X�́@�R���������R�̏nj�Q
�@�X�t�B���S�����~�Ϗǁi�X�t�B���S���s�h�[�V�X�j
�@�V�g�X�e���[������
10�́@�X�E�����ۏ�
12�́@���N�g�[�X�s�ϐ�
�@�O���R�[�X�A���́iGLUT�j�����������邪��זE
13�́@�Ƒ������R���X�e���[������
�@�����b����PAF�A�Z�`���q�h�����[�[
14�́@���A�����j�A���ǂƔA�f��H�̑�ӈُ��
�@�V�����}�X�X�N���[�j���O�Ώێ����̃A�~�m�_��ӈُ��
�@�|���t�B������
�@���@�t
15�́@���b�V���E�i�C�n���nj�Q
�@�d�Ǖ����Ɖu�s�S�ǁiSCID�j
16�́@NER�֘A�^���p�N���̕ψقɋN�����鎾��
���Տ�����
�T�́@�����w���O���r���CHbA1c �Ɠ��A�a�f�f
�U�́@�y�f��p���������}�[�J�[�̑���
12�́@C�y�v�`�h�����iCPR�j
13�́@���^�{���b�N�nj�Q�i���^�{���b�N�V���h���[���j
14�́@�Տ������ɂ�����AST��ALT����у�-GTP
�@�t�@�\����
�����͖@
�V�́@�j�_�̒�ʖ@
�X�́@�����̒��o�ƕ���
10�́@FRAP�i�u���ސF�@�j�ɂ��g�U���x�̑���
������3�ł̏�
�@�{���̏��ł́C���̐����̍\���Ƃ����̑�ӂ����������w�̗̈�̃~�j�}���G�b�Z���X�������������e�Ƃ��āC�q�g�̂��炾�̍č\�z���R���Z�v�g��2015�N1���ɏ㈲���ꂽ�D���̌�C2019�N�ɉ������ꂽ��2�ł��㈲����Ă���ق�5�N���o�߂����D
�@���̊ԁC2022�i�ߘa4�j�N�x�ɖ�w���烂�f���E�R�A�E�J���L�������̉����i�V�R�A�J���j������C����܂Ŗԗ��I�C�ڍׂɒ���Ă�����ʖڕW�iGIO�j�ⓞ�B�ڕW�iSBO�j��p�~���āC�T�O�������w�C�ڕW�ɉ��߂�ꂽ�D�V�R�A�J���̖{���Ɋւ��w�C�ڕW�ł́C�uC-6 �������ۂ̊�b�v�Ƃ��ăq�g���̂��\�������{�P�ʂł���זE�̐���ƍP�퐫�ɂ��āC�uC-7 �l�̂̍\���Ƌ@�\�y�т��̒��߁v�Ƃ��čזE�C�g�D����ъ튯�̍\���ƍP��I�@�\�ɂ��Ċw�C���C���w�N�ł̎����̗\�h�⎡�ÂɊւ���Ȗڂ𗝉������Ղ��`�����邱�Ƃ����߂��Ă���D�{�����ł́C��2�ł̓��e��V�R�A�J���ɑΉ������ꕔ�q�g�ł̒m���𒆐S�ɏ������߂�Ƌ��ɁC�����w�C���q�����w�݂̂Ȃ炸�w����w�̈�ɂ�����V���Ȓm���Ȃǂ������āC���ȏ��Ƃ��Ă����łȂ��C�w�K�҂̃��x���ɉ����Ď��Ȋw�K�ɂ�蔭�W�I�Ɋw�ԋ��ނƂȂ�悤�ɕҏW��Ƃ��s�����D
�@�{�����ł́C�w�K�̐U��Ԃ�╜�K�̂��߂ɁC�d�v���ڂ̂܂Ƃ߂���Ƃ��Ċe�P���̏I���Ɂu�|�C���g�v���ڂ����D���O�E����̊w�K�ɖ𗧂悤�ɁC�v���ł́u�������Ă������v���C���̏͂�P���Ƃ̊֘A�����邽�߂Ɂu�����ɂȂ���v�����������݂����D�܂��C��2�ł܂ł́u�R�����v����e�I�ɂ������ɕ��ނ��ĕ�����₷�������D���Ȃ킿�C�m���Ă����Ɩʔ������Ƃ�G�w�I�ȋL�����u���m���v�C���i�ƂȂ�����e�̋L�����u���i�̒m���v�C���a�ƂȂ�����e�̋L�����u���a�̒m���v�C�܂��C�Տ�����⌤�����ōs���錟���╪�͎�i�ɂ����ڂ��C���ꂼ��u�Տ������v�C�u���͖@�v�Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂��D����ɔ��W�I�ȓ��e��ŐV�̒m���́u�A�h�o���X�v�Ƃ��ď����������D�{���Ɋ֘A�̂��鐶���w�C���q�����w����ы��E����̉ߋ�10�N���̖�t���Ǝ��������C�����ƊȒP�ȉ�������ĂƂ�܂Ƃ߂āC�V���ɍ쐬�����d�q�ł̕t�^�Ƃ����D�d�q�łł́C�{���̓��e�������Ă���p�ꓮ��������ł���E�F�u�y�[�W���Љ���D��w�����N�ɂ́C���x���ɍ��킹�Ė{�������ɗ��p���Đ����w���w�сC��w�S�̗̂�����[�ߎ��M�����Ă������������D
�@���łɌ���ꂽ����ȕ�������Ȃǂ��ł������C���������C�����s�\���ȂƂ��������Ǝv����D�{���𗘗p���ĉ�����搶�E�w���̊F�l����̂��ӌ��E���w�E�������C���ǂ����ȏ��ƂȂ�悤��������P�ɓw�߂Ă��������ƍl���Ă���D
�@�Ō�ɁC���M��S�������������搶�C��3�ł��o�ł���@���^���Ă�����������]���Ȃ�тɕҏW��Ƃł����b�ɂȂ����o�ŕ������Ɋ��ӂ��鎟��ł���D�܂��C�Z����Ƃł��т��ѕύX�����肢���邱�ƂɂȂ�C���̂��тɑΉ�����������]���̃X�^�b�t�ɐS�����\���グ��D
2025�N1��
�O�c���m
���^�i
���ł̏�
�@�������ۂ����w�I�ɂƂ炦�������悤�Ƃ��鐶���w�̗̈��20���I�ɑ傫�Ȕ��W�𐋂��C����~�ς������ʂ͖c��Ȃ��̂�����D�܂��זE�����w�╪�q�����w�ƗZ������e�[�}�������C���̑��̊�b�̈���܂ߍL���w�˂Ȃ�Ȃ���w���ɂƂ��Đ����w�̓n�[�h���̍����w�K�ȖڂɂȂ��Ă��܂�����������D�������Ȃ���C��Ì��ꂪ���߂��Ȃ���6�N����w����ł́C�̓��ŋN���Ă��鎖�����w�ї������邱�Ƃ̏d�v���͈�w�����Ă���D���̒��ŁC���̐����Ƃ��̑�ӂ����S�e�[�}�ł��鐶���w���w�ԈӋ`�͖��炩�ł���D
�@����C������w���烂�f���E�R�A�J���L�������̐����w�̈�ɉ��������ȏ���ҏW����ɂ�����C�u�q�g�̂��炾�̍č\�z���R���Z�v�g�ɁC�e�����E��ӌo�H���q�g�̂��炾�łǂ̂悤�Ȉʒu�Â��ɂ���̂��������C�e�_�����łȂ��C�����I�ȗ����𑣂����e�Ƃ���v���Ƃ�ڕW�ɁC�e�͂̎��M�҂Ɉ˗������D����Ɏ��a�Ƃ̂������ɂ��Ă��Љ��ƂƂ��ɁC�w����w�ɂ��֘A�����C��t���Ǝ����̕��������ӎ��������ȏ�����ڎw�����D��w���w�������̂킩��₷���\���C��w���w���ɂƂ��ă~�j�}���G�b�Z���X�������������e�Ƃ����R���p�X�V���[�Y�̊�{�ɂ͒��ӂ͕���������ł��邪�C�ǂ����Ă����W�I�ȓ��e�܂œ��ݍ��܂���Ȃ������D����́C�����w�̈����̈悪�L���[���Ƃ������ƂƁC�w�������̎Q�l���ȂǂŒ��ׂȂ��Ă��悢�悤�ɂƔz���������߂ł����育�e�͊肢�����D
�@�{���ł́C�e�͂̊e�區�ڂ̂͂��߂ɃR�A�J���́u���B�ڕW�iSBO�j�v�Əd�v���ڂ́g�Љ�E�܂Ƃ߁h�ł���u�|�C���g�v�����C�w�K�̖ڕW�𗝉����₷�������D�܂��C�u�������Ă������v��u�����ɂȂ���v��݂��C���O�E����̊w�K�ɖ𗧂悤�ɂ����D���W�I�ȓ��e�̓R�����𒆐S�ɏq�ׂĂ��邪�C���߂��K�v�ȗp��Ȃǂ̓T�C�h�X�y�[�X�ŕ⑫�������ď[����}�����D�}�\�ɂ��u�����ځv���痝��������Ƃ����_���ӎ���������ł���D�e�͖��ɂ͗��K���ł���uExercise�v��݂��Ċe���ڂ̗���x���m�F�ł���悤�ɂ��Ă���CCBT��ɂ��𗧂ĂĂ������������D
�@��w�����N�ɂ͖{����P�ɍu�`�Ȗڂ̋��ȏ��Ƃ��Ďg�p���邾���łȂ��CCBT���t���Ǝ����Ɍ����Ďg������ł����������Ƃ�����Ă���D�܂��C�ǎҏ�������̂��ӌ��E���w�E�����������Ȃ�����ǂ����ȏ��Ƃ��Ă��������ƍl���Ă���D���ӌ������肦��K���ł���D
�@�Ō�ɁC���M��S�������������搶���ɂ́C�Z���Ԃɐ��͓I�ɍ�Ƃ𐋍s���ĉ����������ƂɊ��Ӑ\���グ��D�܂��C�{�����o�ł���@���^���Ă����������i���j��]���Ȃ�тɕҏW��Ƃł͌��t�Ɍ����\���Ȃ��قǂ����b�ɂȂ������ȏ��o�ŕ������ɐS��芴�ӂ��鎟��ł���D
2014�N11��
�O�c���m
���^�i

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)

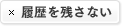
����
���ē�