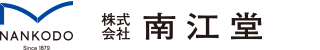やさしい腫瘍学
からだのしくみから見る“がん”
| 著 | : 小林正伸 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26991-4 |
| 発行年月 | : 2014年12月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 240 |
在庫
定価3,520円(本体3,200円 + 税)
サポート情報
-
2022年07月01日
最新情報に基づく情報更新
正誤表
-
2024年05月30日
第1刷〜第4刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

「がんの本態」「がんの診断」「がんの治療」に関する基礎的な知識を、生理学の観点から理解できるよう解説。オリジナルの豊富な図表とていねいな本文解説でやさしく読み進めることができる。医・薬学部、認定看護師養成課程で腫瘍学を教える筆者による、ツボを押さえた解説で日ごろのがんに対する疑問を楽しみながら解決。明日の実践に活かせる一冊。
第I章 正常細胞の誕生と増殖と死
1 正常組織の恒常性を維持する機構
A 今日のあなたは昨日のあなたと同じ?−新陳代謝の意義
B ヒトの細胞にはなぜ寿命があるのか?
C 臓器の恒常性維持はどのように行われているのか?
(1) 細胞の寿命とは何か?
(2) ヘイフリックの限界を乗り越える細胞の存在−幹細胞システムの意義
a■ 組織幹細胞
b■ 幹細胞としての生殖細胞
c■ 幹細胞はなぜ必要なのか?
2 正常細胞はどのように生きているのか?
A 正常細胞の生存に必要な要素は何か?
B なぜ分解して吸収するのか?
C 吸収された栄養はどのように絶え間なく供給されるのか?
D エネルギーはどのように産生されるのか?−酸素・栄養供給の必要性
(1) ATPの産生−嫌気性解糖系とTCA回路の違いは何か?
(2) 酸素と栄養を運ぶ血管
3 正常細胞はどのように生まれるのか?
A 正常細胞はどのように増殖をスタートするのか?−増殖因子と増殖因子受容体
(1) 外傷後の修復過程
(2) 増殖因子の働きは何か?
B 増殖の指令はどのように核まで伝わるのか?−シグナル伝達の役割
(1) シグナル伝達の意味
(2) シグナル伝達のメカニズム
(3) 増殖因子のシグナル伝達に関与するタンパク
C 細胞周期
D 分化の機構
4 老化した細胞はどのように死ぬのか?−細胞の死の制御機構
A 細胞死の役割は何か?
(1) 単細胞生物から多細胞生物へ
(2) 老化した細胞の排除
B 大部分の細胞の死は自殺なのか?−自殺と他殺の意義
C 細胞の生と死を決めるメカニズムは何か?
D 死を誘導するメカニズムがあるのか?−死のシグナルの意義
(1) ミトコンドリアを介する死のシグナル
(2) 死の受容体を介する死のシグナル
E 細胞死の例−ウイルス感染細胞のリンパ球による排除
第II章 がん細胞の誕生とがん細胞の特徴
1 がんの特徴−がんとは何か?
A 腫瘍とは何か?悪性腫瘍とは何か?がんとは何か?
(1) 腫瘍とは何か?
(2) 悪性腫瘍とは何か?
(3) がんとは何か?
B 単クローン由来の証明
(1) X染色体による証明
(2) 成人T細胞性白血病による証明
C がんは何年くらいかかって大きくなるのか?
(1) 1個のがん細胞から直径1cmのがんへの経過
(2) 直径1cmのがんになるための計算上の分裂回数
(3) 広島と長崎の原爆被爆からわかること−ヒトでのがん発生の時間経過
(4) 膵がんの進展の経過
2 がん細胞はどのように誕生するのか?
A がん遺伝子とは何か?
(1) がんウイルス
a■ がんウイルスの発見とがん化の原因遺伝子存在の推測
b■ がんウイルスの遺伝子と原がん遺伝子の発見
(2) がん遺伝子の誕生のメカニズム
(3) 原がん遺伝子の本来の役割
a■ 原がん遺伝子の役割の発見
b■ 原がん遺伝子と細胞増殖
c■ 増殖シグナルが常時スイッチオンとなるメカニズム
B がん抑制遺伝子とは何か?
(1) がん抑制遺伝子の存在の確認
a■ がん細胞と正常細胞の融合
b■ クヌドソンのツーヒットセオリー
(2) がん抑制遺伝子の本来の役割−p53の機能
(3) がん抑制遺伝子の喪失はがん細胞に何をもたらすのか?
C 遺伝子異常は1個で十分か?
(1) 遺伝子対rasとmyc −両遺伝子の活性化によるがん化
(2) ヒトの細胞のがん化に遺伝子異常は何個必要か?
3 がん細胞は細胞死しにくいのか?−細胞死機構における変化
A 細胞死誘導シグナル伝達系の異常−アポトーシス抵抗性
B テロメラーゼ活性と細胞の不死化
4 がんの原因は何か?−遺伝子の変異をもたらしている原因
A がんのなりやすさは遺伝するのか?−遺伝要因と環境要因
B 遺伝子変異とDNAポリメラーゼのミス
(1) 放射線被曝や発がん物質
(2) DNAポリメラーゼのミス
(3) DNAポリメラーゼのミスの意義−進化への貢献
C 放射線の与える影響
D 化学発がん物質の作用
(1) 職業がんから化学発がん物質の発見
(2) 化学発がん物質
(3) たばことたばこの煙に含まれる化学発がん物質
E 感染によるがん発症
F 重層的ながんの原因
5 がん化に必要な血管新生
A がん細胞は豊富な栄養と酸素に恵まれているのか?
B がん組織における酸素濃度
C 血管新生のメカニズム
6 がん幹細胞
(1) がん幹細胞の証明−白血病幹細胞
(2) 正常幹細胞とがん幹細胞の関係
(3) がん幹細胞の意義
第III章 どのように人はがんで死亡するのか?−転移
1 転移こそがん死亡の原因か?
A がんの進展過程(原発巣の増大と転移)
B がんの進行に伴う転移の増加
(1) 病期の進行に伴う転移の増加が生存率低下をもたらす
(2) 進展に伴う不均一な細胞集団の形成−転移能力の獲得
2 転移先臓器の特異性
A 転移先として多い臓器とその理由−血液循環の役割
B がんの違いによる転移先の好み(!?)の違い
(1) 肺転移、肝転移
(2) 骨転移
3 がん細胞の転移機構
A 正常に起こる細胞の移動とその機構
(1) 白血球の移動
B がんの転移に必要なステップは何か?
(1) 血管新生とがん細胞の血管内への侵入
a■ 血管の形成
b■ がん細胞がバラバラに離れる
c■ 血管内へ侵入
(2) 転移臓器での血管外脱出
a■ 造血幹細胞の骨髄定着機構
b■ がん細胞の骨髄への定着機構
c■ がん細胞の肺、肝定着機構(仮説)
(3) 転移臓器内での増殖
4 がん細胞はなぜ転移するのか?
A ケモカイン仮説
BS eed &Soil Theory(種と畑仮説)
C 微小環境仮説
第IV章 がんの診断
1 がんはどのように診断するのか?
A がんの診断の実際の流れ
(1) 肺がん診断の例
B スクリーニング検査
(1) スクリーニング検査とは
(2) スクリーニング検査のデメリット
(3) スクリーニング検査の有用性と実際
2 腫瘍マーカーとは何か?
A 腫瘍マーカーの定義
(1) 腫瘍マーカーの探求
(2) 腫瘍マーカーの意義
B 腫瘍マーカーの臨床的意義
(1) がんのスクリーニング検査としての意義
(2) がんの進展度診断における意義
(3) 治療効果のモニタリング
(4) 再発の監視
3 がんの確定診断には何が必要か?
A 細胞診
(1) 細胞診で診断可能な疾患
B 病理組織診断
4 病気の進行度(病期)はどのように診断するのか?
A 病期診断の意義
B 病期分類
C 病期ごとの治療法選択
5 最新の診断法
APET /CT検査
B 遺伝子検査
(1) がん特異的変異タンパクの検出
(2) 遺伝性/家族性がんの遺伝子異常の検出
(3) 予後の予測のための遺伝子検査
第V章 がんの治療
1 進歩するがん治療
(1) 個別化医療の進捗
(2) 手術方法の進捗
(3) 放射線療法の進捗
(4) 支持療法の進捗
2 がんの手術療法
A 拡大手術から縮小手術へ
B 手術療法の実際の方法
C 手術療法の選択
D 内視鏡手術の進歩
E 鏡視下手術の進歩
F 高齢者に対する手術療法の進歩
3 がんの放射線療法
A 姑息的治療法から根治療法へ
B 放射線療法の進歩
(1) 定位放射線治療
(2) 強度変調放射線治療
(3) 密封小線源治療
(4) 粒子線治療
C 緩和治療としての放射線療法
4 がんの化学療法
A がん化学療法の基礎
(1) 抗がん薬開発のきっかけ
(2) 主な抗がん薬の抗腫瘍メカニズム
a■ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)
b■ プラチナ製剤
c■ アルキル化薬
d■ 抗がん抗菌薬(アントラサイクリン系)
B がん化学療法のメカニズム
(1) 白血病に対する化学療法
(2) 固形がんに対するがん化学療法
(3) がん化学療法が治癒に結び付く理論的条件
(4) 進行期固形がんに対する化学療法はどこまで効くのか?
a■ ステージIV期の非小細胞肺がんに対する化学療法
b■ ステージIV期大腸がんに対する化学療法
C 術後補助化学療法
(1) 術後補助化学療法の理論的根拠
(2) 術後補助化学療法の実際
(3) 術後補助化学療法の効果
D 術前化学療法
E がん化学療法の副作用
(1) 消化器症状
a■ 悪心・嘔吐
b■ 下痢
(2) 骨髄抑制
a■ 抗がん薬による骨髄抑制
b■ 顆粒球減少時の感染リスクと対策
(3) 脱毛、皮膚症状
a■ 脱毛
b■ 手足症候群
c■ 爪障害
(4) 神経症状
(5) 薬剤性間質性肺炎(肺障害)
(6) 心毒性
(7) 肝障害
a■ 直接の肝細胞障害
b■ ウイルス肝炎の活性化
(8) 腎障害
a■ 腎への直接作用
b■ 腫瘍崩壊症候群
c■ 腎障害の予防
F 抗がん薬耐性
(1) 細胞膜の変化、薬剤の膜輸送機構の変化
(2) 標的酵素、タンパクの増量
(3) 薬剤代謝の変化による薬剤耐性
(4) 傷害修復機構、DNA修復の亢進
5 先端医療
A 免疫療法
(1) がんに対する免疫応答
a■ 放射線照射がん細胞の皮下移植によるがん細胞特異的免疫の誘導
b■ がん細胞に対する免疫寛容の例
c■ 低親和性特異的T細胞の存在する可能性
B 新しい免疫療法
(1) 抗体療法
(2) 樹状細胞や活性化リンパ球の移入療法
(3) ペプチドワクチン
C 分子標的治療
(1) 分子標的治療薬の種類
(2) 分子標的治療薬のメカニズム
(3) 分子標的治療の効果
第VI章 がんの予防
1 そもそもがんの予防は可能か?
A がんの原因
(1) 化学物質
(2) 放射線
(3) たばこ
(4) 動物のがんが示唆すること
B 減っている「がん」はあるのか?
C がんのリスク要因
2 効率的ながん予防−高リスク要因をもつグループを対象に
A 高リスクグループ
(1) ウイルス感染者、ヘリコバクター・ピロリ菌感染者
a■ 肝炎ウイルス
b■ ヒトパピローマウイルス
c■ ヘリコバクター・ピロリ菌
(2) 喫煙者
(3) 遺伝子異常、変異をもつ人
(4) 肥満、やせ体型の人
(5) 運動不足の人
索引
はじめに
がん(悪性腫瘍)は,「ある1つの正常細胞に複数個の遺伝子変異が入り,外からの刺激なしに増殖できる自律増殖能を獲得し,さらに転移・浸潤する能力を獲得したために,宿主を死にいたらしめる細胞の塊」のことをいう.現在がん罹患者全体の約半数が治癒するようになったとはいえ,死亡率が50%もある疾患であることを考えると,今でもやはり難治性の恐ろしい疾患といえる.日本では1981年以来死亡原因の第1位を占め続け,死亡者の約3分の1(30数万人)ががんで亡くなっており,今後も増加することが予想されている.
100年近くになる現代医学研究の成果によって,がんの原因となる多数の「がん遺伝子」「がん抑制遺伝子」が同定され,がん細胞の増殖に特徴的な自律増殖のメカニズムが明らかにされてきた.また,転移を引き起こすメカニズムに関与する遺伝子変異,がん細胞が抗がん薬や放射線照射に抵抗性になるメカニズムに関与する遺伝子などが明らかにされてきた.さらに2003年にはヒトの全DNA配列が解明され,がんを克服できる日も近いのではないかと期待された.しかしながら,これらの研究の成果として開発されてきた多くの抗がん薬や分子標的治療薬は,一部の薬剤を除くと期待されたような「がんの治癒」をもたらすものではなく,せいぜい数ヵ月間の生存期間の延長をもたらすのみであった.今後の研究の進展によっては,末期がんでさえ治る時代がくる可能性を否定することはできないが,ここしばらくの間は,現在の治療の新しい組み合わせや新薬の追加などで一歩一歩前進を図るのが精一杯という現状にある.
筆者はこれまで認定看護師センター,医学部,薬学部で腫瘍学を教えてきた経験より,学生ばかりでなく,がんを専門に扱っている医療従事者でさえも,「がん細胞は無限に速く増殖してくる」「がん遺伝子という特別な遺伝子に異常が入っている」「転移で亡くなるのはわかるが,転移がなぜ起こるのかはわからない」といった誤解や疑問をもっていることを知っていた.また,そうした誤解や疑問に対して,正確な情報をわかりやすく解説した教科書がなかなか見当たらないと感じていた.そこで本書は,長年のがん研究によって明らかにされてきたがんの本態を理解しやすい形にまとめ,「がんの病態」「がんの診断」「がんの治療」に関する最新の知見を,医療系の学生,がん医療に従事する医師,看護師,薬剤師,放射線技師などすべての職種の方たちに理解してもらうことを目的として,新たに書き上げることにした.
本書では,まず「第I章 正常細胞の誕生と増殖と死」で正常細胞の増殖と死がどのように制御されているのかを説明したうえで,「第II章 がん細胞の誕生とがん細胞の特徴」でがん細胞にどのような変化が起きたのか,その結果がん細胞の増殖と死が正常細胞とは異なる制御を受けるようになったのかを説明する構成になっている.なぜこのような構成をとって,がん細胞とはまったく異なると思われる正常細胞の増殖機構をくどくどと説明するのか理解しがたいかもしれない.しかし,こうした構成にしたのにはそれなりの理由が存在する.がん患者を長らく診ていると,たとえ治癒切除ができたと思えるような症例でも,がん細胞が1個でも残されてしまうと再発してしまい,最終的には患者の死を避けることができない,といった経験をしばしばすることがある.このようながん細胞の異常な増殖能を実感すると,がん細胞の増殖が何か特殊なスーパーマンのような超常的機構をもっているように錯覚してしまうことがある.しかし,がん細胞といえども正常細胞から出発しており,正常細胞の増殖機構を利用しつつ,いくつかの変化の積み重ねによって正常細胞とは異なる増殖機構を示すことになったと考えられ,正常細胞の増殖と死のメカニズムとまったく異なる特殊な機構をもっているわけではない.本書では,こうしたがん細胞に対する理解に基づいて,まず正常細胞の増殖と死の機構を説明することからはじめ,続いてがん細胞に特異的な増殖と死に対する抵抗性について触れた.
次に「第III章 どのように人はがんで死亡するのか? −転移」で,なぜがん細胞だけが遠隔臓器に移動しそこで増殖する,「転移」という能力を獲得するのかというメカニズムに触れている.がん患者の生死が転移の有無で決まっているのにもかかわらず,転移を制御する治療法の開発は進んでいない.本章では転移のメカニズムを,原発がん組織の環境レベル,がん細胞と正常細胞の協力関係,造血細胞のホーミング機構の転用,といった多方面からの解析結果をまとめて得られた最新の仮説に基づいて解説した.
診断と治療に関しては,「第IV章 がんの診断」および「第V章 がんの治療」で,多くの臨床研究の成果として明らかにされてきた,現段階における最新の標準的診断方法,治療方法を解説した.
また今後は,「がんの予防」が重要な課題となってくると考えられ,「第VI章 がんの予防」では「がんの予防」の世界的標準となっている事実を解説して,今後のがん予防の進む方向性を示した.
本書は最新の情報に基づき執筆したが,読者の皆さんには勉強を続け,本書の理解のうえに新たな知見・変更点を加えていってほしい.最後に本書が,“がん”を科学的かつ正確に理解できるようになり,より深く広い知識に裏付けられた臨床実践となる一助になってくれればと切に望んでいる.
2014年11月
小林正伸
悪性腫瘍がわが国の死因のトップを占めるようになって久しい。毎年30万人を超える人ががんで亡くなっており、男性では2人に1人、女性でも3人に1人ががんで亡くなるといわれている。そう、わが国は立派ながん大国なのである。毎年、がんの死亡者が増え続けているが、高齢化が進んでいるため仕方がないとされてきた。しかし、米国ではがんに対する対策が成功しており、がんの死亡率が減少してきている。先進国では米国のようにがんの死亡率が減り始めているのに、わが国だけが増え続けているのが現状である。したがって、わが国のがん対策は正しくないことが理解できる。わが国のがん対策のどこが間違っていたのかを検討するのに最適な本が発行された。それが本書である。
著者の小林正伸先生は血液内科の医師として白血病などの難治がんの化学療法に従事した後、基礎のがん研究者に転じ大きな業績をあげてきた。これまで腫瘍学の教科書は主として基礎の研究者の立場から書かれたものが多い。そのため学問的レベルは高くても実際の臨床とはかけ離れている可能性が指摘されてきた。本書は、基礎、臨床の記載のバランスが見事に調和し、学問的にも最新の知識が満載され、わかりやすいのみならず腫瘍学を実際に臨床応用するための方法論が詳細に述べられている。まずは腫瘍を理解するための基礎的事項が丁寧に解説されている。「がんとは何か」の項では腫瘍、悪性腫瘍、がんについてそれぞれの本質が述べられているが、説得性に富んでおり、読者はこのあたりから本書に没入していくと思われる。「がんは何年かけて大きくなるのか」は腫瘍学の核心というべきところであるが、最新の情報である膵がんの進展の経過を入れて考察していることで説得性を増している。
本書の真骨頂は臨床についての記載である。なぜがんで亡くなるのかという腫瘍学の原点について、転移を主体に最新の知識を余すことなく述べてくれている。わかりやすくポイントをしっかり押さえて記載されているが、これは小林先生が臨床の医師であったことの証しでもある。彼の専門のがん化学療法についても詳述されており、効果と限界そして重要な副作用について必要かつ十分な知識を得ることができる。
最後の章でがんの予防について述べられているが、すべて一次予防のみの記載である。一次予防を行うためには原因が明らかにされていなければならない。わが国のがん対策の遅れのもっとも大きな原因は、がんの二次予防のみに大きな力が入れられていることである。二次予防のみ行ってもがんを撲滅できないことは科学的に自明である。本書では、がん予防の章に二次予防である検診についてはまったく記載されていない。著者の優れた見識であろう。
臨床雑誌内科116巻4号(2015年10月号)より転載
評者●北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座特任教授 浅香正博