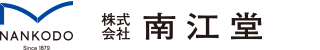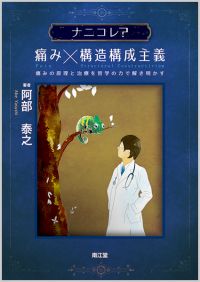ナニコレ?痛み×構造構成主義
痛みの原理と治療を哲学の力で解き明かす
| 著 | : 阿部泰之 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26587-9 |
| 発行年月 | : 2016年6月 |
| 判型 | : A5 |
| ページ数 | : 160 |
在庫
定価3,080円(本体2,800円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

“構造構成主義”という哲学から痛みを捉えようとする新たな試みの書。構造構成主義を用いて理論的に痛みを解説し、さらに、理論を臨床に役立たせる実例も併せて提示。親しみやすいイラストで、痛みを“哲学”することをやさしく解説した。痛みを診るすべての医療者はもちろん、痛みを理解したい一般の方へもおすすめの一冊。
はじめに(序章)
本書の構成
本書の読み方
1章 痛みをめぐる様々な問題
痛みとは何か
痛みとルネ・デカルト
痛みとルードヴィヒ・ウィトゲンシュタイン
現代において痛みとは何か
人が医療を求める一番の理由は“痛み”
生物学的な視点から離れてみる
現代医療では痛みは二の次?
患者の期待を裏切る現代医療の枠組み
困らない痛みと困る痛みがある
いったい何が問題なのか
痛みは科学的視点だけではよくできない
人間はいつから痛みを「科学的」に捉え始めたのか〜デカルトから読み解く
「科学的」な視点で扱えるのは機械論的身体のみである
痛みとは何か,それを“どう”考えたらよいか
どうして哲学なのか
2章 構造化に至る軌跡の提示としての自己開示:志向相関的自己開示
自己開示をすることの重要性
構造化に至る軌跡とは
人間の意味や価値を研究する場合には条件開示が重要になる
志向相関的自己開示
志向相関的自己開示−痛みの理解と対応の遍歴
3章 構造構成主義とは何か
構造構成主義とは何か
量的研究と質的研究の対立
量的研究の背景は(論理)実証主義
質的研究の背景は(社会)構築主義
構造構成主義は違う世界観,世界認識を持つもの同士がわかり合うための理論
構造構成主義は多元論
原理とは
構造構成主義の中核原理を理解しよう
中核原理を理解する:(1)現象〜立ち現れたすべてのもの
中核原理を理解する:(2)志向相関性〜受け取り方が変わると世界が変わる
中核原理を理解する:(3)契機(相関性)〜志向が生まれ,変わる「きっかけ」
中核原理を理解する:(4)構造〜契機志向相関的に構成され続けるもの
その他の原理
(5)戦略的ニヒリズム〜あえてニヒルからスタートする
そもそもニヒリズムとは
あえてニヒルから始める
構造構成主義における戦略的ニヒリズム
(6)方法の原理〜方法のよさは状況と目的によって決まる
(7)問い方のマジック〜どちらが正しいかという問いにはリスクがある
4章 構造構成的痛み論
国際疼痛学会「痛みの定義」にみる限界
画期的な痛みの定義−国際疼痛学会
国際疼痛学会が痛みに対する(論理)実証主義的視点を強めた?
スローガンだけでは現場は変わらない
新しい痛みの定義とその意義
痛みとして立ち現れたすべては痛みである
痛みとは構造である
理論の賞味期限?〜賞味期限の長い理論をベースに,賞味期限の短い理論を使い分ける
慢性的に続く痛み≠慢性痛症
5章 痛みという構造理解のための切り口(志向性)
ここでいう“切り口”とは
痛みに関する様々な切り口
客観的実在としての“感覚”
痛みと抑うつ
オペラント学習
アレキシサイミア
転換性ヒステリー(転換性障害)
認知の歪み
痛がりの遺伝子
痛みの感じ方=閾値
痛みを引き起こす社会背景
痛みの“意味”
愛は痛い人を救う?
6章 治療論に入る前に−「他者承認の原理」を知る
治療論に入る前に
原理を実践に落とし込むための乗り越えるべき壁
「信じる」こと,「覚える」ことの不安定さ
人間関係の原理としての他者承認
他者とは何か〜フッサールとレヴィナスの「他者論」より
他者承認の原理〜他者からの応答により他者が生起する
対人援助の原理としての他者承認
援助する者とされる者との不均衡さを認めよう
ある医学生との対話から〜他者承認の原理を身につけるには
ユマニチュード〜臨床における他者承認の具体的な現れ
7章 原理を実践に活かす−構造構成的慢性痛症治療
志向を捉えて“よき”構造を構成する
痛みの意味づけを変えるということ〜中村さんの例より
構造(痛み)に働いている志向(背景,意味づけ)を探る
痛みの意味づけを変えていく
構造をなくしてしまうのではなく,構造を望ましいものに構成しなおす
治療関係の“形”をつくる
形(1)「まな板の上の鯉」スタイル
形(2)「いっしょに痛みをやっつけよう」スタイル
形(3)「私はあなたのガイド」スタイル
鍼灸治療は「ガイド」スタイル?
診断名をつけない!?
診断名=名づけをしない
名づけは恣意的である
診断名は思考をしばる
構造を意識させる〜どんな言葉を投げかけるか
「痛みの悪循環を断つ」
「痛みの記憶(記憶としての痛み)」
「現に痛みはある」
「梅干しを想像してみて」
「うまくやれていますね」
契機としての薬物療法
薬物療法は契機である
以前効かなくても,今なら効くことがある
対病名ではない薬剤選択
薬剤をいつやめるか〜オピオイドを例として
薬物療法はバランスゲーム
構造構成的慢性痛症治療の実践例
nihilistic painの解明〜これからの展望として
現代人のニヒリズム
痛みの臨床で見られるニヒルさ〜nihilistic pain
これからの展望〜ニヒルさの緩和の効能は医療に限らない
あとがき
謝辞
はじめに(序章)
ライオンキングをご存知ですか。いわずと知れたディズニーのアニメーション映画です。その後、文楽や歌舞伎、影絵などの手法を取り入れたミュージカルとして再編され、ブロードウェイをはじめ世界中で愛される大ヒット作品となっています。日本でも劇団四季がミュージカル・ライオンキングを上演し続けており、2015年7月に前人未到の日本公演10,000回を達成しました。私も子どもにせがまれてミュージカルを観に行きましたし、自宅でもDVDを何回も見る羽目になっています。
本書を書き出してから、ライオンキングのある場面がどうにも気になり出しました。物語の中盤、主人公のシンバ(ライオン)、友達のティモン(ミーアキャット)、プンバァ(イボイノシシ)の3人が仲よく夜空を見上げるシーンです。
プンバァ「あのキラキラ光ってるのはなんだろうな 考えたことあるか」
ティモン「まったく 考えるまでもなく知ってるよ ホタルさ ホタルが山ほど飛んできて あの黒いところに捕まっちまったってわけだ」
プンバァ「ほお オレはまたてっきり何十億キロも遠いところでさ ガスのかたまりが燃えているのかと思ってたよ」
ティモン「お前 ガスのことしか頭にねえのかよ」
プンバァ「シンバ お前はどうだ?」
シンバ 「さあ 知らないよ」
ティモン「つきあい悪いぞ いいから言ってみな早く言えよ」
シンバ 「誰かがこんなことを言ってたな 死んでいった王さま達が おれ達を見守っている……」
プンバァ「ほんとに?」
ティモン「死んだ連中がピカピカ光って見守ってるって!? プー ウハハハハハ アー ハハハハハ 世界一のほら吹き野郎だ」
シンバ 「ハハハ バカだよな……」
この3人の“星”についての見解の違いは、大きな世界観の違いを見事に表しています。プンバァの言っているのは、まさに科学の視点で見た星の解釈です。現代人の多く、もしくは本書を読んでいる人のほとんどは、星とは何か?と聞かれれば、おおむねプンバァと同じような答え方をするでしょう。本文でも繰り返し出てきますが、近現代の人達が自然と身につけているものの見方という意味で、これを「自然的態度」(p31参照)といいます。科学的な解釈方法・態度の一番の欠点は、物事の意味や価値を説明できないことです。科学はwhyには答えられません。ただhowを説明するのみです。
ティモンの解釈は宗教や神話に近いものです。「ホタルが飛んで行って捕まってしまった」多くの宗教・神話には、このようなストーリーがたくさん用意されています。批判を恐れずに言い切ってしまえば、宗教・神話が共通して持っている基本的機能は、世界や物事をあるひとつの物語として説明することです。そうして、出来事の意味(大災害が起きたのは、神が世界を創り変えようとしているためである、とか)、ルールや規範・道徳(因幡の白ウサギはワニ(鮫)をだますようなことをしたからひどい目にあった、だから人を騙すのはよくない、とか)を説明し共有しようとするのです。ティモンが言ったホタルの件りにも、ひょっとすると、どれだけ魅力的なものであっても、皆で一斉に飛びつくとロクなことはない、というような道徳的な話が続いていたのかもしれません。
では、シンバの言っていた“星”はどのような世界観に基づいているのでしょうか。それを説明するには、シンバの置かれていた状況を思い出す必要があります(ライオンキングをよく知る人には不要でしょうが)。シンバは父親のムファサに続いて、次の王になるべきライオンでした。しかし、シンバが王になることを羨む叔父のスカーの策略にはまり、父親殺しの責任を負わされて王国から追放されてしまいます。父親が死んだのは自分のせいだと考えているシンバにとって、父親、そして王という存在を考えることは、大きな葛藤を伴うことであり、特別な意味を持っています。つまり、シンバが「王」という言葉を使うとき、そこには他の人が「王」というときとはまったく違う個別的な意味や価値を含んでいるのです。このように現実とは、そこに生きる人々が意味づけをすることにより構成されていくものだという考え方は、(社会)構築主義的な世界観と言えます。
まさに「三者三様」の世界観でしたね。では、本書で大事にしたい世界観は、はたして3つのうちのどれでしょう?
−答えは“ぜんぶ”。ずいぶんと都合がいいように感じられるかもしれませんが、“ぜんぶ”大事にしたいと思っています。
本書のテーマは痛みです。痛みはありふれたものです。痛みを経験しない人はいません。それゆえに実に悩ましいものでもあります。我々は一生のなかで幾度となく痛みを味わって苦痛を感じ、そして戸惑い、また痛みを訴える他者をなんとかしてあげたいと共感しながら、多くは徒労に終わっています。そして、私は痛みを診る医者です。臨床において痛みで苦しむ患者さんの治療やケアにあたってきました。一所懸命診ますが、なかなかよくならない痛みがたくさんあります。ときには、(よくしてあげられなかったゆえ)去っていく患者さんもいます。それでも、どうしたらよいのだろう、そもそも痛みってなんだろう、そうやって考えに考えていくなかで、タイトルにある「構造構成主義」という哲学にたどりつきました。この哲学を使えば、先ほどの“ぜんぶ”の世界観を包括し、調停することが可能だ、という考えに達しました。それで、本書を書くことにしました。
哲学の話が出てきますので、“難しい”と感じる方も多いかもしれません。ただ、「痛み」という壮大かつ複雑怪奇な現象を解きほぐし、その治療にあたる我々の立ち位置を根本から考え直すには、これだけの量の論述が必要でした。「気軽に楽しんで読んでください!」とは言いません。人によっては、文章を行きつ戻りつ、“格闘”しながら読むことになるかもしれません。それでも、いや、それゆえ、読み終えた際には、皆さんのなかで、「痛み」というものの理解に革新的な変化が起こると思います。そして、それは皆さんが治療しケアする患者さんにも確実にフィードバックされることでしょう。
さて、プンバァ、ティモン、シンバ、彼らの世界観はすべて大切にしたいと思います。でも、やはり主人公であるシンバに肩入れしたくなるのが、人の情ってものです。その後、シンバは自分のなかの葛藤にきちんと向かい合い、それを克服し、王国を取り戻します。私たちも痛みという大いなる葛藤と、今一度向かい合わなければならないのでしょう。そして、痛みで苦しむ人がいない、それは夢のようなことですが、そういう“王国”を目指したいものだ、と思います。
さあ、序章はこれくらいにして、そろそろ“格闘”を始めましょう!!
痛みと構造構成主義という新しいパラダイム
「○○さんは抗菌薬が奏効して熱も下がり、CRPも低下しています。
腰痛はまだ残っていますが、ほかに問題はありません」
「で、その腰痛はどうなったの?」
「??」
「××さんは頭痛と発熱で受診されました。血液検査では……
これから培養とって、ペコポコマイシン使おうと思います」
「で、この患者さん、なんで頭痛いんだろ」
「???」
この手の問答を何年も繰り返し行ってきた。かくも医療現場が痛みに無配慮、無神経なのだ。近年でこそ「緩和ケアチーム」の充実で疼痛対応は充実してきたが、「緩和」という文字の印象が早期の介入をためらわせる。そして、血液検査や画像検査で異常がみつからない疼痛を低くみる。これは、医療者のみならず患者にも少なからずみられる傾向だ。痛みに苦しむ患者は、「検査の異常がありません」というととても嫌そうな顔をするのである。
本書は「痛み」をターゲットにしているが、「そもそも痛みとは何か」という根源的な問いから始めているところが、きわめて特徴的だ。痛みは測定できず、その実在さえしばしば証明できない(よって懐疑の対象となる)。
懐疑は、即座の存在否定とは異なる。思考に思考を重ねて、その存在がどうしても否定せざるをえない場合にのみ否定するような、デカルト的アプローチが必要だ。しかし、多くの医師は即答型の思考に慣れているため(日常診療のほとんどが「即答」からできているからだ)、このような射程の長い徹底的懐疑には慣れていない。よってシンプルに「ない」と断定する、より楽な道を選択する。
量的に実証できない対象には質的なアプローチ、たとえば質的研究、が可能だが医学界(とくに医師のサークル。ナースは必ずしもそうではない)では質的研究はまだまだ人口に膾炙していない。私も先日投稿した質的研究で査読者に「Nが不十分で統計的解析がない」という批判を受けて苦笑した。
このような世界観の克服に有用とされるのが西條剛央氏が提唱する「構造構成主義」である。痛みのように度量しがたい対象については、多元的なアプローチが有用である。多元的なアプローチには自分のアプローチ、自分の世界観を一回離れ、そうでないアプローチの存在を容認しながら「痛み」を解釈、判断する必要がある。痛みの診療において構造構成主義的アプローチは親和性の高いアプローチだ。
思考の多重性を容認し、二元論を廃し、信念対立を克服せんとする構造構成主義は現代日本医療における非常に有効な思考法だと思う。しかし、二元論の克服は困難で、この援用には慎重を要する。たとえば、本書では構造構成主義的痛み論と従来の痛みに関する個別理論が対比されている(p66)が、これこそが二元論的思考に陥ってしまっている。幻肢のように、従来の科学的痛み解釈には限界があるかもしれない。しかし、そのわかっているところとわかっていないところの了解線を引く唯一の方法は、実はコンベンショナルな科学的方法である。この辺りのジレンマを乗り越えれば痛みの医療はもっと豊かで、患者に有益なものになるんじゃないか。私はそう考えている。
池田清彦先生の「構造主義科学論の冒険」には、次のように述べられている「コトバとは変なる現象から不変なるなにかを引き出すことができると錯覚するための道具のひとつなのです」。この本は繰り返し読んだが、この文章がさっぱり理解できなかった。本書を読んで、その引用箇所にいたったとき、私はようやく腑に落ちた気がしたのである。本書を読む価値がいかに高いか。私はそれを説明しようとしているが、伝わるだろうか。
臨床雑誌内科118巻4号(2016年10月号)より転載
評者●神戸大学医学部附属病院感染症内科教授 岩田健太郎
「痛みとは何なのか?」。このことについて筆者自身は整形外科医であったので毎日痛みの患者の診療をする中で、どこかに原因があるはずだと考えて取り組み、原因がわからず痛みを改善できなければ、何故だ? どうしてだ? と悩んできた。同じようなことを他の医療者や研究者だけでなく、長引く痛みをもち悩んだことのある人も考えたに違いない。筆者自身は、国際疼痛学会が定義したように、「脳」で経験する「不快な感覚情動体験である」ということに基づいて、神経科学的な手法でもって痛みをとらえる試みを繰り返しつつ、日々の臨床では難治性の腰痛などの診療に取り組んできた。
臨床家としての筆者はそんな毎日を送ってきた中で、なんとなくこのようなものが「慢性痛」であるというイメージが、最近になってようやくわかってきたように思っている。しかし、いざ「痛みが何なのか?」ということを具体的に文章にして伝えようとすると、これは非常にむずかしいものである。
本書は著者・阿部泰之先生の人柄もあってか、やさしい言葉で書き上げられている。しかし、小説のように決してすらすらと読んでいけるものではない。本書では「痛みを構造として位置付けており、これが契機・志向に影響され続けて変わっていくものである」としている。
突然そういわれても何のことかまったくわからないことであろう。本書は哲学書なのである。すなわち、物事の原理(ここでは痛みの原理)を論述している本なのであり、痛みに関する課題を言語化した例を示しながら一つずつ言語化し、構造構成主義でもって慢性痛が何であるのかを示している書である。したがって、そうすらすらと読めるはずはない。そのため、本書を読む際に著者は冒頭で「本書の読み方」というページをつくってくれているので、これはありがたい。
筆者の場合、指示通りにまずは読んでみた。著者が自ら書いているように、筆者には馴染みのない考え方なのでいったりきたりであるが、まずは1回読破した。なんとか、著者の考えていることは理解することができたように感じた。しかし、書かれていることを人に説明するには不十分であったので、再度読み返して現在にいたっている。
その結果感じるところは、本書は筆者が考えイメージしてきた慢性痛というものを見事に、言葉にすることに成功した名著であると思う。とりわけデカルト以降、普及している心身二元論の限界を、構造構成主義という原理(哲学)で慢性痛をきれいに論理化して解釈可能にしており、素晴らしいところであると確信をもっていえる。本書の特筆すべきところは、生物・心理・社会モデルでしか説明しえなかった慢性痛を論理化したことだけでなく、さらにその論理をもとに治療の考え方にまで言及しており、慢性痛を診療する医療者にとって基軸となるべき理論書であるといえる。
臨床雑誌整形外科67巻13号(2016年12月号)より転載
評者●愛知医科大学学際的痛みセンター教授 牛田享宏