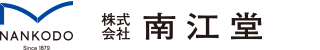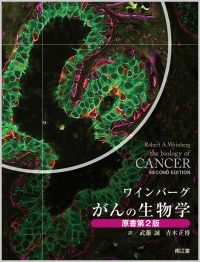ワインバーグ がんの生物学原書第2版
| 著 | : Robert A.Weinberg |
|---|---|
| 訳 | : 武藤誠/青木正博 |
| ISBN | : 978-4-524-26581-7 |
| 発行年月 | : 2017年6月 |
| 判型 | : A4変型 |
| ページ数 | : 960 |
在庫
定価15,400円(本体14,000円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

がん研究の第一人者として世界的に著名なロバートA.ワインバーグの名著「The Biology of Cancer」の改訂版。がんの生物学の歴史や分子生物学を駆使した最先端の基礎研究から臨床研究、治療について分かりやすく解説された本書の初版翻訳版は日本翻訳出版文化賞を受賞。今版でもストーリー性のある理解しやすい解説と多くの図・写真は健在。この間に解明されたこと、進展した治療法などの情報更新がなされ、さらに“がん”の正体に迫っている。
第1章 細胞および個体の生物学と遺伝学
1.1 メンデルは遺伝学の基本原則を確立した
1.2 メンデル遺伝学によって説明しやすくなったダーウィンの進化論
1.3 メンデル遺伝学は遺伝子,染色体両方の挙動を支配する
1.4 ほとんどの種類のがん細胞で染色体の変化が見られる
1.5 がんの原因となる突然変異は生殖細胞系列,体細胞のどちらにも起こりうる
1.6 DNAの塩基配列として具体化された遺伝子型はタンパクを介して表現型を創り出す
1.7 遺伝子の発現パターンも表現型を制御する
1.8 ヒストン修飾と転写因子が遺伝子の発現を調節する
1.9 遺伝子発現はさらなる機序に制御されて受け継がれる
1.10 通常とは異なるRNA分子もまた遺伝子の発現に影響を与える
1.11 多細胞動物は,非常に長い進化の期間を超えて保存されてきた構成要素から成り立っている
1.12 遺伝子クローニングの技術は,正常細胞および悪性化細胞の研究に革命をもたらした
第2章 がんの本性
2.1 腫瘍は正常組織から出てくる
2.2 腫瘍は,体中のいろいろな種類の細胞から出てくる
2.3 ある種の腫瘍は大まかな分類にあてはまらない
2.4 がんは段階的に発達・進展する
2.5 腫瘍は単クローン性の増殖体である
2.6 がん細胞は正常細胞と異なったエネルギー代謝を呈する
2.7 がんの発症率は人口集団間で著しく異なっている
2.8 がんの危険度は,生活習慣などの特定できる影響力で増加する
2.9 特定の化学物質によって,がんを引き起こすことができる
2.10 物理的な発がん性要因も,化学発がん物質も,ともに変異原性因子として作用する
2.11 変異原がヒトのがんの原因の一部かもしれない
2.12 概要と見通し
第3章 腫瘍ウイルス
3.1 ペイトン・ラウスはトリ肉腫ウイルスを発見した
3.2 ラウス肉腫ウイルスが,感染した培養細胞を形質転換することが発見された
3.3 形質転換を維持するにはRSVの持続的な存在が必要である
3.4 DNA分子を持つウイルスもがんを引き起こすことができる
3.5 腫瘍ウイルスは,腫瘍原性の獲得を含め,細胞の表現型に多くの変化を与える
3.6 腫瘍ウイルスのゲノムは,宿主細胞DNAの一部となることによってウイルスで形質転換した細胞中に消えずに残る
3.7 レトロウイルスゲノムは感染細胞の染色体に組み込まれる
3.8 RSVが持つsrc遺伝子の類似遺伝子が非感染細胞にも存在する
3.9 RSVは細胞性遺伝子を持ち去って利用し,細胞を形質転換する
3.10 脊椎動物のゲノムには原がん遺伝子の大きな集団が存在する
3.11 緩徐に形質転換させるレトロウイルスは,そのゲノムを原がん遺伝子の近傍に挿入することによってこれらの細胞性遺伝子を活性化する
3.12 一部のレトロウイルスはもともとがん遺伝子を持っている
3.13 概要と見通し
第4章 細胞性がん遺伝子
4.1 ヒトのがんは内在性レトロウイルスの活性化で誘発されるか
4.2 DNAのトランスフェクションが,非ウイルス性のがん遺伝子を検出する手段となる
4.3 ヒトの腫瘍細胞株から発見されたがん遺伝子は,形質転換能のあるレトロウイルスが持っているがん遺伝子と近縁関係にある
4.4 原がん遺伝子は,タンパクの発現や構造に影響する遺伝的変化によって活性化されうる
4.5 主題と変奏曲:mycがん遺伝子は,少なくともさらに3つの独立した機構で活性化できる
4.6 タンパク構造の一連の広範な変化もまた,がん遺伝子の活性化を引き起こす
4.7 概要と見通し
第5章 増殖因子,増殖因子受容体とがん
5.1 正常な多細胞生物の細胞はお互いにその生死を制御している
5.2 Srcタンパクはチロシン・キナーゼとして働く
5.3 EGF受容体はチロシン・キナーゼとして機能する
5.4 変異を受けた増殖因子受容体は腫瘍化タンパクとして機能しうる
5.5 増殖因子の遺伝子は,がん遺伝子になりうる:sisの場合
5.6 交叉リン酸化が受容体型チロシン・キナーゼの作用の基礎となっている
5.7 哺乳動物細胞は,また別の受容体を用いて周辺環境と情報交換することができる
5.8 核内受容体は低分子量脂溶性リガンドの存在を感知する
5.9 インテグリン受容体は細胞と細胞外基質の会合を感知する
5.10 下流のシグナル伝達連鎖の一部と思われるRasタンパクはGタンパクとして機能する
5.11 概要と見通し
第6章 細胞質でのシグナル伝達回路が,がんの形質の多くを決定している
6.1 シグナル伝達経路は,細胞表面から核内へ到達する
6.2 Rasタンパクは複雑なシグナル伝達連鎖の中間に位置している
6.3 チロシンのリン酸化が多くの細胞質内シグナル伝達タンパクの位置,ひいては作用を制御する
6.4 増殖因子受容体がどのようにRasを活性化し,シグナル伝達の特異性を獲得するかをSH2とSH3ドメインが説明してくれる
6.5 Rasで調節されるシグナル伝達経路:タンパク・キナーゼの1つの連鎖が,Rasの下流の3つの重要なシグナル伝達経路の1つを形成している
6.6 Rasで調節されるシグナル伝達経路:下流の第二の経路はイノシトール脂質とAkt/PKBキナーゼを制御する
6.7 Rasで調節されるシグナル伝達経路:第三の下流経路はRasの遠縁の分子Ralを介して作用する
6.8 Jak-STATシグナル経路は,細胞膜から直接核へのシグナル伝播を可能にする
6.9 細胞接着の諸受容体が発信するシグナルは,増殖因子受容体から放出されるシグナルと合流する
6.10 Wnt-βカテニン・シグナル経路は細胞増殖に寄与する
6.11 Gタンパク共役型受容体もまた正常およびがん細胞の増殖を促進する
6.12 さらに4つの『二重アドレス』シグナル伝達経路が,正常細胞とがん細胞の増殖にさまざまな様式で寄与する
6.13 良く設計されたシグナル伝達回路は負と正のフィードバック制御を必要とする
6.14 概要と見通し
第7章 がん抑制遺伝子
7.1 細胞融合実験は,がんの表現型が劣性であることを示唆する
7.2 がん細胞の表現型が示す劣性の性質は遺伝学的な説明を必要とする
7.3 がん抑制遺伝子の遺伝学上の謎に対する解答は,網膜芽腫によってもたらされた
7.4 初期のがん細胞は,がん抑制遺伝子の野生型コピーを取り除く手段を創り出す
7.5 Rb遺伝子は腫瘍においてしばしばLOHを示す
7.6 ヘテロ接合性の消失を用いてがん抑制遺伝子を見つけることができる
7.7 家族性のがんの多くは変異型がん抑制遺伝子を受け継ぐことで説明される
7.8 プロモーターのメチル化はがん抑制遺伝子不活化の重要な機序である
7.9 がん抑制遺伝子群とそのタンパクはさまざまな方法で機能する
7.10 NF1タンパクはRasシグナル伝達を負に制御する因子として作用する
7.11 Apcは細胞が大腸陰窩から出て行くのを促進する
7.12 フォン・ヒッペル-リンドウ病:pVHLは低酸素に対する応答を調節する
7.13 概要と見通し
第8章 レチノブラストーマ・タンパク(pRb)と細胞周期時計の制御
8.1 細胞の成長と分裂は一連の複雑な調節因子により調整されている
8.2 細胞はG1期のある特定の期間に増殖か静止かについての決断をする
8.3 サイクリンとサイクリン依存性キナーゼが細胞周期時計の中心的要素をなしている
8.4 サイクリン-CDK複合体は,CDK阻害タンパクによっても調節される
8.5 ウイルス性腫瘍化タンパクが,pRbがどのように細胞周期の進行を阻止するかを明らかにしている
8.6 細胞周期時計によりpRbはR点ゲートの番兵の役を課されている
8.7 pRbによる増殖対静止の決断の実務を転写因子E2Fが可能にする
8.8 多様な増殖促進シグナル伝達経路がpRbのリン酸化状態を制御する
8.9 Mycタンパクは増殖するか,分化するかの決定を統治する
8.10 TGF-βはpRbのリン酸化を防ぎ,それによって細胞周期の進行を阻止する
8.11 pRbの機能と分化の制御は密接に関連している
8.12 全てではないにせよ,ヒトのほとんどのがんでpRbの機能の制御が撹乱されている
8.13 概要と見通し
第9章 p53とアポトーシス:護衛隊長,兼死刑執行人
9.1 パポーバウイルスがp53の発見につながった
9.2 p53はがん抑制遺伝子であることが発見される
9.3 変異型のp53は正常なp53の機能を妨害する
9.4 p53タンパク分子は,通常寿命が短い
9.5 さまざまなシグナルがp53を誘導する
9.6 DNA損傷や制御を外れた増殖シグナルはp53の安定化を引き起こす
9.7 Mdm2は自身の創造者を破壊する
9.8 ARFとp53を介したアポトーシスは,細胞内シグナル伝達を監視することによってがんの発生を防ぐ
9.9 p53は,DNA損傷に応答して細胞周期の進行を止める転写因子として機能し,修復過程の促進を試みる
9.10 p53は,しばしばアポトーシスによる死のプログラムへと案内する
9.11 初期のがん細胞は,腫瘍が進行していく多くの段階においてp53の不活化による恩恵にあずかる
9.12 p53経路に影響を与える変異型アレルを受け継ぐと,さまざまな腫瘍が発生しやすくなる
9.13 アポトーシスは複雑なプログラムで,しばしばミトコンドリアに依存する
9.14 内在性および外因性アポトーシス・プログラムの両方が細胞死を引き起こせる
9.15 がん細胞は多くの方法を編み出してアポトーシス機構の一部または全部を不活化する
9.16 壊死とオートファジー:腫瘍進展の道における2つの更なる分岐点
9.17 概要と見通し
第10章 永遠の生命:細胞の不死化と腫瘍形成
10.1 正常な細胞集団はその世代数を記録し,それらが由来した初期胚細胞とは一線を画す
10.2 がん細胞が腫瘍を形成するためには不死化する必要がある
10.3 細胞の生理的ストレスが複製を制御する
10.4 培養細胞の増殖は,染色体のテロメアによっても制御される
10.5 テロメアは容易には複製されない複雑な分子構造をとっている
10.6 初期のがん細胞はテロメラーゼを発現することで危機を逃れることができる
10.7 テロメラーゼはヒトがん細胞の増殖に重要な役を果たす
10.8 一部の不死化細胞はテロメラーゼなしにテロメアを維持する
10.9 テロメアは実験用マウスとヒトの細胞では異なった役割をする
10.10 テロメラーゼ陰性マウスは,がん感受性が減少も増加もしている
10.11 テロメラーゼ陰性マウスでがんの病因となっている機序は,ヒト腫瘍の発達にも作動しているかもしれない
10.12 概要と見通し
第11章 多段階腫瘍形成
11.1 ほとんどのヒトのがんは,何十年もの時間をかけて発生する
11.2 組織病理学が多段階腫瘍形成の証拠をもたらす
11.3 細胞は腫瘍進展が進行するにつれて遺伝子の変化とエピジェネティックな変化を蓄積する
11.4 多段階腫瘍進展は,家族性腺腫症と広域発がんを説明しやすくする
11.5 がんの発達はダーウィンの進化論の法則に従うように思われる
11.6 腫瘍幹細胞が,クローン継承と腫瘍進展のダーウィン進化論的モデルをさらに複雑にしている
11.7 クローンの継承が直線的に進むという考え方は,がんの現実を単純化しすぎている:腫瘍内の不均質性
11.8 腫瘍発生のダーウィン進化論的モデルを実験的に証明することは難しい
11.9 正常細胞はたった1個の変異遺伝子による形質転換に対して抵抗性であることが,複数の証拠から明らかになった
11.10 形質転換には通常2個かそれ以上の変異型遺伝子の協同作業を必要とする
11.11 トランスジェニック・マウスは,がん遺伝子の協同作用と多段階の細胞形質転換のモデルを提供する
11.12 ヒトの細胞は,不死化や形質転換に対して高い抵抗性を持つよう構築されている
11.13 細胞の増殖を促進するものを含めた非変異原性物質が,腫瘍形成に重要な寄与をする
11.14 毒性を持った物質および分裂促進物質がヒトの腫瘍促進物質として作用しうる
11.15 マウスおよびヒトにおいて,慢性炎症が往々にして腫瘍進展を促進する
11.16 炎症依存性の腫瘍促進は,決まったシグナル伝達経路を介して作用する
11.17 ヒトの多くの組織において,腫瘍促進が腫瘍進展の速度を決定する重要な要素となっている可能性が高い
11.18 概要と見通し
第12章 ゲノムの完全性の維持とがんの発達
12.1 組織は突然変異の蓄積が進行するのを極力減らすようにできている
12.2 幹細胞が,がんに至る変異誘導の標的であることもあり,そうでないこともある
12.3 アポトーシスや薬物ポンプとDNA複製メカニズムは,変異した幹細胞が組織に蓄積するのを最小限に抑える方法を与えている
12.4 細胞ゲノムはDNA複製中に起きる間違い(エラー)に脅かされている
12.5 細胞のゲノムは内因性の生化学的な諸過程によって常に攻撃されている
12.6 細胞のゲノムは,外因性の変異原やそれらの代謝物から,しばしば攻撃を受ける
12.7 細胞はDNA分子が変異原物質によって攻撃されるのを守る,多様な防御を配備している
12.8 修復酵素群が諸変異群によって変化したDNAを修繕する
12.9 ヌクレオチド除去修復,塩基除去修復,それにミスマッチ修復における遺伝的欠損は特定のがん高感受性症候群を起こす
12.10 まだよく解明されていない,その他の多様なDNA修復機構の欠損によってもがんの感受性が増加している
12.11 がん細胞の核型は染色体の構造異常のために変化している
12.12 がん細胞の核型はしばしばその染色体の数に変化を示す
12.13 概要と見通し
第13章 対話が独り言に取って代わる:異種細胞間相互作用,そして血管新生の生物学
13.1 正常および腫瘍性の上皮組織は相互依存的な細胞種から形成される
13.2 がん細胞株を形成する細胞は異種細胞間相互作用なしに出現し,ヒトの腫瘍内の細胞の挙動からは逸脱している
13.3 腫瘍は治癒しない創傷組織に似ている
13.4 間質細胞が腫瘍形成に積極的に寄与していることは実験によって直接的に示されている
13.5 マクロファージと骨髄細胞は,腫瘍随伴間質の活性化において重要な役割を果たす
13.6 内皮細胞とそれらが形成する血管によって,腫瘍は循環への十分なアクセスを確保している
13.7 腫瘍の拡大には血管新生スイッチを始動させることが不可欠である
13.8 血管新生スイッチは高度に複雑化した過程を開始する
13.9 血管新生は,通常は生理的な阻害物質によって抑制されている
13.10 血管新生阻害治療法は,がんを治療にも利用できる
13.11 概要と見通し
第14章 外へ:浸潤と転移
14.1 原発腫瘍から転移可能な部位へのがん細胞の移動は,一連の複雑な生物学的な段階によっている
14.2 浸潤.転移の連鎖の中で転移増殖が最も複雑で困難な段階を成している
14.3 上皮間葉移行と,それに伴うEカドへリン発現の消失が,がん細胞を浸潤性にする
14.4 上皮間葉移行(EMT)はしばしば,周囲のシグナルによって誘導される
14.5 間質の細胞が浸潤性の誘起に貢献する
14.6 EMTは胚発生の重要な諸段階を調和調整する転写因子群によりプログラムされている
14.7 EMTを誘導する転写因子群は幹細胞状態への導入も可能にする
14.8 EMTを誘導する転写因子群は悪性進展の推進を助ける
14.9 細胞外のタンパク分解酵素が浸潤性に重要な役割を果たす
14.10 Ras様の低分子量GTPase群が,細胞の接着,形態,それに運動性などの諸過程を制御している
14.11 転移している細胞はリンパ管を使って原発腫瘍から拡散することがある
14.12 播種したがん細胞がどの臓器に転移巣を形成するかは多様な因子で支配される
14.13 骨への転移には骨芽細胞と破骨細胞を欺くことが必要である
14.14 転移抑制遺伝子群は転移の表現型を統制するのに寄与する
14.15 潜在性微小転移が,がん患者の長期生存を脅かしている
14.16 概要と見通し
第15章 群衆整理:腫瘍免疫学と免疫療法
15.1 免疫系は生体組織内の外来の侵入者や異常細胞を破壊する
15.2 適応免疫応答は抗体産生を引き起こす
15.3 別のタイプの適応免疫応答から細胞傷害性細胞が形成される
15.4 自然免疫応答は,前もっての感作を必要としない
15.5 自己を非自己と区別する必要から免疫寛容が生じる
15.6 制御性T細胞は適応免疫応答の主要な構成要素を抑制することができる
15.7 免疫監視機構理論の誕生と挫折
15.8 遺伝子改変マウスを用いることにより,免疫監視理論が復活する
15.9 ヒトの免疫系は,ヒトのさまざまなタイプのがんを防ぐのに決定的な役割を演じている
15.10 正常組織と腫瘍組織の微妙な違いのおかげで免疫系はそれらを識別できる
15.11 腫瘍移植抗原は,しばしば強力な免疫応答を引き起こす
15.12 腫瘍関連移植抗原は,抗腫瘍免疫も引き起こすかもしれない
15.13 がん細胞は,腫瘍抗原の細胞表面への提示を抑制することによって,免疫による検出を逃れることができる
15.14 がん細胞は,NK細胞やマクロファージによる破壊から自らを保護している
15.15 腫瘍細胞が免疫細胞に対して反撃を開始する
15.16 がん細胞は,免疫系が用いるさまざまな様式の殺傷作用に対して本質的に耐性となる
15.17 がん細胞は,他のリンパ球による攻撃をかわすために制御性T細胞を引き寄せる
15.18 モノクローナル抗体による受動免疫を用いて乳がん細胞を殺傷することができる
15.19 抗体による受動免疫を用いてB細胞腫瘍を治療することができる
15.20 異質なリンパ球を移植することが特定の造血器腫瘍の治癒につながる
15.21 患者の免疫系を動員して腫瘍を攻撃することができる
15.22 概要と見通し
第16章 がんの合理的な治療
16.1 効果的な治療の開発と臨床応用は,病気の正確な診断に依存する
16.2 外科手術,放射線療法,それに化学療法が現在のがん治療が依拠する主要な柱となっている
16.3 がん細胞を殺すのに分化,アポトーシス,それに細胞周期のチェックポイントを利用できる
16.4 がん細胞内の諸タンパクを機能に基づいて考察すると,それらのほんの一部だけしか魅力的な創薬標的にはなり得ない
16.5 タンパクの生化学的性質もまた,がんの進行に介入するのに魅力的な標的かどうかを決定する
16.6 創薬化学者は広範な一団の薬物可能性物質を作り,それらの生化学的性質を探索することができる
16.7 新薬候補化合物の個体レベルでの有用性を測定するためには,最初に細胞モデルで試験しなければならない
16.8 実験動物での薬物作用の研究は,前臨床試験の必須な要素である
16.9 見込みのある候補薬は,ヒトの第I相試験において厳格な臨床試験を行わねばならない
16.10 第II相と第III相の試験が,薬効の信頼できる臨床的な指標を提供する
16.11 腫瘍は当初効能のあった治療法に対して,しばしば耐性を生ずる
16.12 グリーベックの開発は,他の多くの(分子)標的化合物の開発に範を示した
16.13 EGF受容体拮抗薬は,広範なタイプの腫瘍の治療に有用かもしれない
16.14 プロテアソー厶阻害薬が予期しなかった治療効果を生じる
16.15 ヒツジの催奇形物質の1つが強力な抗がん薬として有用になるかもしれない
16.16 細胞生理の主要調節器であるmTORは,抗がん療法の魅力的な標的の1つを代表している
16.17 B-Rafの発見がメラノーマ問題に食い込んだ
16.18 概要と見通し:今後の挑戦と可能性
訳者より日本語版第二版の読者へ
原著初版と比較すればお分かりになると思うが、第二版では全体の構成や枠組みを殆ど変更せずに、内容の最新化と充実を図ることに意が尽くされており、後の方の章ほど大幅な改訂(中身の入れ替え)や追加が多くなっている。前の方の章では大きな変更は少ないが、注意深く読んでいただくと、細部に至る書き直しや語句の入れ替え、図やサイドバーの入れ替えや追加が至る所に認められ、第一版からSupplementarySidebarに移動されたものも多い。実に念入りな推敲が施されており、手の入らないページは存在しない。
このような改訂に伴い、原著自体が初版に比べ内容が増え、約80ページ増えているだけでなく、本文のフォントサイズを小さくしてページ当りの語数も増えている。従って、本文の図表やサイドバーなどのレイアウトが合うようにするために、日本語版のフォントサイズも少し小さくせざるを得なかった。このような状況でも読み易い文面にするため、少し濃めの書体に変更した。
初版では費用の関係で原著に付属していたCD-ROMを省略したが、一部の読者から付けて欲しいとの要望があった。原著第二版ではこれらの補助情報がDVD-ROMとして付属していると同時に、出版社Garlandのウェブサイトでもアクセスするように変更になっているので、本書第二版の日本語版では初版同様DVD-ROMは付録にしていないが、Garland社の英語サイトを活用していただきたい。
この度、英語原著の第二版を日本語版として訳出するにあたり、上記のフォント以外にも、以下の諸点に変更を加えて改善に努めた。
日本語の語句や専門用語について全書で統一する努力をすると同時に、原著の意図が正確に再現されるよう工夫を重ねた。但し、漢字かな交じり文の日本語文脈における読み易さを最優先したので、かな表記をするか、漢字を用いるかについては、教科書などの表記に従ったところとそうでないところがある。
また、“phosphatase”、“phosphothreonine”などの語句における“pho”のカタカナ表記については、「ホスファターゼ」、「ホスホスレオニン」などのように「ホ」とすることが教科書も含めて通例となっているため、本書初版でもそのように表記した。しかしながら、これは“fork”を「ホーク」と表記するようなもので本来の音とかけ離れているため、第二版では思い切って「フォスファターゼ」、「フォスフォスレオニン」などのように「フォ」に統一した。なお、“phosphatase”を「フォスファターゼ」とするのはドイツ語読みであり、本来なら「フォスファテイス」としたいところではあるが、全ての酵素の語尾を変更すると混乱を招く可能性があるため、そこまでの変更は見送った。
初版では本文中に英語の重要語句をそのまま挿入していたが、第二版では脇組に移動した。ただ、例外としてin vivo、in vitroなどの日本語になりつつあるラテン語源の重要単語は本文中に残した。
さらに、細かいことだが、日本語で数値や時間の幅を示すのにチルダ「.」を使用するが、英語表記ではこれは数値の頭に使い、「およそ、約」を表すのに使う。混同を避けるため、チルダは全て「およそ、約」と、かな表記した。逆に、英語の数値や時間の幅を示す“-”(n-dash)は日本語ではチルダで表現することが多いが、本書では全て「から」とした。これを機会に、読者諸氏が英語で論文や手紙を書く際にもこれらを混同しないよう習慣づけてもらえれば幸いである。
最後に、第二版の翻訳に際して初版からの変更・追加部分を精査してくれた、愛知県がんセンター研究所分子病態学部の玉置広美氏と、出版に協力してくれた、南江堂、特に星野仙、菊池安里、飯島純子の諸氏に感謝する。なお、ワインバーグ博士は原著第三版の準備を進めておられると聞いており、今後の改善のためにも、読者から訳者にコメントがあれば遠慮なくお知らせ頂きたい。
2017年3月
武藤誠(Makoto Mark Taketo,M.D.,Ph.D.)
青木博(Masahiro Aoki,M.D.,Ph.D.)