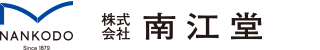痛みの考えかた
しくみ・何を・どう効かす
| 著 | : 丸山一男 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26397-4 |
| 発行年月 | : 2014年4月 |
| 判型 | : A5 |
| ページ数 | : 366 |
在庫
定価3,520円(本体3,200円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

もっとも身近にもかかわらず、あまり考えずに対処してしまいがちな「痛み」。痛みとは何か、そのメカニズムを把握することにより、臓器や筋肉の痛み、関連痛などの幅広い痛みの種類を理解し、さらには痛みを止めるしくみや耐性・プラセボまでを自然と理解できる。親しみやすい解説と豊富なイラストで「痛み」を楽しくマスターできる、医師、薬剤師、看護師、理学療法士など、すべての医療従事者にお薦めの一冊。
1章 痛みは測れるか−プロローグ
A 生命と痛みの目的
B 痛みの発生の仕組み
C 痛みの伝導と伝達
D 痛みを測る
2章 弁慶の泣きどころ−神経線維の役割分担
A 痛みを伝える神経線維
B 神経線維の分類
C 侵害受容器
3章 ヨーイ、ドン−活動電位の発生
A 膜電位
B 活動電位の発生:電位依存性Na+チャネル(NaV)が開く
4章 痛みのリレーとバトンタッチ−中継点は脊髄後角と視床です
A 痛み刺激はどこへ行く?
B ゴールはどこ?体性感覚野と大脳辺縁系
C 脊髄後角からの路
5章 痛みのスープの味は?−発痛物質:炎症の問題
A 炎症があると痛い?
B 発痛物質の正体
C 炎症と発痛物質
D 発痛物質の働き:ブラジキニンとプロスタグランジンE
6章 痛みのセンサー−侵害受容器と受容体
A 侵害受容器
B 自由神経終末のありか
C 繋ぎの電位(起動電位)と活動電位:トランスデューサーチャネルとNaV
D 治療についての考察
7章 味の素とアンパン−グルタミン酸とAMPA受容体
A 1次ニューロンから2次ニューロンへの伝達
B シナプスでの出来事
C 興奮性シナプスと抑制性シナプス
D 鎮痛との関係
8章 心頭滅却すれば火もまた涼し−上からシナプス伝達を抑える:下行性抑制系
A 自分で痛みを抑える仕組み
B 下行性抑制系:内因性の鎮痛物質の放出
C ノルアドレナリン、セロトニンの作用
D まとめ:治療に関連して
9章 開けゴマ−痛みの伝達門の開閉:ゲートコントロール
A 痛みの伝導路
B ゲートコントロール理論:門番は誰?
C 何もしなくても痛い
D 簡単なまとめ
E 治療方法と門との関係
10章 いつでも、どこでも、まずはNSAIDs−COXの問題
A アラキドン酸とCOXの大きさ比べ
B NSAIDsの分類
C 用量と作用の関係
D アセトアミノフェン:NSAIDsではありません
E まとめ:投与量の問題
11章 ナトリウムチャネルをブロックせよ−局所麻酔薬です
A 局所麻酔薬の作用
B 局所麻酔薬の使い方
12章 オピオイド−身体の中でも作られています
A オピオイドとは
B 内因性モルヒネ様物質
C オピオイド受容体
D オピオイドと依存
13章 カルシウムチャネルの問題−高血圧だけではありません
A Ca2+チャネルの異常と病気
B Ca2+チャネルの種類
C Ca2+チャネルを抑える:α2δリガンド
14章 筋肉の痛みの会話−隣の筋肉痛とAγ運動ニューロン
A 筋の緊張
B 筋の痛み
15章 トリガーポイントを探せ−押さえて痛い:関連痛
A 痛みの局在
B 関連痛とは
C トリガーポイント
16章 普通でない痛みですか?−痛くないことを痛く:中枢性感作
A 痛みの閾値の低下
B 末梢性感作
C 中枢性感作:広作動域(WDR)ニューロンの役割
D 神経障害性疼痛
E NMDA 受容体
17章 痛みのメモリー−覚えたくはありませんが……
A 痛みはどこで覚えるか
B 脊髄で痛みを記憶する
C 痛みを忘れるために
18章 交感神経と痛みの関係は?−内臓の痛み、ケガの後の痛み
A 交感神経系が伝える痛み:内臓痛の問題
B 交感神経の源(大脳辺縁系-視床下部)と痛みの問題
C 交感神経遠心性線維による痛み:ケガの後の痛み
19章 プラセボ効果は気休めか?−いいえ、そうではありません
A ナロキソンの作用
B プラセボ効果の仕組み
C プラセボ効果の実際
20章 食わずぎらいのあなたに−耐性と身体依存
A オピオイドの傾向と対策
B 快感をめぐって:量や回数で快感が戻れば耽溺のもと
C 耐性の仕組み:副作用に対する耐性は歓迎されます
D 退薬症状の仕組み:徐々に減量すれば予防できます
参考文献
索引
痛みは、電気として神経を伝わる。原因となる病気やケガを治しつつ、薬、注射、理学療法、運動療法などを駆使して痛みを止める。「痛みを止めるための治療」は、間接的・直接的に痛みのニューロンでの電気活動を抑制しているのだが、イメージが湧きにくい。神経伝達の講義は、生理学の分野で神経生理や電気生理という題目で講義されてきた(大変格調高い内容であったと思う)。しかしながら、何が、どこに、どのように効くのか、モヤモヤしている医療従事者も多いのではなかろうか。そこで、絵と図を用いて読み物風にして、痛みの仕組みと薬や処置の作用点について説明してみた。
医師は患者さんに応じて薬や処置を組み合わせる。一方、看護師・薬剤師・理学療法士といったメディカルスタッフは、処方こそしないが、患者さんと深く関わってケアしているチームの一員である。薬や処置がどこに効いているか分かり、患者さんの痛みが止まれば、納得のチーム医療となるであろう。
巻頭の目次マップでは、痛い部分から脳に至る「痛みの道」を示した。痛みの仕組みの全体像を捉えるには、全体の中で個々の役割を考えるのがよい。点と点を線に繋げたいと思うのである。最初から読み進めて、何回か行ったり来たりしていただければありがたい(関連する章・頁・図番号を入れた)。ややこしそうな内容は、飛ばしても後で分かるよう、表現を変えて繰り返し述べた。図を追って、流れをつかみとってほしい。神経伝達物質・受容体・活動電位・イオンチャネルなどはムズカシい……という雰囲気を吹き飛ばしたいのである。繋がればスッキリし、薬の効く場所が分かる。それから、もう1つ−痛みを我慢させてはいけない、覚えてしまうから−の仕組みを説明した。生理学にごぶさただった先生方や研修医、医学生・薬剤師・看護師・理学療法士・鍼灸師などの皆さまのお役に立てば幸いである。
筆者はこれまで、南江堂より「周術期輸液の考えかた」、「人工呼吸の考えかた」を上梓し、診療の基本について考えてきた。痛みの診療は、各科から集中治療、緩和ケアチームまでを横断している。
2014年4月
丸山一男
送られてきた本書を手にしたとき、「ここまできたか」という感慨を覚えた。一つは、痛みについての生理や薬理について知りたいという医療従事者の関心の高まりが存在するという事実である。もう一つは、理解してもらうための著者の工夫の仕方である。その工夫の仕方は、たとえていえば「生活」を「暮らし」と、「世界」を「世の中」とするような、わかりやすい表現への置き換えである。
家庭環境のせいで、幼いころから評者は「痛み」に関心をもっていた。医師になり、整形外科医として腰痛を自分のlife workに掲げて仕事をした。当時、現場での実情と研究成果との間には相当な乖離があった。たとえば、腰痛の診断は単純X線像で行い、治療はその効果発現機序も治療成績も不透明な状態での実施であった。
腰痛の国際学会(International Society for the Study of the Lumbar Spine:ISSLS)で、“Pain and the Nerve Roots”というシンポジウムで、痛みがはじめて取り上げられたのが1982年である。当時、演題のほとんどは画像診断、生体力学、そして手術であった。目にみえない痛みを、画像を代表とした形態でとらえようとしていた時代である。腰痛の診断・治療は壁に突き当たっていた。
文化の視点から痛みの歴史をたどってみると、示唆的なエピソードが垣間みえてくる。
医療の対象としての痛みは当初、切断や抜歯に代表される「目にみえる疼痛」であった。1846年の有名なエーテルを使った最初の外科手術の成功により、疼痛の治療は完全に解決したかにみえた。しかしその後、医療は「目にみえない痛み」に直面した。
「目にみえない痛み」の多くは慢性である。慢性の痛みは、急性の痛みや重篤な疾患と比べてあまり深刻にはみえない。しかし最新の研究は、慢性の痛みが免疫機能や生活習慣病の発症に関与していることを明らかにした。また、「動かないこと」が寿命、癌、認知症など、人間の健康の維持に深く関与していることも明らかになった。さらに最新の科学は、従来われわれが認識していた以上に早期から痛みに心理・社会的因子が深く関与していることも明らかにした。「健全な精神は健全な肉体に宿る」ではなくて、「健全な肉体は健全な精神に宿る」のである。
17世紀、デカルトによる痛みのロープ牽引モデルは、19世紀のベルやマジャンディーなどによる疼痛の器質的モデルの発展につながった。
ただ、痛みに関する科学の急速な進展により見失ってしまったこともある。それは、15世紀、フランチェスカの「キリストのむち打ち」の絵画に表現されている、痛みが有している社会的・心理学的意味である。この時代には、痛みは電気生理学的現象というとらえ方ではなくて、苦悩や苦痛を伴う情緒的要素が含まれていることを認識していた。
20世紀初頭、ルリッシュは、医療現場で医療従事者がみている痛みは実験室で研究されているようなものではなく、「生きている痛み」であることを指摘した。そして、痛みは「大脳の現象」であることを提示した。これにより、患者のみえない痛みは心と体が複雑に絡み合っている現象であることが広く認識されるようになった。医療というartと医学というscienceがようやく合流したのである。
近年の神経科学の発達は、痛みという現象を細胞や分子レベルで明らかにしつつある。それだけに、第一線の診療現場で痛みの治療に従事している人間にとっては、痛みの理解はかえってむずかしくなったことも事実である。
本書は、このような痛みのとらえ方の時代的変遷を経ての登場という時代的意義を有している。疼痛の生理学的基礎を完全に理解・把握して、研究と臨床の最前線に立っている著者がどのようにしたら読者にわかってもらえるかを真剣に工夫した結果、本書が生まれたのである。
本書は、疼痛に関心のある医療従事者や医学を学ぶ学生には入門書として、疼痛の専門家には自分の知識や認識の再整理のために、一読すべき価値がある。しかも、定価は高くない。
臨床雑誌整形外科65巻11号(2014年10月号)より転載
評者●福島県立医科大学理事長兼学長 菊地臣一