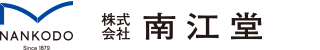苦い経験から学ぶ!緩和医療ピットフォールファイル
| 編集 | : 森田達也/濱口恵子 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-25979-3 |
| 発行年月 | : 2017年6月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 238 |
在庫
定価3,850円(本体3,500円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

緩和医療における失敗事例を分析することで、臨床に役立つ知識と技能を磨くことができるケースファイル集。経験豊富な医師や看護師をはじめとした緩和ケアのエキスパート陣が、自身の苦い経験に基づく教訓をレクチャー。多岐にわたる失敗事例を読み進めるごとに、緩和ケアの思いがけない「落とし穴」に気づくコツと視点を身につけることができる。
第1章 痛み・その他の症状のマネジメントにまつわる失敗
A 見逃していた!この病態
Case1.下肢の痺れにトリプタノールR.ふらつくと思っていたら
Case2.胃がんでの下肢筋力低下.脊髄圧迫がないけど原因は?
Case3.食欲も活気もないのは,落ち込んでいるため?オピオイドのため?
Case4.吐き気と思っていたら
Case5.肩こりと頭痛の原因は
Case6.せん妄が改善しない理由は
Case7.便秘がよくならない理由は
Case8.全身状態がどんどん悪くなっていく理由は
Case9.転倒リスクが高くても「自分でトイレに行きたい」
B 薬剤による思わぬ落とし穴
Case10.痛みの緩和のために廊下をウロウロしていると思っていたら
Case11.パニック障害による過呼吸症候群と思っていたら
Case12.「顔が洗えない」のは体力低下のせい?
Case13.高熱,赤色尿,意識障害は感染症のせいと思っていたら
Case14.利尿薬で胸痛発作!?
Case15.分泌抑制薬で喘鳴は軽減したが
Case16.ミオクローヌス治療でパーキンソニズムまで改善して
Case17.鎮静開始し,朝に薬剤を止めたら
C 痛みのマネジメントにまつわる失敗
Case18.持続痛と思っていたら
Case19.アブストラルR開始量の盲点
Case20.オピオイド増量で痛みが増強?
Case21.抗がん薬治療中に呼吸抑制が発生
Case22.抗がん治療後のオピオイドの退薬症状
Case23.放射線治療中に痛みが増強
第2章 患者・家族,医療従事者間でのコミュニケーションにまつわる失敗
A 人によって受け取り方の異なる言葉
Case24.「状態が悪化しています」
Case25.「何をしてもいいですよ」105
Case26.「様子を見ましょう」
B 「ものには理由がある」〜患者・家族の真意(ニーズ)を捉え損ねた失敗〜
Case27.「経鼻胃管を抜きたい!」と繰り返した患者
Case28.「あなたに私のつらさは分からない」
Case29.「抗がん治療を続けたい」その言葉を言わせたのは私たち?
Case30.「痛みをゼロにしたいわけではない」
Case31.「つらい治療はしたくない」
Case32.「抗がん薬は止めたい」
Case33.「本人が不安を感じています」は本当?
Case34.「こんなはずじゃなかったのに」
C あと少し必要だった配慮
Case35.「あなただけに話したつもりだったのに」
Case36.せん妄を疑い,簡易テストを行ったら
Case37.沈黙がうまくできなくて
Case38.「奇跡」を願ってはダメですか?
D 「何もしてくれない」という家族の思い
Case39.「口から食べさせたい」
Case40.「モニター装着で異常の早期発見をしてほしい!」
Case41.「苦しそうなのに,最期に何もしてくれなかった」
Case42.心肺停止後に心臓マッサージを始めた家族
E 患者と家族の間で
Case43.「患者の傍にいる家族の言葉を信じて!」
Case44.鎮静−患者と家族の希望,どちらを優先?
Case45.「転院したので早く亡くなってしまった」と憤る家族
Case46.「もっと痛みのとれる治療はないの?」
F 予後,ACPにまつわる失敗〜いつなのか,今なのか〜
Case47.「予後を訊きたい」と言われたが
Case48.緩和ケア外来の話をしたら
Case49.外来にて緩和ケア病棟を紹介したら
Case50.本人に予後の説明ができないまま
G 「間に合う/間に合わない」〜見極めの難しい看取りのタイミング〜
Case51.まさか今日亡くなるとは
Case52.付き添わないと看取りに間に合わない可能性があるなんて
Case53.最期が近いと家族に伝えたものの
H 異なる立場間でのコミュニケーション
Case54.複数の病院で治療を受ける患者,誰が主治医?
Case55.在宅医や訪問看護とのすり合わせ:依頼だけでは連携にならない
索引
序文
本書は、緩和ケア領域だと初めてとなる「失敗事例」を中心としたケースブックである。緩和ケアの書物は、最近やっと個性あるものが増えてきたが、ちょっとお堅い感じの教科書か、どこかで見たことのある表のついているマニュアル、それと「こんなにうまくいくかなあ…」と首を傾げたくなるうまくいった事例が山盛りのものが多い。本書では、うまくいかなかったとき、失敗したと思ったとき、そんなケースから臨床家が学ぶことを第一に考えた。
これまでにこのような本がなかった理由として、緩和ケアにはこれといった正解がないことが多いことが挙げられる。「入院して検査したら○○だと判明した!」「大丈夫と思って救急でその日に帰したら、救急車で意識不明になって戻ってきた!」のように、正解と間違いの差がはっきりしていないことが多い。緩和ケアを専門とする方たちも、「これ、私たぶん間違えました」と堂々と言いにくいところがある。
それでも、うまくいかなかったときから学ぶことは大きい。うまくいったときに学ぶことなど後でよくよく考えても思いつかないが、「これは一生に一度ないなあ…」という間違いこそ、多くのことを教えてくれる。編者がまだ若きホスピス医だったころ、死亡直前に「痙攣が止められない」状況に出会った。ジアゼパムにフェニトインをいやというほど打ったが、まったく痙攣が止まらなかった。とうとう痙攣が止まらないまま患者さんは亡くなってしまった。今なら(数年後なら)自信を持ってバルビツールを静注していたが、当時は「呼吸が止まってしまうかも」という懸念から打てなかった。
臨床家であれば医師でも看護師でも、このような「間違い」(というのか、この表現が難しいところだが)、まさか!の症例、もう少し慎重にしておけばよかった経験、ニアミスの事例、「こんなこと一生ないよなあ」というまれな事例を経験しているはずである。不思議なもので、ひとは「自分が経験しないと学ばない」。世の中には同じようなことが繰り返されているのだから、いい加減それから学べばいいと思うのだが、自分で経験して実感する以上のことはない。
とはいえ、苦い経験はできれば避けたいのは誰もが思うところだ。自分にとってもだが、患者さんにとっても。本書では、経験のある緩和ケアの臨床家に実に多様な「苦い経験」を持ち寄ってもらった。一つひとつの苦い経験が読者と共有されて、「苦い経験になったはずのできごとが誰にも意識されないまま防げた」現象が日本中に何回かでも生じれば、編者としてはとても嬉しい。
さいごに、苦い経験を活字にすることは勇気のいることであったに違いない。協力していただいた全国の執筆者に敬意と感謝を示したい。また、読者においては、プライバシーの点から、本書掲載の事例は学会の症例報告のように正確に記載しているわけではなく、伝えたいことが変わらない範囲で経過や結果を変更していることを了解いただきたい。
2017年5月
編者一同
緩和医療(緩和ケア)は、従来誤解されてきたような「ターミナルケア(終末期医療)に限ったもの」ではなく、必要に応じて原疾患に対する治療と「併せて」提供されるべきものである。平成28年末に改正された「がん対策基本法」においても、手術、放射線治療、化学療法と並ぶ「がん治療の柱」として併記され、少なくとも基本的緩和ケアについては全国あまねく実践が求められている。最近は一般市民にも緩和ケアは広く認識されており、患者が「緩和ケアを受けたい」と希望してきた際に、「私は(当院では)できない」では済まされない。実際、各地で「緩和ケア研修会」が開催されており、読者のなかにも参加された方が多いのではないかと思うが、どのような医療もそうであるように、知識を得た後には実践し、さらには他者へ指導すること(learn it,do it,teach it)で理解が深まるのが常である。ただ、まれな病態については実践を積むにも難しく、本書のように経験豊富な専門家が経験した「落とし穴」を臨場感あふれる形で学べることは大いに有用であろう。緩和ケアはとかく「対症療法」に終始するものと誤解されがちだが、その根底には総合的な内科的診断力が必要とされることがわかる好事例が多数あげられている(「何もしていない」とみえる場合でも、的確な予後予測に基づいてリスク&ベネフィットのバランスを考慮して「あえて行わない」という選択をしていることを十分ご理解いただきたい)。
さらに本書において注目すべきは、半分以上の頁数を「コミュニケーション」に関する事例に割いていることである。実際、緩和ケアチームや緩和ケア外来の形で他科の患者に関わると、問題が単なる「症状」ではなく、医療者との「コミュニケーション不足」に起因している事例が少なくない。本書では専門家が「よかれと思って」行った対応ですら「落とし穴」となった事例が数多くあげられているが、現実には、患者側に(身体症状以外に)どのような辛さ(とそれを乗り越えた先に叶えたい希望)があるのか、そもそも念頭にない主治医が非常に多い印象である。優れたコミュニケーション能力は治療の成否をも左右する重要な「医療技術」であり、患者・家族と医療者が課題を共有して取り組めば、「心身ともに穏やかな療養」の達成も容易になる(これは緩和ケアに限ったことではない)。「強くなければ生きていけない、優しくなければ生きていく資格がない(レイモンド・チャンドラー)」は、小説のなかだけでなく医療現場においてもスマートに実践していただけることを強く願う。
臨床雑誌内科121巻4号(2018年4月増大号)より転載
評者●東北大学大学院医学系研究科緩和医療学分野教授 井上彰