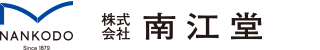外科学の原典への招待
| 編集主幹 | : 國土典宏 |
|---|---|
| 編集 | : 臨床雑誌『外科』編集委員会 |
| ISBN | : 978-4-524-25799-7 |
| 発行年月 | : 2015年4月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 262 |
在庫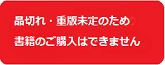
定価5,500円(本体5,000円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

臨床雑誌『外科』の好評連載「外科学の古典を読む」を書籍化。よく知られる手術や治療、疾患概念の多くは、高名な医学者の1〜2篇の論文に基づいており、その後の関連領域の論文にも必ず引用されているが、そのオリジナル論文(原典)を読む機会はほとんどない。著者の人物紹介や論文の意義、エピソードなども取り上げ、原典を読みものとして紹介した。
CHAPTERI 18〜19世紀
1.Boerhaave症候群の原典
2.Budd-Chiari症候群の原典−George BuddとHans Chiari
3.Luschka管とは何か−Hubert Luschkaの原典を探る
4.Listerの防腐手術の原典
5.Albert-Lembert縫合の原典
6.Hirschsprung病の原典
7.McBurney点,McBurney法の原典
8.Witzelの胃瘻・腸瘻の原典
9.Roux-en-Y吻合の原典
10.Halsted手術の原典
11.Rex-Cantlie線の原典
[コラム]Rex line
CHAPTERII 20世紀前半
1.Kocher授動の原典
2.Pringle法の原典
3.Miles手術の原典
4.Grovesによる網嚢切除術の原典
5.Hartmann手術の原典
6.Electro-surgery(電気メス)手術の原典
7.胃癌治療の原典−未来を見通したバイブル
8.Mallory-Weiss症候群の原典
9.肝再生研究の原典−Higgins and Andersonの方法
10.Crohn病の原典池内浩基
11.Whipple手術の原典part1
12.Whipple手術の原典part2
13.Milligan-Morgan法の原典
14.術中胆道造影の原典−Mirizzi part1
15.Mirizzi症候群の原典−Mirizzi part2
16.Kasabach-Merritt症候群の原典
17.膵全摘術の原典
CHAPTERIII 20世紀後半〜現代まで
1.Gambee吻合の原典
2.肝右葉切除の原典part1−京都大学・本庄による世界最初の肝右葉切除成功例
3.肝右葉切除の原典part2−Lortat-Jacobによる世界最初の肝右葉切除の報告
4.Appleby手術の原典
5.Couinaudの肝区域分類の原典,
6.噴門側胃切除・空腸間置手術の原典
7.Zollinger-Ellison症候群の原典
8.臨床肝移植の原典−Starzl part1
9.肝再生因子(hepatotrophic factor)の原典−Starzl part2
10.Child-Pugh分類の原典part1−オリジナルのChild分類
11.Child-Pugh分類の原典part2−Pughによる改良
12.Klatskin腫瘍(肝門部胆管癌)の原典
13.葛西手術の原典,
14.膵頭部癌に対するregional pancreatectomyの原典−動脈・門脈合併切除再建を伴った一括切除
15.食道静脈瘤に対する杉浦手術(東大第二外科法)の原典
16.免疫抑制薬cyclosporinAの原典
17.自動縫合器の原典
CHAPTERIV 特別篇
1.ノーベル賞と外科医
2.日本における西洋医学part1−アルメイダ,沢野忠庵,シャムベルゲル
3.日本における西洋医学part2−ケンペル
4.日本における西洋医学part3−ツュンベリー
5.日本における西洋医学part4−シーボルト
6.日本における西洋医学part5−ポンぺ
序文
外科に限ったことではないが、医学の世界では、知らない人がいないくらい有名な医学者による超有名な業績に基づいて手術(治療)が行われたり、疾患概念が確立したりしている事例が非常に多い。これらの業績のほとんどは1.2篇の論文に基づいており、後世の関連領域の論文では必ず引用され、その論文の存在を誰もが知っている。しかし、実際にオリジナルの論文(原典)を読んだことがあるかと問えば、実はほとんどない、という事例が少なくない。これはデータに基づかない編者の推論であるが、実際に多くの研究者と話をしてきた経験に基づく実感である。たとえば、肝細胞癌の治療方針を決める際に重要なChild−Pugh分類を知らない外科医はいないはずであるが、そのオリジナルである1964年のChildの論文(実は著書)と1973年に発表されたPughの論文を読んだことのある外科医はどのくらいいるであろうか?Miles手術の原典しかり、McBurney点の原典、Pringle法の原典、Rex−Cantlie線の原典しかり……枚挙にいとまがない。
そんな古い原典を時間と手間をかけて手に入れてわざわざ読まなくても、その主旨を理解して臨床の現場で応用すればよいではないか、要旨を理解して引用すれば論文も書けるし、と考えられる諸兄も多いであろう。確かにそのとおりである。引用するからには100%読んでおくのが論文を書く者の当然の務めである、と原則論をここで述べるつもりはない。もう少し気楽に考えていただいて、これらの原典を純粋に読み物として読んでいただくと、その医学的価値がさらに詳しく正しく理解できるだけでなく、新しい発見があったり、興味ある歴史的背景がわかるものである、ということを紹介することが本書の目的である。
オリジナルの論文(原典)をここでは「外科学の古典」と銘打たせていただき、本書の書名を『外科学の原典への招待』とした。これら原典は、最近はやりの言葉でいえば、その医学領域でパラダイムシフトをもたらしたといえる論文であるが、発表当初から注目されたものもあれば、最初はほとんど注目されなかったのに、あるときその価値が再発見されて広く知られるようになったものもある。「外科学の古典」の定義は、外科医なら誰もが知っている古い(少なくとも30年以上前の)論文である。編者の独断で選ばせていただいた。厳密にいえば外科の論文ばかりではなく、外科に大きな影響を与えた内科や病理学の論文も含まれている。原則英語論文であるが、ドイツ語、フランス語、和文論文も一部含まれる。本書で取り上げた論文の被引用回数を調べてみると、ノーベル賞論文なみに数千回引用されている論文もあれば意外に少ないものもあるし、著書や他言語のため引用回数を調べようのない著名論文もあることがわかる。
本書では論文ごとにその要旨をまとめたうえで表紙ページ、主要な図を引用し、著者の人物紹介、論文の意義と論文や著者にまつわるエピソードを紹介した。著者の経歴については論文検索やインターネット検索を駆使し、また筆者の伝聞情報を含めて手に入る限りの情報を紹介するよう努力したが、なかにはどのような人物であったのかほとんどわからない著者もいた。エピソードも筆者・編者の限られた情報源に基づくものであるので、誤りや誤解、不十分な点も多々あろうことを最初にお断りしておきたい。本書の内容は雑誌「外科」の連載として年1月号から2015年3月号まで掲載されたものを、原典の発表された年代順に並べ直し、再編したものである。本書は読み物として通読いただいてもよいし、目次から目にとまった項をランダムに読んでいただいても十分楽しんでいただけると思う。連載当初は編者が医局の若手の力を借りて始めたが、その後、本連載の主旨に賛同いただいた多くの外科医諸兄のご助力を得て連載を終了することができた。著者の皆様にこの場をかりて厚くお礼を申し上げたい。特に日本における西洋医学について32頁に及ぶ詳細な解説を執筆いただいた竹之下誠一教授、ノーベル賞について特別寄稿をいただいた兼松隆之名誉教授に御礼を申し上げる(特別篇参照)。また、本連載を温かく見守り協力いただいた雑誌「外科」編集委員の亀岡信悟先生、名川弘一先生、佐野武先生に深謝する。
本書は気楽な読み物として、外科のトリビアとしてお読みいただきたい。私事になるが、編者が10数年前に在籍した癌研究会附属病院消化器外科部長(当時)の故高橋孝先生が外科の歴史がお好きで、歴史の勉強会や「古典論文」の抄読会を医局で盛んに主催されていたことをなつかしく思い出す。本書を高橋先生に捧げたいと思う。
2015年4月
國土典宏
学会の書籍展示場で、偶然本書を目にした。手にとって頁を繰り始めたら、もう止められない。その場で全頁に目を通してしまった。國土典宏先生が選び抜かれた原典、外科領域にパラダイムシフトをもたらした業績が、きら星のごとく並ぶ。手術法や疾病概念の原典をたどることによって、先人の積み上げた業績の上に今日の外科学が成り立っていることを再認識する。
本書では、原典の表紙頁、内容要旨、重要な図とともに、著者の詳しい経歴、エピソードが紹介され、肖像もある。そして、どのようにしてその業績が達成されたのか、背景、後の外科学に与えたインパクトが簡潔にまとめられている。
論文を引用するとき、原則としては原典を読んでおくべきであろう。それだけではなく、本書に示されるような周辺の状況、業績の位置づけを知ることも重要である。ただ、多忙な外科医には時間の制約もある。それでも本書を読んで興味をもち、周辺を調べる気になったなら、それこそ編者の意図したところであろう。
白状すれば、本書で取り上げられた原典のうち、筆者自身が原典そのものを読んだとはっきり記憶しているのは、4篇にすぎない。さらに由来をまったく知らなかった論文も多い。たとえば、胃癌手術での意義を説明し、実施してきた網嚢切除の必要性は、Grovesによって1910年に発表されていたこと、術中胆道造影のMirizziがアルゼンチン人で、Mirizzi症候群の報告がスペイン語でなされていたことも、はじめて知った。語源を知らずによく口にしていた「ペッツ」は、1924年にハンガリー人のPetzによって、従来のものを大幅に改良して発表されていた。「ペッツ」から自動縫合器、自動吻合器の時代の経験に思いが飛ぶ。また、筆者自身は脳外科から修業を始めたので、術中に電気メスを使うとき、陣内傅之助先生の「ボビー」という声をよく耳にした。それが人名(Bovie)で、原典は1928年の『Surgery,Gynecology &Obstetrics』に発表されたことも知らなかった。日本人の原典では、三宅速、本庄一夫、葛西森夫、杉浦光雄先生のものが収載されている。いずれも今日の医療における位置づけ(たとえば葛西手術では生体肝移植との関連)が述べられ、理解しやすい。巻末には特別篇として、「ノーベル賞と外科医」、「日本における西洋医学」があり、興味深い。
本書を読みものとして通読すれば、歴史を学ぶ楽しさが味わえる。さらに現役外科医にとっては、どのように術式を改良するか、開発するか、新しい疾病概念をまとめるかを考えるのに役立つ。また教育に携わるなら、学生や研修医の教育で、記憶に残るようにどのようなエピソードをつけ加えるか工夫するために有用であろう。
「歴史を知らない民族は滅びる」という欧州の諺がある。すべての外科医が本書を座右の書とすることをおすすめしたい。
臨床雑誌外科77巻7号(2015年7月号)より転載
評者●市立貝塚病院総長 小川道雄
近年の医学の進歩はめざましいものがある。外科領域も急速に発展しておりわれわれは常にその水準に達しておく必要があり、さらには、そのさらなる向上へと努力を重ねていくことが重要であることはいうまでもない。そのような状況のもと、われわれは診療、研究、そして教育の場で、常に最新のup-to-dateの知識と技術を展開させていくことが責務である。一方で、「今」現在の最先端の医療知識と技術を伝えることや、「これから」将来の展望を示すことにとどまらず、「これまで」過去の歴史の中で先達がどのように考え、どのように対処し、どのような創意工夫をなし、そのためにどのような努力が重ねられたか、さらにはどのような人間ドラマが展開され、それらの歩みがどのように現在に連なったかを学ぶことは「今」、さらには「これから」の外科学を考えるうえでもきわめて重要なことであると思われる。ここで「外科学」の教科書や雑誌に目を移してみると、過去の事象については限られた分量の記載であったり、単発的な記事と掲載にとどまっていることが多いと思われる。そのような状況を鑑み、筆者自身、ある医学雑誌において「外科学 温故知新」なる企画を起案し、シリーズで分担執筆をお願いした経験もある。
今回本書を拝読する機会があり、その編集の姿勢と熱意に圧倒され、たいへん興味深く一気に読ませていただいた。本書は臨床雑誌『外科』の連載として「外科学の古典を読む」というシリーズで掲載されたものを中心に、原典発表の年代順に並べ直して編集されたものである。そして編集主幹は、現日本外科学会理事長東京大学肝胆膵外科・人工臓器移植外科教授の國土典宏先生である。
本書の素晴らしさは、何といっても、外科学におけるさまざまな疾患や手術手技に関して、その「原典」に「直接」接して、その業績を紹介していることである。われわれは往々にして、過去の業績を学ぶ際には、教科書や最近の論文から「間接的」に知識を得ていることが多いと思われる。その際、幕内雅敏先生が本書の推薦文の中で述べられているように、事実に反する事象が一般に認識されていることもありうることを教えられた。ここにまさに「原典」を直接熟読し、それによる正確な知識を得ることの重要性を実感し、本書の編集の姿勢の見事さ、そしてその意義に対し心から感服した次第である。
さらにそのことによって、「原典」を著した多くの先達の「息吹き」や「熱意」が「直接」伝わってくることに大きな喜びを感じることができる。そしてそれと同時に、各々の原典を多大なる努力で調査・解説された、分担執筆者の「息遣い」も伝わってくる。本書には、特別篇として「ノーベル賞と外科医」ならびに「日本における西洋医学」が掲載されている。
本書の執筆と出版に携われた多くの方々のご尽力に深甚なる敬意と感謝の念を表するとともに、本書が外科に携わる医師に限らず、医学生から熟練した医療人に幅広く購読され、また特に若き外科医や外科を志す前途洋々たる若者の外科学への「熱意」と「誇り」を涵養し、今後の外科学の発展に大いに寄与することを切望するものである。
胸部外科68巻12号(2015年11月号)より転載
評者●群馬大学病態総合外科学教授 桑野博行