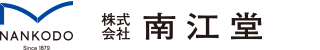マクロライド系薬の新しい使い方
実践の秘訣25
| 編集 | : 門田淳一 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-25769-0 |
| 発行年月 | : 2015年6月 |
| 判型 | : A5 |
| ページ数 | : 162 |
在庫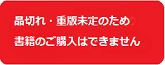
定価3,300円(本体3,000円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

抗菌薬として知られるマクロライド系薬の“抗炎症作用”が再注目され、マクロライド系薬の使い方は新しい時代を迎えている。びまん性汎細気管支炎(DPB)に始まり、COPDからインフルエンザまで他の慢性/急性炎症性疾患に応用の幅が広がっている。本書は具体的な疾患を例に挙げ、”新しい使い方”を基礎・臨床両面の視点から25個の秘訣としてまとめた。各項の冒頭には重要となる「ポイント」を提示するなど薬の応用をわかりやすく解説した実践書。
I マクロライド系薬のnovel actionを理解しよう
(1)マクロライド系薬は抗炎症薬である
(2)炎症細胞とマクロライド系薬
(3)気道上皮細胞とマクロライド系薬
(4)細胞内分子機構とマクロライド系薬
(5)マクロライド系薬が微生物の機能に及ぼす作用
II 慢性気道感染症とマクロライド系薬
(6)びまん性汎細気管支炎におけるマクロライド系薬のエビデンス
(7)副鼻腔気管支症候群と気管支拡張症にマクロライド療法は有効か
(8)マクロライド系薬をどう使う−どれから使用し,いつまで使うか
III 閉塞性肺疾患とマクロライド系薬
(9)COPDの増悪を予防するマクロライド療法とは−そのエビデンス
(10)マクロライド療法が期待できる気管支喘息の病態とエビデンス
IV 急性呼吸器感染症とマクロライド系薬
(11)インフルエンザウイルス感染症におけるマクロライド系薬の併用とそのアジュバント効果の意義−小児領域
(12)インフルエンザウイルス感染症におけるマクロライド系薬の併用と意義−成人領域
(13)マクロライド耐性マイコプラズマに対する有効性とその機序
(14)肺炎の生命予後を改善するマクロライド併用療法のエビデンス
(15)マクロライド療法は繰り返す肺炎の罹患頻度を減少させるか
V 非結核性抗酸菌症とマクロライド系薬
(16)肺MAC症の標準治療としてのマクロライド療法の有効性は−治療開始時期と終了時期はどうするのか
(17)肺MAC症におけるerythromycin単剤療法の可能性
VI その他の呼吸器疾患とマクロライド系薬
(18)嚢胞性線維症におけるマクロライド系薬のエビデンスと日本における使用状況
(19)関節リウマチ関連細気管支炎および移植後閉塞性細気管支炎にマクロライド系薬は有効か
(20)急性呼吸窮迫症候群および間質性肺炎の急性増悪に対してマクロライド系薬は有効か
VII 耳鼻咽喉科疾患とマクロライド系薬
(21)慢性副鼻腔炎におけるマクロライド系薬のエビデンス−その有効性と限界
(22)滲出性中耳炎にマクロライド系薬は有効か
VIII マクロライド系薬の最新トピックス
(23)マクロライド長期療法と耐性菌誘導のリスクは関連するのか
(24)マクロライド系薬とpolypharmacology
(25)日本発のマクロライド系薬の新作用と創薬展開
序文
1952年にerythromycinが発見されて以来、マクロライド系薬は抗菌薬として感染症診療において多くの貢献をしてきたが、1980年代に入ってびまん性汎細気管支炎(diffuse panbronchiolitis:DPB)に対する少量長期療法の有用性が確立し、新たな時代を迎えた。マクロライド系薬は少量長期療法という従来の抗菌化学療法の常識を超えた投与法によってDPBの予後を著明に改善した薬剤であり、これほど予後を改善させた薬剤は他には見当たらない。その有効性の機序として抗菌活性以外の作用である抗炎症作用や抗微生物作用、および細胞内分子機構などの新作用が明らかになるにつれて、DPBにとどまらず他の慢性炎症性疾患や急性炎症性疾患にも応用の幅が広がってきた。通常、薬剤は作用機序を基に開発がなされ臨床応用へと進展するものであるが、マクロライド系薬に限っては臨床的有用性を基に作用機序の解明がなされ、さらにその作用機序から種々の疾患への臨床応用が展開してきた稀有な薬剤である。つまりbed to bench、bench to bedを繰り返しながら進化してきた薬剤で、translational researchの真髄と言っても過言ではない。まだまだ未解明の部分も多く残されているためマクロライド研究の興味は尽きることはなく、今後もさらに進化を続けていくに違いない。
これまでマクロライド系薬の臨床効果や作用機序の解明に関してはそれぞれの領域を中心に研究・実践がなされ、新作用に関する知識を総括的に理解・実践する機会は少なかった。そこでマクロライド系薬のnovel actionの研究がはじまって30年が経過しようとしているこの機会に、これまで蓄積されてきた各領域の臨床研究および基礎研究を網羅した総括的な書籍として、『マクロライド系薬の新しい使い方−実践の秘訣25』を発刊することになった。現在までに解明された事象の理解と実践、および将来の展望をもとに25のパートに分類することで読者の興味のある領域から入っていけるようにしている。専門領域の先生にはもちろんのこと実地医家の先生にもわかりやすい実践書として、常に手元に置いて活用していただければ幸いである。
また、執筆をお引き受けいただいた先生方や30年にわたりマクロライド研究を遂行されてきた多くの先生方にMacrolider(マクロライダー)の一人として敬意を表するとともに、今後のさらなる医学研究の進展に本書が少しでもお役にたてばこの上ない幸せである。
2015年5月吉日
門田淳一
「マクロライドの新作用」という言葉を知らない医師はほとんどいないと思われるが、その端緒をつくったのはわが国の開業医師である(松本市宮澤内科医院、宮澤 博医師、新潟大学薬理学教室出身)。今日、マクロライド療法は、Fraser &Pareの「Diagnosis and Disease of the Chest第3版」(1989年)以来、欧米の教科書に記載され、米国内科専門医更新試験にも出題されるなど普遍的になっているが、わが国で確立された治療法なのである。すなわち、重症化したびまん性汎細気管支炎(DPB)の患者が宮澤内科医院に転院した後、著明に改善したことを見逃すことなく、同医院で行われていたerythromycin(EM)少量長期投与の効果を多数例で検討・報告した工藤翔二らと、それに続いたわが国の多くの医学者がこの金字塔を確立したのである。なお、宮澤医師の在籍した新潟大学では、第二内科の桂 重鴻教授の時代にtetracycline少量長期投与療法が行われていたという。
1941年のペニシリンGの実用化以来、抗菌薬は多くの生命を救ってきたが、1980年代以降、抗菌作用ではないマクロライド系薬の新作用によって助かった人も増えている。その端緒となったDPBは、かつては呼吸器領域の難病であり、1970年代までは10年生存率が30%台であった。細菌感染を反復して多くが緑膿菌感染にいたり、呼吸不全で亡くなっていたが、緑膿菌には抗菌力がほとんどないEMの投与で1990年代以降、その10年生存率は90%台と劇的に改善した。これは、工藤翔二らの1987年のEM少量(1日量600mg)長期療法の有効性に関する初めての報告を経て、1990年厚生省研究班(班長:田村昌士、分科会長:山本正彦)による全国規模のプラセボを用いた二重盲検比較試験でその効果が確認されてからの成果である。
今日、EMを含む14員環および15員環マクロライド系薬の新作用は、細菌感染症以外にもウイルス感染症その他へ、呼吸器以外でも耳鼻咽喉科領域その他へ応用が広がりつつある。すなわち、その効果はDPB以外にも気管支拡張症や副鼻腔気管支症候群などの慢性気道感染症で認められ、COPDや気管支喘息などの閉塞性肺疾患でも有効性が確認されつつある。また、わが国では200万出生に1人ときわめて少なく、欧米では5,000出生に1人と多い嚢胞性線維症(cystic fibrosis)では、欧米からazithromycin長期投与の報告がある。さらには、インフルエンザウイルス感染症などの急性呼吸器感染症、肺炎の生命予後改善にも効果が確認されつつある。一方、本来の抗菌作用は非結核性抗酸菌症の治療にも及び、肺MAC(Mycobacterium avium-intracellulare complex)症に対してはclarithromycinが必須のキードラッグとなっている。
北里研究所の大村 智らはかつて、EMには消化管蠕動ホルモンのモチリンに類似した作用があることをすでに報告していたが、新作用の機序の解明は臨床での華々しい成果に触発されて進んできた。今日では、気道炎症の病態の改善に関わるさまざまな作用機序が明らかになっているが、臨床で得られた成果が基礎的な解明を進め、それが臨床応用の範囲を広げ、そこから再び基礎の進歩が促されるというtranslational researchの最たる成果といえよう。
本書は、このマクロライド療法が確立してから30年になる今、本来の抗菌作用をも含みながら幅広い新作用を中心に、「どのような疾患へどのように使うのか?」、「その作用はどこまで及び、その範囲をどのように見極めるのか?」、「いつ、止めるのか?」、など多岐にわたる問題を一冊で概観できる書籍であり、呼吸器科医のみならず多くの領域の臨床医に一読してほしい。
臨床雑誌内科117巻2号(2016年2月号)より転載
評者●東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門教授 渡辺彰