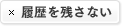�V���v�����w�Ö@�w�V���[�Y
�_�o�؏�Q���w�Ö@�w�e�L�X�g�mWeb����t�n������4��
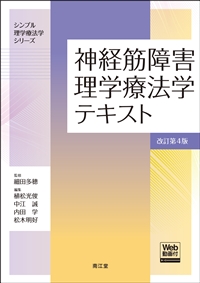
| �ďC | : �דc���� |
|---|---|
| �ҏW | : �A�����r/���]��/���c�w/���ؖ��D |
| ISBN | : 978-4-524-23466-0 |
| ���s�N�� | : 2025�N3�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 488 |
��
�艿6,600�~(�{��6,000�~ �{ ��)
����\
-
2025�N07��11��
��1��
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

���w�Ö@�m���������邱�Ƃ̑����_�o�؏�Q�ɂ��āC�����@���C��Q�̕]���C���w�Ö@�̎��ۂ܂ł�����������ȏ��D�������ł͐������̃��n�r���e�[�V�����ɂ��Ă��L�q���[�������C��莞��ɑ��������e�ւƃA�b�v�f�[�g�����D�܂��C����������̓I�ɃC���[�W�ł���悤�C�Ж�ჁC�Ґ������ɂ����铮�������̗l�q�̓���𑽐����ڂ����D
���@�_
�P�@�_�o�؏�Q�̑S�e
�@A�@�_�o�،n�Ƃ�
�@�@�@�����_�o�̑S�̑�
�@�@�A�_�o�n�̕���
�@�@�B�̐��_�o�̏o�͌n
�@�@�C�^����Q�̌���
�@B�@�_�o�؏�Q�̓����ƏǏ�
�@�@�@�����_�o��Q�̌����Ɠ���
�@�@�A�����_�o��Q�ɂ��Ǐ�
�@�@�B�]�����������Q
�@�@�C�Ґ������Ő������Q
�@�@�D�^���̒��ߌn��Q
�@�@�E���̑��̐_�o�؏�Q
�@C�@�����_�o��Q�Ɨ��w�Ö@�ɂ�����^��
�@�@�@���w�Ö@�̎��Î�i
�@�@�A�����_�o��Q�҂ɑ���^���Ö@�̈Ӗ�
�@�@�B�^���Ö@�̌���
���
�Q�@�Ж�Ⴢ̌����C�]���Ǐ�Q�Ƃ�
�@A�@���ǂ̌���
�@�@�@�]���Ǐ�Q
�@�@�A�]���
�@�@�B�����O��
�@�@�C�������d����
�@B�@�]���Ǐ�Q�̗����̂��߂̔]�̍\���Ƌ@�\
�@�@�@�]�����̍\��
�@�@�A�]�����̟��z�̈�
�@�@�B���̘H�Ɣ]�����̊W
�@C�@�]���Ǐ�Q�Ƃ�
�@�@�@NINDS�̕���
�@�@�A�]���Ǐ�Q�̐_�o�w�I����
�@�@�B�]���Ǐ�Q�Ɖ^�����
�R�@�]���Ǐ�Q�̐f�f�C�}��������
�@A�@�]���Ǐ�Q�e�a�^�̓���
�@�@�@�]�o��
�@�@�A�N�������o��
�@�@�B�]�[��
�@B�@�]���Ǐ�Q�̉摜�f�f
�@�@�@�]�o��
�@�@�A�N�������o��
�@�@�B�]�[��
�@C�@�]���Ǐ�Q�̋}�������Âƃ��n�r���e�[�V����
�@�@�@�}�����̎���
�@�@�A�a���ƃ��n�r���e�[�V����
�@�@�B�p�p�nj�Q�ƃ��n�r���e�[�V����
�@�@�C���w�Ö@�iPT�j�̊J�n��ƃ��X�N�Ǘ�
�@�@�D�}�����̃x�b�h�T�C�h�ł̃��n�r���e�[�V����
�S�@�Ж���҂̕]���@
�@A�@�]���̍l����
�@�@�@�@�\��Q�����̌o�܂Ə�Q�̓���
�@�@�A���ې����@�\���ށiICF�j�Ɨ��w�Ö@
�@�@�B���w�Ö@�]���̒���_
�@B�@�]���Ǐ�Q�̑����I�ȕ]��
�@�@�@���X�N�Ǘ�
�@�@�A�����E����̐�������
�@�@�B�]���Ǐ�Q�̑����]��
�@C�@�Ж���҂̋@�\��Q�ɑ��闝�w�Ö@�]��
�@�@�@�]���Ǐ�Q�̈ꎟ��Q�ɑ��錟���E����
�@�@�A�]���Ǐ�Q�̓�Q�ɑ��錟���E����
�@�@�B�g�̉^���̐��s�ɑ��錟���E����
�@D�@���������E�Q������Ȃǂ̊ώ@�ƒ���
�@�@�@���������iADL�\�́j�̊ώ@�ƒ���
�@�@�A�Q������̕]��
�T�@�Ж���҂̕]���A
�@A�@���w�Ö@�]���̎���
�@�@�@���w�Ö@�]���̖ړI
�@�@�A�]�����ڂ̑I��Ǝ��O�����W
�@�@�B�]���̎菇
�@�@�C�����Ɖ���
�@�@�D�ڕW�ݒ�
�@�@�E�ڕW�ݒ�ɕK�v�ȗ\��\��
�@B�@�]���Ɋ�Â������w�Ö@�̂����
�@�@�@�]���Ɋ�Â������w�Ö@�v���O�����̍l����
�@�@�A�����̍ĕ]���̏d�v��
�@�@�B�]���Ǝ��Â̐U��Ԃ�
�U�@�d�ǕЖ�თ�ɑ�������w�Ö@�̎��ہi����1�j
�@A�@�Ȃ��d�Ǔx�ʂ̗��w�Ö@���K�v�Ȃ̂��H
�@�@�@�d�ǕЖ�თ�Ƃ�
�@�@�A���w�Ö@�̖ړI�𗝉�����
�@�@�B�p�p�nj�Q�̖��
�@B�@ADL�̕K�{����C���쐋�s�̗͌�
�@�@�@ADL�Ɗ�{����
�@�@�A��{����̗͌�
�@�@�B��ʌy���̈Ӌ`
�@�@�C�e����C�P���p�@��̊��p
�@C�@�^���Ö@�̎��ہi�d�͂Ƃ̊W�j
�@�@�@�d�ǕЖ�თ�ɑ���^���Ö@�̊�{
�@�@�A�ŗD�捀�ڂ͍R�d�͈ʎp���ւ̕ϊ�
�@�@�B�R�d�͈ʎp���ƃ��X�N�Ǘ�
�@�@�C�R�d�͈ʎp���ւ̕ϊ�
�V�@�d�ǕЖ�თ�ɑ�������w�Ö@�̎��ہi����2�j
�@A�@�^���Ö@�̎��ہi�؎��k�̊֗^�j
�@�@�@�R�d�͈ʎp���Ƌ؎��k���^��
�@�@�A�����I����s�̗��ӓ_
�@�@�B�؎��k���^��
�@�@�C�؎��k��Ȃ��^��
�@B�@�^���Ö@�̎��ہiADL�ւ̔��f�j
�@�@�@��{����i�N���ړ�����j�P��
�@�@�AADL�P���Ɨ��w�Ö@
�@�@�B���ʎp�����܂ޕ����I����
�@C�@�����]�@�\��Q�C�̊��@�\��Q�ɑ���H�v
�@�@�@�p���̈��艻�C�ۑ蓮��̒P����
�@�@�A�m���ȗ͌��̊��p
�@D�@�a���Ƃ̘A�g�C�Љ�A�Ɍ�����������
�@�@�@���l�ς̋��L
�@�@�A�Љ���̊��p
�W�@���K
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@�d�ǕЖ�ჂƔp�p�nj�Q�̊W
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n�d�ǕЖ��
�X�@�y�ǕЖ�თ�ɂ���������琶�������݂��������w�Ö@�̎��ہi����1�j
�@A�@�y�ǕЖ�ჂƂ�
�@B�@�Ж���҂ɂ�������s
�@�@�@�u���s�v�Ƃ����^���̂��Ӌ`
�@�@�A���肵�����s�ɕK�v�ȗv�f
�@�@�B��\�I�ȕ��s�̓���
�@C�@���w�Ö@�̎���
�@�@�@�Z��������iAFO�j�̓K���Ɨ��ӓ_
�@�@�A���s�ɂ����闝�w�Ö@
�@�@�B�y�ǕЖ�Ⴢ̉^���ɂ���
10�@�y�ǕЖ�თ�ɂ���������琶�������݂��������w�Ö@�̎��ہi����2�j
�@A�@���w�Ö@�̎��ہi����1�j
�@�@�@�Ж�Ⴢɑ���_�o�؍ċ���@
�@�@�A�ݑ�A���������w�Ö@�ɂ����闯�ӓ_
�@B�@���w�Ö@�̎��ہi����2�j
�@�@�@�Љ�A�Ɍ��������w�Ö@
�@C�@�Љ�̗v���ɉ�����u���w�Ö@�m�v�ł��邽�߂�
11�@���퐶���ɂ�����g�̋@�\�̊��p�i�����@�\�̌���j
�@A�@�Ж���҂̓��퐶�������ɂ����闝�w�Ö@�m�̖���
�@B�@��{����
�@�@�@�Q�Ԃ�
�@�@�A�N���オ��
�@�@�B���@��
�@�@�C�����オ��
�@�@�D���@��
�@�@�E�ځ@��
�@�@�F���@�s
�@�@�G�Ԃ����쓮
�@�@�H�K�i���~
�@C�@�Z���t�P�A
�@�@�@�H�@��
�@�@�A���@�e
�@�@�B�g�C������
�@�@�C�X�ߓ���
�@�@�D���@��
�@D�@�������̐_�o�؎������҂ɂ�������\�h�E�����x����ړI�Ƃ����ʏ��^�Z���W���\�h�T�[�r�X�̕K�v��
12�@���K2
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@�e�]�����ڂ̈Ӌ`
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n�y�ǕЖ���i�\��ǍD��j
13�@���K�P
�@A�@�Ж�҂̓���ɂ��������
�@B�@�Ж�Ⴢ̊�{����
�@�@�@�Q�Ԃ�
�@�@�A�N���オ��
�@�@�B�x�b�h����̗����オ��
�@�@�C�ڏ擮��
�@�@�D������̗����オ��
�@�@�E����s
�@C�@�ڏ�̍ő��@�̏K���C�Ԃ����̋쓮
�@�@�@�ő��i��ბ������̎x�������Ⴂ�j�̈ڏ�
�@�@�A�Ԃ����̋쓮�i���ʌ^�̎Ԃ������g�p�j
�@D�@����̑���
�@�@�@��������̑���
�@E�@�d�x�Ж�҂ɑ��锼�����I����s
14�@�Ж�҂ɂ݂��鍇���ǂƂ��̑�
�@A�@�Ж�҂ɂ݂��鍇����
�@�@�@�p�p���̗v���ɂ�鍇���� �� �p�p�nj�Q
�@�@�A��p���̗v���ɂ�鍇���� �� ��p�nj�Q
�@�@�B���̑��̗v���ɂ�鍇����
�@�@�C�����ǂɂ��d����Q
�@�@�D�����ǂɑ���\�h�I���w�Ö@�̏d�v��
�@B�@�����ǂ̓���
�@�@�@�x�@��
�@�@�A�؈ޏk�E�ؗ͒ቺ
�@�@�B�̗͒ቺ
�@�@�C�[���Ö������ǁiDVT�j
�@�@�D���߈��E�P
�@�@�E���ߒɁC����nj�Q
�@�@�F�ߍS�k
�@�@�G�����G
15�@�����]�@�\��Q�E�ېH������Q�Ɨ��w�Ö@
�@A�@�����]�@�\��Q���҂̗��w�Ö@
�@�@�@��\�I�ȍ����]�@�\��Q
�@B�@�ېH������Q�̗��w�Ö@
�@�@�@�ېH������Q�̊T�v
�@�@�A�ېH�����̊e��
�@�@�B�ېH������Q�̕]��
�@�@�C�ېH������Q���҂̌P��
�^������
16�@�^�������Ƃ�
�@A�@�^�������̒�`
�@B�@���]�̍\���Ǝ�v���˘H
�@C�@�������ʂɂ��^�������̕��ށE����
�@D�@���]�̋@�\�����Ƌ����^������@�\
�@E�@���]���^�������̏Ǐ�̓���
�@�@�@�c���敪�ɂ��Ǐ�̓���
�@�@�A�����敪�ɂ��Ǐ�̓���
�@�@�B�nj�w����݂��^�������̓T�^�I�ȏǏ�
�@F�@�]���Ǐ�Q�ɂ��^�Ə��]�ϐ������ɂ��i�s�^�̓���
�@�@�@�^�i�]���Ǐ�Q�ɂ����́j
�@�@�A�i�s�^�i���]�ϐ������j
�@G�@�^�������̕]��
�@�@�@�l���̉^������
�@�@�A�؋ْ��ቺ
�@H�@�p���o�����X�ƕ��s��Q
�@�@�@�p���o�����X
�@�@�A���@�s
�@�h�@��ʓI�ȗ��w�Ö@�]���̍l����
17�@���]���^�������̗��w�Ö@
�@A�@���w�Ö@�̍l����
�@�@�@�T�@�v
�@�@�A�����ƏǏ�
�@�@�B�����Ǐ�
�@�@�C�����Ɋ�Â������w�Ö@
�@�@�D�l��������ʂ̔w�i
�@B�@�^�������̌����Ɠ���
�@�@�@���]���^������
�@�@�A��]���^������
�@�@�B�Ґ����^������
�@�@�C���H���^������
�@C�@���]���^�������Ǘ�̕]��
�@D�@�^���Ö@�̎���
�@�@�@�����Ǝ�����
�@�@�A�ړI��
�@E�@���̑��̉��
�@�@�@���̎g�p
�@�@�A�Z���̒���
�@�@�B�Ƒ��ւ̉�w��
�@�@�C�Љ�T�[�r�X�̓�������
18�@���K3
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@�^�������̕a��
�@�@�A���]���^�������ɑ��闝�w�Ö@�̎��_�ƒ��ӓ_
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n�^������
�p�[�L���\���Ǐ�
19�@�p�[�L���\���a�Ƃ�
�@A�@�p�[�L���\���a�̕a��
�@�@�@�T�@�v
�@�@�A��]���j�̋@�\
�@�@�B�Տ��Ǐ�
�@�@�C�p�[�L���\�j�Y����悷�鎾��
�@�@�D�\�@��
�@B�@���@��
�@�@�@�Ö@
�@�@�A��p�Ö@
�@�@�B���n�r���e�[�V����
�@C�@���w�Ö@�]��
�@�@�@�z�[�G�������[���iHoehn��Yahr�j�̏d�Ǔx����
�@�@�AUnified Parkinson�fs Disease Ratin�@G�@Scale�iUPDRS�j
�@�@�BFreezin�@G�@o�@F�@Gait questionnaire�iFOGQ�j
�@�@�CBalance Evaluation Systems Test�iBESTest�j
�@�@�DTimed Up and Go test�iTUG�j
�@�@�E���̑��̕]��
20�@�p�[�L���\���a�̗��w�Ö@
�@A�@�ځ@�I
�@B�@�]�@��
�@C�@���w�Ö@�C�^���Ö@�̍l�����i�^���Ǐ�ւ̑Ή��j
�@�@�@�a���i��Q���x�j�ɑΉ����闝�w�Ö@
�@�@�A�p�p�nj�Q�ւ̑Ή�
�@�@�B��܂̍�p�E����p�Ƃ̊W
�@�@�C���s�P��
�@�@�D���̊��p
�@�@�EADL�ւ̔��f
�@�@�F�]�|���X�N�̉��
�@�@�G�p�[�L���\�j�Y���̗��w�Ö@
�@�@�H�^���Ǐ�ɑ��鐶�����̗��w�Ö@�̎���
�@D�@��^���Ǐ�ւ̑Ή�
�@�@�@������Q
�@�@�A���_�E�F�m�E�s����Q
�@�@�B�����_�o�Ǐ�
�@�@�C���o��Q
�@�@�D���̑�
�@�@�E��^���Ǐ�ɑ��鐶�����̗��w�Ö@�̎���
�@E�@�܂Ƃ�
21�@���K4
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@���̘H��Q�Ɛ��̊O�H��Q�̑���
�@�@�A�p�[�L���\���a�̓���
�@�@�B�p�[�L���\���a�Ənjp�[�L���\�j�Y���ɂ���
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n�p�[�L���\���a
���̑��̐_�o��Q
22�@�����O���C��_�f���]��
�@A�@�����O���Ƃ�
�@�@�@�����O���̓����C����
�@�@�A�ǁ@��
�@�@�B���w�Ö@�̍l����
�@�@�C�]���̎���
�@�@�D���w�Ö@�̎���
�@�@�E�Љ�A�Ɍ������ۑ�
�@B�@��_�f���]��
�@�@�@�����̌����Ɠ���
�@�@�A��������
�@�@�B��Q�̓���
�@�@�C���w�Ö@�̍l����
�@�@�D�]���̎���
�@�@�E���w�Ö@�̎���
�@�@�F�Љ�A�Ɍ������ۑ�
23�@�������d���ǁC�؈ޏk�������d����
�@A�@�������d����
�@�@�@�����T�O
�@�@�A�f�f�Ǝ���
�@�@�B���n�r���e�[�V�����C���w�Ö@�̍l����
�@�@�C�]���Ɨ��w�Ö@�̎��ہE�l���_
�@�@�D���w�Ö@���{��̍l���_
�@B�@�؈ޏk�������d���ǁiALS�j
�@�@�@�����T�O
�@�@�A�^���j���[���������ɂ���
�@�@�B�f�f�Ǝ���
�@�@�C���n�r���e�[�V�����̈Ӌ`
�@�@�D���w�Ö@�̍l����
�@�@�E�]���Ɨ��w�Ö@�̎���
�@�@�F�^���Ö@�����̉��p
�@�@�G����Љ�
24�@���̑��̐_�o�،n��Q�i�W�X�g���t�B�[�C�������؉��C�d�Njؖ��͏ǁCGuillain-Barré�nj�Q�j
�@A�@�W�X�g���t�B�[
�@�@�@�����T�O
�@�@�ADuchenne�^�W�X�g���t�B�[�iDMD�j
�@�@�BBecker�^�W�X�g���t�B�[�iBMD�j
�@�@�C���̌^�W�X�g���t�B�[�iLGMD�j
�@�@�D��V���i���R�^�j�W�X�g���t�B�[�iFCMD�j
�@B�@�������؉��iPM�j�C�畆�؉��iDM�j
�@C�@�d�Njؖ��͏ǁiMG�j
�@D�@Guillain-Barré�nj�Q�iGBS�j
�l����ჁE�Ζ��
25�@�Ґ��̉�U�E�@�\�C�Ґ������̌���
�@A�@�Ґ��̍\���Ƌ@�\
�@�@�@�Ґ��̊O�i
�@�@�A�Ґ��̓��i
�@�@�B�Ґ��̌���
�@�@�C�Ґ����̓`���H
�@�@�D�畆�߂Ƌؐ�
�@�@�E�Ґ�����
�@�@�F�����_�o�@�\
�@B�@�Ґ������̌���
�@C�@��Ⴢ̎��
�@D�@�Ґ������̏�Q��
�@�@�@�Ґ��V���b�N
�@�@�A�Ґ��s�S�����̊e���ԂƏǏ�̓���
�@�@�B�������ʂ̕\���Ɛg�̏�Q�͈�
�@�@�C�Ґ������̎��ÊT�v
26�@�����_�o�ƐҐ������̐����Ǐ�E������
�@A�@�����_�o�̍\���Ƌ@�\
�@�@�@�̐��_�o�Ǝ����_�o
�@�@�A�����_�o�ƕ������_�o
�@�@�B�����_�o�̉��S�H�Ƌ��S�H
�@�@�C�����_�o�n�̐_�o�`�B����
�@B�@�Ґ������̐����Ǐ�
�@�@�@�ċz��Q
�@�@�A�N�����ጌ��
�@�@�B�r�A��Q
�@�@�C�����Ǐ�Q
�@�@�D�����_�o�ߋْ�����
�@�@�E�̉����ߏ�Q
�@�@�F�ُ�������
�@C�@�Ґ������̔p�p�nj�Q
�@�@�@��@�
�@�@�A�؈ޏk
�@�@�B���ޏk
�@�@�C�ߍS�k
�@�@�D���̑�
�@D�@��Q��e�ߒ�
27�@�Ґ������̕]��
�@A�@�Ґ������̕]���̍l����
�@�@�@��Q���f���Ɨ��w�Ö@�]��
�@�@�A���w�Ö@�̎��{���e�ւǂ̂悤�ɕ]���f���邩
�@�@�B��ʂ���щ��ʉ^���j���[������Q
�@�@�C�Ґ��������琶���閃Ⴢ̗���
�@�@�D�Ж�Ⴡi�]�����j�]���Ƃ̑Δ�
�@B�@���w�Ö@�]��
�@�@�@�_�o�w�I����
�@�@�A�������ʂ̔���@
�@�@�B�ؗ͂���ъ��o�����̈Ӌ`
�@�@�C��Ⴢ̒��x
�@�@�DASIA�̋@�\��Q�ړx�iAIS�j
�@�@�E�U���R���[�̕���
�@�@�F���s�\�͂̕]���iWISC�@�h�@�U�j
�@C�@���w�Ö@�]���̎���
�@�@�@�o�C�^���T�C���̃`�F�b�N
�@�@�A�@�\��Q�ɑ���e��e�X�g
�@�@�B�p�p�nj�Q�̃`�F�b�N
�@�@�CADL�]��
�@�@�D��{����e�X�g
�@�@�E���앪��
�@�@�F���w�Ö@�]���̎���
28�@�l����Ⴢ̗��w�Ö@�i�}�����j
�@A�@�}�������w�Ö@�̖ړI
�@�@�@���`�O�ȓI���Â̗���
�@�@�A�I�����ǂ̗\�h
�@B�@�x�b�h�T�C�h�̗��w�Ö@
�@�@�@�ċz���w�Ö@
�@�@�A�ǎ��ʂƑ̈ʕϊ�
�@�@�B�߉���̈ێ��C�g��
�@�@�C�͈ؗێ��E����
�@�@�D�d�́i�N���j�ϐ��̌���
29�@�l����Ⴢ̗��w�Ö@�i���j
�@A�@�����w�Ö@�̖ړI
�@�@�@�c���\�͂̋���
�@�@�AADL�\�͂̍č\�z
�@�@�B�I�����ǂ̗\�h
�@B�@���w�Ö@�̎���
�@�@�@�߉���̊g��
�@�@�A�ؗ͋���
�@�@�B�o�����X�P��
�@�@�C���㓮��
�@C�@ADL�P��
�@D�@�I�����ǂ̗\�h
30�@���K5
�@A�@�O���[�v���c
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n����
31�@���K2
�@A�@�l����҂̊�{����
�@�@�@�Q�Ԃ蓮��i���������ւ̐Q�Ԃ蓮��̏ꍇ�j
�@�@�A�N���オ�蓮��
�@�@�B�v�b�V���A�b�v����
�@�@�C�ڏ擮��i�g�����X�t�@�[�j
�@�@�D�Ԃ����쓮
32�@�Ζ�Ⴢ̗��w�Ö@�i�}�����j
�@A�@�}�������w�Ö@�̖ړI
�@�@�@���`�O�ȓI�������Ö@�̊T�v
�@�@�A�I�����ǂ̗\�h
�@�@�B�c���@�\�E�\�͂̈ێ��C����
�@B�@�x�b�h�T�C�h�̗��w�Ö@
�@�@�@�ċz���w�Ö@
�@�@�AROM�P��
�@�@�B�͈ؗێ��E�����P��
�@C�@�������ւ̓K��������ɓ��ꂽ���g��
33�@�Ζ�Ⴢ̗��w�Ö@�i���j
�@A�@�����w�Ö@�̖ړI
�@�@�@�c���\�͑�����ADL�\�͍č\�z
�@�@�A�Ԃ�������ɂ��ADL����
�@B�@���w�Ö@�̎���
�@�@�@�R�d�͈ʑϐ��̌���
�@�@�A�v�b�V���A�b�v����C�ڏ擮��̊m��
�@�@�B�߉���̈ێ����P�C�ؗ͑���
�@�@�C���i�}�b�g�j�㓮��
�@�@�D�Ԃ�������C���p����i�L���X�^�[�グ�j
�@�@�E���s�P��
�@C�@ADL�P��
�@�@�@�e���C����
�@�@�A�Ԃ�������ƕ��s����̃G�l���M�[�����r
�@�@�B���p�I�ړ���i�̊m��
�@�@�C������Ƃ̘A�g
�@�@�D�H���C�r���C���e�C�X�߁C��������Ǝ�����ɂ���
�@�@�E�N���P��
34�@���K6
�@A�@�O���[�v���c
�@B�@�Ǘ�̒ɂ�郍�[���v���C
�@�m�Ǘ�n��������
35�@���K3
�@A�@�Ζ�҂̊�{����
�@�@�@�Q�Ԃ蓮��
�@�@�A�N���オ�蓮��
�@�@�B�v�b�V���A�b�v����
�@�@�C�ڏ擮��
�@�@�D���~�ڏ擮��
�@�@�E�Ԃ����쓮
�@B�@�Ζ�҂̎Ԃ������p����
�@C�@�Ζ�҂̗��ʁE���s����
�@�@�@���ʕێ�����
�@�@�A���s����
36�@�s�S����
�@A�@�s�S�����̉u�w�ƕa��
�@�@�@�u�@�w
�@�@�A�a�@��
�@�@�B�s�S�����̏Ǐ�
�@�@�C�Տ���
�@�@�D���S�������̊��������������킯
�@�@�E���o��Q�i�ُ튴�o�j
�@B�@���w�Ö@�]��
�@�@�@�]�@��
�@�@�AISNCSCI
�@�@�BFrankel����
�@�@�C����Frankel����
�@�@�DISMG�̑����ϔ�
�@�@�EWISC�@�h�@�U
�@�@�FSCIM
�@C�@���w�Ö@
�@�@�@���@��
�@�@�A���ʌP���̑O�ɍs���P��
�@�@�B���ʁC�e�B���g�e�[�u����p����
�@�@�C���s�_����s
�@D�@�̏d�Ɖ��g���b�h�~���g���[�j���O�iBWSTT�j
�@�@�@BWSTT�̓���
�@�@�ABWSTT�̑Ώێ�
�@�@�B�P���̎��ہi�v���O�����C���ӓ_�j
�@�@�C���ʂ̋@��
�@E�@����҂ɂ����钆�S���������҂̓]�|�\�h�ɂ���
�t�^�F���K�̉�
���K1�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@B�@�Ǘጟ��
���K2�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@B�@�Ǘጟ��
���K3�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@�^�������̕a��
�@�@�A���]���^�������ɑ��闝�w�Ö@�̎��_�ƒ��ӓ_
�@B�@�Ǘጟ��
���K4�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@���̘H��Q�Ɛ��̊O�H��Q�̑���
�@�@�A�p�[�L���\���a�̓���
�@�@�B�p�[�L���\���a�Ənjp�[�L���\�j�Y���ɂ���
�@B�@�Ǘጟ��
���K5�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@�����ɂ�����e���ߋ@�\�c�����x���ł̎�v�@�\��
�@�@�A�e���ߋ@�\�c�����x���̉\�Ȋ�{����
�@�@�B�����ԉ^�]�����邽�߂ɕK�v�Ȃ���
�@B�@�Ǘጟ��
���K6�̉�
�@A�@�O���[�v���c
�@�@�@������������э��������ɂ�����c������юc���@�\
�@�@�A������������э��������ɂ������{���삨���ADL�\��
�@�@�B�Ζ���҂ɂƂ��ĕK�v�ȉƉ��������̎��
�@�@�C�d���𑱂��邽�߂ɕK�v�ȏ��E�葱��
�@B�@�Ǘጟ��
�Q�l����
���@��
������4�ł̏�
�@�{�����ł́C�����_�o��Q���w�Ö@�K�C�h���C�����f���u����w�K���ʂɏd�_���������e�L�X�g�v�ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���C�u�V���v�����w�Ö@�w�V���[�Y�v�̑�3���Ƃ��āC�ȉ��̕ҏW��{���j�ɑ�����2008�N�Ɋ��s���ꂽ�D
���w���ɂƂ��đS�̓I�ȏ�Q�����C���[�W���邱�Ƃ������Q�̈�ɂ��āC�Տ����K�⑲��̗Տ�����ɏo��ۂɔ����Ċw��ł����ׂ��K�v�ŏ����̊�{�I�m���C�Z�p���ڂ��킩��₷���\���C�������D
����Q�ɂ������������ނŖڎ����\�����C�ł������]�����Ɋւ��Ă͕a�ԂƗ��w�Ö@�����т��悤�H�v���C�d���Ⴉ��y�Ǘ�܂Ŗԗ�����D
���w���̎��K�┭�W�w�K�ւ̋��������߂邽�߂ɉ��K�E���K��K�X���荞�ݗՏ��Ƃ̊֘A�Â������߂�D
�@�����̓��F��,���s�㑁�������r�I�����]���Ă����D
�@�܂�, �u�w���ɂƂ��ď�Q�����킩��₷����������e�L�X�g�v��ڎw���������ɂ����ẮC�ȉ��̎��g�݂��s�����D
�@������2�łł͐V���ɋW�X�g���t�B�[�C�������؉��C�d�Njؖ��͏ǁCGuillain-Barre�nj�Q��lj�
�A������3�ł�菑�����w�_�o�؏�Q���w�Ö@�e�L�X�g�x�ƕύX�C���킹�Ď��ʂ����V����4�F��
�B�}�\�̓d�q�f�[�^���ɂ����ƃv���[�������Ƃ��Ă̊��p�x��
�@�����̎��g�݂ɂ��C���Ŋ��s��17�N���o�����������]������C�����̗{���Z�ɂ����ċ��ȏ��Ƃ��Ď��グ�Ă����������ӂɊ����Ȃ��D
�@����ɍ��ł̉����ɂ����ẮC�l����ჁE�Ζ�Ⴢ̗��w�Ö@�Տ�����ɂ�����Ώۏ�Q�ɕs�S�������������߂�Ƃ����Տ�����̎��Ԃ���C�V���ȏ͂�݂��Ă��̕ω��ɑΉ����邱�ƂƂ����D����ɉ����Ċw���ɂƂ��ď�Q�����w�K����ɂ����蓮��͑傢�ɗ����̏����ɂȂ���̂ł��邱�Ƃ���C�{�e�L�X�g�ɂ�����劲�I�ȏ�Q�ł���]���Ǐ�Q���҂ƐҐ��������҂̐������̓�������ڂ���Ƃ������傫�ȉ������������D�{���ƍ��킹�ē�����������邱�Ƃɂ��w���̏�Q���̗������[�܂邱�Ƃ����҂��Ă���D����B�e�ɂ������ẮC�����̐搶���ɑ���Ȃ邲�x�����������������ƂɊ��Ӑ\���グ��D�܂��C�B�e�ɉ������Ή��������������җl�ɂ��S���[�Ӑ\���グ��D
�@�ȏ�̂悤�ȉ����������C��葽���̗{���Z�ł��g������������悤�ȋ��ȏ���ڎw�����D
�@������u�`�����搶����w�����N�ɂ͐���Ƃ����݂̂Ȃ����ӌ��C����]�����������C����Ɂu����w�K���ʂ̍����e�L�X�g�v�ւƏ�����Ă����悤�w�߂����D�����āC�{�����Ŋ��s�����������狤�ɓ��̈�ɂ�����K�C�h���C���̃��f���ƂȂ�ׂ��M���z�����������g��ł����ҏW��,�]���ꐬ�搶��,������4�Ŋ�攼�ɂ����Đ������ꂽ���Ƃ͐��ɒf���̎v���ł���D���̏����Ė������F�肽���D
�@�Ō�ɁC�ҏW�̂���`����������������]���̏����Ɋ��ӂ̈ӂ�\�������D
�ߘa 7 �N 1��
�ҏW���\���ā@�A�����r

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)