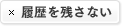NEW�w������8��

| �ҏW | : �c�����q/��������/���{�� |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-23377-9 |
| ���s�N�� | : 2025�N3�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 708 |
��
�艿10,120�~(�{��9,200�~ �{ ��)
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

�w�̃o�C�u���Ƃ��āC���ł���30�N�ȏ�ɂ킽��C��w�E��w���w�����猤���҂܂ő����̓ǎ҂Ɏx�����ꍂ���]���Ă��鋳�ȏ��D���Â̌����̗����ɂ́u���`�B�̍זE�����w�v�̎��_���s���Ƃ̊�{���j�ŕҏW���Ă���D�������ł́C �i�݂��� �����E�a�Ԃ̕��q���J�j�Y���Ƃ���ɑΉ�����R�́CDNA�CRNA�Ȃǂ����_���e�B�[�Ƃ������̗����𑣐i����L�ڂ��[���������D
��T�́@���@�_
�@1�@�w�Ƃ�
�@2�@��̍�p�l���ƍ�p�@��
�@�@��e�̂̊T�O
�@�@�Z�x�Ɩ���
�@�@�A�S�j�X�g�ƃA���^�S�j�X�g
�@�@��̍�p���x���K�肷�鏔���q
�@3�@��̐��̓�����
�@�@��̋z��
�@�@��̐��̓����z
�@�@��̑��
�@�@��̔r��
�@�@�g�����X�|�[�^�[
�@4�@��͂ǂ̂悤�ɂ��đn���邩
�@�@���i�̌����J���̗��j
�@�@�@����̈��i�̌����J���̎n�܂�
�@�@�@�`�����E�y�v�`�h���i
�@�@���i�̌����J���E���F�̃v���Z�X
�@5�@�������
�@�@�j�_���
�@�@�זE���
�@�@�@�זE���i�J��
�@�@�R�̈��
�@�@�@�R�̕��q�̍\���ƍR�̈��̓���
�@�@�@�R�̈��̍�p�@��
�@�@�@�R�̈��̉��NjZ�p
��U�́@���̓����`�B�@�\
�@���̓����`�B�̊T�v
�@�זE����e�̂Ə��`�B
�@�@�C�I���`���l���Ə��`�B
�@�@G�`���������^��e�́iGPCR�j�Ə��`�B
�@�@�y�f�����^��e�̂Ə��`�B
�@�@���ǂ̃V�O�i�����O�i�܂ލזE���̃V�O�i�����O�j
�@�@�]�ʈ��q��e��
�@�]�ʒ��߁F��`�q�̔�������@�\
��V�́@�`���l���ƃg�����X�|�[�^�[
�@1�@�C�I���`���l��
�@�@�J���V�E���C�I��
�@�@�@Ca2�{�V�O�i���ƍזE�@�\
�@�@�@�זE����Ca2�{�`���l��
�@�@�@Ca2�{���o�`���l��
�@�@�J���E���C�I��
�@�@�@K�{�̐����I����
�@�@�@K�{�`���l��
�@�@�i�g���E���C�I��
�@�@�@���̓���Na�{�Ƃ��̖���
�@�@�@Na�{�`���l��
�@�@�N�����C�h�C�I��
�@�@�@���̓���Cl�|�Ƃ��̖���
�@�@�@Cl�|�`���l��
�@�@�A�N�A�|����
�@2�@�C�I���g�����X�|�[�^�[
��W�́@������������
�@1�@�_�o���A�~�m�_
�@�@��-�A�~�m���_�iGABA�j
�@�@�@���̓���GABA
�@�@�@GABA��e��
�@�@�@GABA�̐����I����
�@�@�@GABA�V�i�v�X�ɍ�p�����
�@�@�O���V��
�@�@�������A�~�m�_
�@�@�@�O���^�~���_��e��
�@2�@���������A�~��
�@�@�A�Z�`���R����
�@�@�@���̓��̃A�Z�`���R����
�@�@�@�A�Z�`���R�����̍�p
�@�@�@�A�Z�`���R������e��
�@�@�J�e�R���~��
�@�@�@���̓��̃J�e�R���~��
�@�@�@�J�e�R���~����e�̂ƍזE�����`�B�n
�@�@�Z���g�j��
�@�@�@���̓��̃Z���g�j��
�@�@�@�Z���g�j����e��
�@�@�@�Z���g�j���̍�p
�@�@�@�@�Z���g�j���_�o�n�ɍ�p�����
�@�@�q�X�^�~��
�@�@�@�q�X�^�~����e��
�@�@�@�q�X�^�~���̍�p
�@�@�@�q�X�^�~����e�̝h�R��
�@3�@���������k�N���I�`�h�E�k�N���I�V�h
�@4�@���������y�v�`�h
�@�@�_�o�y�v�`�h
�@�@�@���̓��̐_�o�y�v�`�h
�@�@�I�s�I�C�h�y�v�`�h
�@�@���������E�����̃y�v�`�h
�@�@�@���������y�v�`�h
�@�@�@�����̌�t�y�v�`�h
�@�@�@�����̑O�t�y�v�`�h
�@�@�I���L�V��
�@�@�ېH���߃y�v�`�h
�@�@�@�����ł̐ېH����
�@�@�@��������̐ېH����
�@�@�����ǃy�v�`�h
�@�@�@�X���y�v�`�h
�@�@���Ǎ쓮���y�v�`�h
�@�@�@�i�g���E�����A�y�v�`�h�t�@�~���[�iANP, BNP, CNP�j
�@�@�@�A���M�I�e���V��
�@�@�@�G���h�Z����
�@�@�@�u���W�L�j��
�@5�@���Ǔ���זE�R���o�Ɉ��q�\NO
�@6�@�G�C�R�T�m�C�h�Ƃ��̑��̎������f�B�G�[�^�[
�@�@�G�C�R�T�C�m�h
�@�@�@���̓��̃G�C�R�T�m�C�h
�@�@�@�G�C�R�T�m�C�h��e�̂Ə��`�B
�@�@�@�G�C�R�T�m�C�h�̍�p
�@�@�G���h�J���i�r�m�C�h
�@�@�����������f�B�G�[�^�[
�@7�@PAMPs/DAMPs���R�Ɖu
�@8�@�T�C�g�J�C���ƃP���J�C��
�@�@�T�C�g�J�C��
�@�@�@�@�T�C�g�J�C���֘A��
�@�@�P���J�C��
��X�́@�_�o��
�@1�@�����_�o�̍\���Ƌ@�\
�@�@�����_�o��p��̕���
�@2�@�R������p��
�@�@���X�J������e�̍�p��
�@�@�@�R�����G�X�e���ނƓV�R�A���J���C�h
�@�@�j�R�`����e�̍�p��
�@�@�R�����G�X�e���[�[�j�Q��
�@�@�R�����G�X�e���[�[�ĕ�����
�@3�@�R�R������p��
�@�@���X�J������e�̝h�R��
�@�@�@�x���h���i�A���J���C�h
�@�@�@�x���h���i�A���J���C�h�U���̂���э������X�J������e�̝h�R��
�@�@�j�R�`����e�̝h�R��
�@�@�@�_�o�ߎՒf��
�@�@�@�_�o�ؐڍ����Ւf��
�@�@���i�ؒ��ڒo�ɖ�
�@4�@�A�h���i������p��
�@�@�J�e�R���~��
�@�@��J�e�R���~���E�A�h���i������p��
�@�@�@�Ԑڌ^�A�h���i������p��
�@�@�@�����^�A�h���i������p��
�@�@�@�A�h���i������e�̍�p��
�@5�@�R�A�h���i������p��
�@�@����e�̝h�R��i���Ւf��j
�@�@�@��I��I����e�̝h�R��
�@�@�@�I��I��1��e�̝h�R��
�@�@����e�̝h�R��i���Ւf��j
�@�@�@��I��I����e�̝h�R��
�@�@�@�I��I��1��e�̝h�R��
�@�@������e�̝h�R��i�����Ւf��j
�@6�@�����_�o�̍\���Ƌ@�\
�@�@�_�o����̑��l��
�@7�@�R���_�a��
�@�@��ꐢ��i�]���^�j�R���_�a��
�@�@�@�t�F�m�`�A�W���U����
�@�@�@�u�`���t�F�m���U����
�@�@�@�x���Y�A�~�h�U����
�@�@�@�C�~�m�W�x���W���U����
�@�@�@�`�G�s���U����
�@�@�@�C���h�[���U����
�@�@���i���^�j�R���_�a��
�@8�@�R����E�C�������E���_�h����
�@�@�R����
�@�@�@�O�n�R����
�@�@�@��O�n�R����
�@�@�@�I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��
�@�@�@�Z���g�j���E�m���A�h���i�����Ď�荞�ݑj�Q��
�@�@�@���̑��̍R����
�@�@�C�������
�@�@�@�C�������Ƃ��Ă̍R�z����
�@�@�@�C�������Ƃ��Ă̔��^�R���_�a��
�@�@����������
�@�@�@�o���A�~��
�@�@�@���̑��̐��_�h����
�@�@�@�I��I�m���A�h���i�����Ď�荞�ݑj�Q��
�@�@�@�I��I��2A��e�̃A�S�j�X�g
�@�@�@�L�T���`���U����
�@9�@Parkinson�a����i����K�Y�j
�@�@�@�h�p�~����p��
�@�@�@�h�p�~����e�̍�p��
�@�@�@���m�A�~���I�L�V�_�[�[B�iMAO-B�j�j�Q��
�@�@�@�J�e�R�[��-O-���`���g�����X�t�F���[�[�iCOMT�j�j�Q��
�@�@�@���̑��̃J�e�R���~���n��
�@�@�@�������R�R������p��
�@�@�@�A�f�m�V��A2A��e�̝h�R��
�@�@�t�D�_�o�ϐ��������Ö�
�@10�@�R�F�m�ǖ�C�]�������Ö�
�@�@Alzheimer�^�F�m�ǎ��Ö�
�@�@�@�A�Z�`���R�����G�X�e���[�[�iAChE�j�j�Q��
�@�@�@NMDA�O���^�~���_��e�̝h�R��
�@�@�@�F�m�ǂ̎����C����
�@�@�@�F�m�ǂ̍s���E�S���Ǐ�iBPSD�j�̎��Ö�
�@�@�]��������
�@�@�@�}�����̎��Ö�
�@�@�@�]�[�ǁE�]�o�����ǂ̎��Ö�
�@�@�@�]�G�l���M�[��ӕ�����
�@�@�@�]������̐��_�E�_�o�ǏÖ�
�@11�@�R�s����E����
�@�@�R�s����
�@�@�@�x���]�W�A�[�s���n�R�s����
�@�@�@5-HT1A��e�̍�p��
�@�@�@�I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��
�@�@����
�@�@�@�x���]�W�A�[�s���n����
�@�@�@��x���]�W�A�[�s���n����
�@�@�@�o���r�c�[���_�n����
�@�@�@�����g�j����e�̍�p��
�@�@�@�I���L�V����e�̝h�R��
�@�@�@���̑��̍Ö���
�@�@�@���b���A���R�[����
�@�@�@�f��⏕��
�@�@�@��ʗ}����
�@12�@�R�Ă��E�������ؒo�ɖ�
�@�@�R���
�@�@�@���̑��i�V����R�Ă��j
�@�@�z����
�@�@�������ؒo�ɖ�
�@13�@�S�g������
�@�@�����̖ړI�E���ނƑS�g�����̕K�v����
�@�@�z��������
�@�@��������
�@�@�@�������@
�@14�@�Ǐ�������
�@�@�@�G�X�e���^�Ǐ�������
�@�@�@�A�~�h�^�Ǐ�������
�@15�@���ɖ�
�@�@�@���I�s�I�C�h���ɖ�
�@�@�@�I�s�I�C�h���ɖ�
�@�@�@�I�s�I�C�h��e�̝h�R��
�@�@�@���̑��̃I�s�I�C�h��e�̂ɍ�p���鎡�Ö�
�@�@�@��I�s�I�C�h���ɖ�
�@�@�@�_�o��Q���u�Ɏ��Ö�
�@�@�@���ɕ⏕��
�@16�@�̑ϐ��ƈˑ���
�@�@�ˑ����̎��
�@�@�@�I�s�I�C�h
�@�@�@�����}����
�@�@�@����������
�@�@�@�喃��
�@�@�@���o������
�@�@�@�L�@�n��
�@�@�@�j�R�`��
�@�@�@�։��⏕��
�@�@�t�D�h�[�s���O
��Y�́@�z���
�@1�@�S����p��
�@�@�R�s������
�@�@�@Na�{�`���l���Ւf��
�@�@�@K�{�`���l���Ւf��
�@�@�@Ca2�{�`���l���Ւf��
�@�@�@����e�̝h�R��
�@�@�@���̑��̍R�s������
�@�@�S�s�S����
�@�@�@���j��-�A���M�I�e���V��-�A���h�X�e�����iRAA�j�n�j�Q��
�@�@�@����e�̝h�R��
�@�@�@�O�A�j���_�V�N���[�[-cGMP�n��������
�@�@�@���A��
�@�@�@Na�{/�O���R�[�X���A���́iSGLT2�j�j�Q��
�@�@�@���[����HCN�`���l���Ւf��
�@�@�@���S��
�@�@�@cAMP�������鋭�S��
�@�@�R���S�ǖ�
�@�@�@�L�@�Ɏ_�G�X�e���i�Ɏ_��j
�@�@�@Ca2�{�`���l���Ւf��i�J���V�E���h�R��j
�@�@�@����e�̝h�R��i���Ւf��j
�@�@�@�R������E�R�ÌŖ�
�@2�@���������Ö�т��̑��̌��Ǎ�p��
�@�@����������
�@�@�@���A��
�@�@�@����e�̝h�R��i���Ւf��j
�@�@�@������e�̝h�R��i�����Ւf��j
�@�@�@��1��e�̝h�R��i��1�Ւf��j
�@�@�@����������і����������_�o�}����
�@�@�@Ca2+�`���l���Ւf��i�J���V�E���h�R��j
�@�@�@�A���M�I�e���V���ϊ��y�f�j�Q��
�@�@�@�A���M�I�e���V���U��e�̝h�R��
�@�@�@�G���h�Z������e�̝h�R��
�@�@�@���j���j�Q��
�@�@�@�A���h�X�e������e�̝h�R��
�@�@�ጌ�����Ö�C������
�@�@�@�h�p�~����p��
�@�@�@�A�h���i������p��
�@�@���NJg����
�@�@�t�D���ɖ�
�@3�@���t�E�������p��
�@�@���t�ÌŁE�����`���ƌ���n��
�@�@�~����
�@�@�R�����
�@�@�@�����ÏW�j�Q��i�R������j
�@�@�@���t�Ìőj�~��C�R�ÌŖ�
�@�@�@����n���
�@�@������
�@�@�@�n������
�@�@�@�������q�i������p��j
��Z�́@���A��Ɣ�A��E���B���p��
�@1�@�t���̋@�\�Ɨ��A��
�@�@�t���̋@�\
�@�@���A��
�@�@�@�Z�������A��
�@�@�@�Y�_�E���y�f�j�Q��
�@�@�@�`�A�W�h�n���A��
�@�@�@���[�v���A��
�@�@�@�J���E���ێ������A��
�@�@�@�o�\�v���V����e�̝h�R��
�@2�@��A��E���B���p��
�@�@�r�A��Q����
�@�@�O���B���ǎ��Ö�
�@�@�u�N�s�S����
�@�@�q�{���k��
�@�@�q�{�o�ɖ�
��[�́@���ǁE�Ɖu�E�A�����M�[��
�@1�@���ǂƂ��̐���
�@2�@�q�g�̖Ɖu�E�A�����M�[�����̕a��
�@3�@��X�e���C�h�E�X�e���C�h�R���ǖ�
�@�@��X�e���C�h�R���ǖ�
�@�@�@�V�N���I�L�V�Q�i�[�[�iCOX�j�j�Q��i�_���R���ǖ�j
�@�@�@�@�T���`���_��
�@�@�@�@�A���[���|�_�n�\�C���h�[���|�_�U����
�@�@�@�@�A���[���|�_�n�\�t�F�j���|�_�U����
�@�@�@�@���̑��̃A���[���|�_�n
�@�@�@�@�A���[���v���s�I���_�U����
�@�@�@�@�I�L�V�J���U����
�@�@�@�@�A���g���j���_�U����
�@�@�@�@�I��ICOX-2�j�Q��
�@�@�@����R���ǖ�
�@�@��M���ɖ�
�@�@�@�@��s�����n��M���ɖ�
�@�@�@�@�s�����n��M���ɖ�
�@�@�X�e���C�h�R���ǖ�
�@4�@�Ɖu�E�A�����M�[�������Ö�
�@�@�Ɖu�}����
�@�@�@�@�A���L������
�@�@�@�@�v������ӝh�R��
�@�@�@�@�J���V�j���[�����j�Q��
�@�@�@�@mTOR�j�Q��
�@�@�@�@���̑�
�@�@�@�Ɖu������
�@�@�@�R���E�}�`��
�@�@�@���q�W�I��
�@�@�@�@�����w�I����
�@�@�@�@�ᕪ�q������
�@�@�R�A�����M�[��
�@�@���A�_���ǁE�ɕ����Ö�
�@�@�@�@�A�_�r�����i��
�@�@�@�@�A�_�����j�Q��
�@�@�@�@�ɕ����Ö�
��\�́@�ċz��E�������p��
�@1�@�ċz���p��
�@�@�ċz�h����
�@�@���P��
�@�@��႖�
�@�@�C�ǎx�g����
�@�@�C�ǎx�b�����Ö�
�@2�@�������p��
�@�@�݁i�H���j�ɍ�p�����
�@�@�@�@�ݎ_����}����
�@�@�@�@�݉^�����i��
�@�@�@�@Helicobacter pylori���ۖ�
�@�@�@�@���f��
�@�@���ɍ�p�����
�@�@�@�@���^���}����
�@�@�@�@���b��i�~����j
�@�@�@�@�����lj^�����P��
�@�@�@�@�R�֔��C����
�@�@�@�@���ǐ����������Ö�
�@�@�@�@���ɖ�
�@�@�̑��E�_���E�X���ɍ�p�����
�@�@�@�̑��E�_���������Ö�
�@�@�@�@�̉����Ö�
�@�@�@�@�̍d�ώ��Ö�i�̕s�S���Ö�j
�@�@�@�@���b�̎��Ö�
�@�@�@�X����������
�@�@�@�@�X������
��]�́@���o���p��
�@��Ȗ�
�@���@��A�Ȗ�
�@�畆�Ȗ�
��Ⅺ�́@�z�������E������E��Ӑ��������Ö�
�@1�@�����̃z�������i�{��p���j
�@�@�@�����̃z���������o���i�z������
�@�@�@�����̃z���������o�}���z������
�@�@�@�����̑O�t�z������
�@�@�@�����̌�t�z������
�@2�@�X�e���C�h�z������
�@�@���t�玿�z������
�@�@�@�����R���`�R�C�h
�@�@�@�@�����R���`�R�C�h�֘A��
�@�@�@�@�����R���`�R�C�h�����j�Q��
�@�@�@�z���R���`�R�C�h
�@�@�@�@�z���R���`�R�C�h��e�̝h�R��
�@�@���z������
�@�@�@���E�z�������i�G�X�g���Q���j
�@�@�@�@���E�z�������֘A��
�@�@�@�@�R���E�z�������֘A��
�@�@�@���̃z�������i�v���Q�X�e�����j
�@�@�@�@���̃z�������֘A��
�@�@�@�@�o����D��
�@�@�@�@�I��I�v���Q�X�e������e�̃��W�����[�^�[
�@�@�@�j���z�������i�A���h���Q���j
�@�@�@�@�j���z�������֘A��
�@3�@�b��B�z������
�@�@�@�b��B�z������
�@�@�@�@�b��B�z�������֘A��
�@�@�@�@�R�b��B��
�@4�@���b�זE�R�����q
�@5�@��Ӑ��������Ö�
�@�@����Ӂ\���A�a���Ö�
�@�@�@�@�C���X��������
�@�@�@�@�o�����A�a��
�@�@�@�@�C���N���`���֘A��
�@�@������Ӂ\�����ُ�ǎ��Ö�
�@�@�@������ӂ̃��J�j�Y��
�@�@�@�����ُ�ǎ��Ö�
�@�@����Ӂ\���J���V�E����ӈُ�ǎ��Ö�
�@�@�@���e頏ǎ��Ö�
�@�@�@�@���z���}����
�@�@�@�@���`�����i��
�@�@�@�@���z���}���E���`�����i��
�@�@�@�@���̑�
�@�@�@�J���V�E����ӈُ�ǎ��Ö�
�@�@�@�@���b��B�@�\���i�ǎ��Ö�
�@�@�@�@���b��B�@�\�ቺ�ǎ��Ö�
�@�@�@�@������ᇂɔ������J���V�E�����ǎ��Ö�
��Ⅻ�́@���w�Ö@��
�@1�@�R��������
�@�@�R�ۖ�i�����V�琳�j
�@�@�@�R������
�@�@�@�@��-���N�^���n�R������
�@�@�@�@�A�~�m�O���R�V�h�n�R������
�@�@�@�@�}�N�����C�h�n�R������
�@�@�@�@�����R�T�~�h�n�R������
�@�@�@�@�e�g���T�C�N�����n�R������
�@�@�@�@�y�v�`�h�n�R������
�@�@�@�@�R���j�R������
�@�@�@�@���̌n�ɕ��ނ���Ȃ��R������
�@�@�@�����R�ۖ�
�@�@�@�@�s���h���J���{���_�n�����R�ۖ�
�@�@�@�@�I�L�T�]���W�m���n�����R�ۖ�
�@�@�@�@�T���t�@�܌n�����R�ۖ�
�@�@�@�@�s���W���n�����R�ۖ�
�@�@�@�@�j�g���C�~�_�]�[���n�����R�ۖ�
�@�@�@�@���̌n�ɕ��ނ���Ȃ������R�ۖ�
�@�@�@����̕a���ۂɓK����L����R�ۖ�
�@�@�R�^�ۖ�
�@�@�@�@�R�^�ې��R������
�@�@�@�@�C�~�_�]�[���n�R�^�ۖ�
�@�@�@�@�g���A�]�[���n�R�^�ۖ�
�@�@�@�@���̑��̌n�̍R�^�ۖ�
�@�@�R������
�@�@�R�E�C���X��
�@�@�@�@�P���w���y�X�E�C���X����ѐ����E�я��v�]�E�C���X
�@�@�@�@�T�C�g���K���E�C���X
�@�@�@�@�̉��E�C���X
�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�iHIV�j
�@�@�@�@�C���t���G���U�E�C���X
�@�@�@�@�R���i�E�C���X
�@2�@�R������ᇖ�
�@�@�E�זE���R��ᇖ�
�@�@�@�A���L������
�@�@�@��ӝh�R��
�@�@�@�@�t�_��ӝh�R��
�@�@�@�@�s���~�W����ӝh�R��
�@�@�@�@�v������ӝh�R��
�@�@�@�@���̑��̑�ӝh�R��
�@�@�@�����Ǒj�Q��
�@�@�@�g�|�C�\�����[�[�j�Q��
�@�@�@�R��ᇐ��R������
�@�@������Ö@��
�@�@���q�W�I��
�@�@�@�R�̖�
�@�@�@�����q�W�I��
�@�@�@�@�I��I�`���V���L�i�[�[�j�Q��
�@�@�@�@���̑��̃L�i�[�[�j�Q��
�@�@�@�@mTOR�j�Q��
�@�@�@�@�}���`�L�i�[�[�j�Q��
�@�@�@�@�v���e�A�\�[���j�Q��
�@�@�@�@HDAC�i�q�X�g���E�A�Z�`�����y�f�j�j�Q��
�@�@�@�@PARP�j�Q��
�@�@�@�@CDK4/6�j�Q��
�@�@�@�@�R�̖�����
�@�@�@�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��
��]�V�́@�Տ��w
�@�Տ��w����
�@�Տ����Ԋw
�@�@���ԗ��_
�@�@���Ԃ̎퍷
�@�@�q�g�ɂ��������
�@��`�w
�@���B����јV�l�w
�@���ݍ�p
�@��̓K�p�@�Ə����w�ւ̓���
�@�Ö@�̌l�ʉ��\TDM�Ɩ��^�v
�@�@�l�œK�����
�@�@Therapeutic drug monitoring �iTDM�j
�@�@��̌������Z�x����̓��^���@�̒���
�@�a�Ԏ��ɂ��������
�@��̗L�����ƈ��S��
�@�@�Ő��̔����@��
�@�@�Տ����Ŋw
�@�@��̕���p�Ƃ��̑�
�@�@�W�F�l���b�N���i�ƃo�C�I�V�~���[���i
�a������
��������
�y������8�ł̏��z
�@21 ���I��4 �����I���߂��悤�Ƃ��Ă���D���̊Ԃ̈�w�̐i�W�͖ڊo�܂������̂�����D��́C��w�̋��ɂ̖ړI�ł���q�g�̕a�C�ɂ���Ĉ����N�������\���Ƌ@�\�̕ω��C�a�Ԃ̕��q�I�������i���Ƃł���C������́C���̐i���ɑΉ����āC�a�Ԃ𐧌䂷�郂�_���e�B�[�Ƃ��āC����܂ł̒ᕪ�q���w�����ɉ����C�R�̂Ȃǂ̒`�����CRNA�CDNA �܂��זE���Ȃǂ����X�Ɠo�ꂵ�����Ƃł���DCOVID-19 �ɑ���mRNA ���N�`���̗L�����͂܂��L���ɐV�����D�����̒m�������炩�ɂ������Ƃ́C�����̕a�Ԃ́C���̂��̂̎����̏�ɂ����鐶�̓����`�B�ُ̈�ɂ���Đ����邱�ƁC�̎��Ì��ʂ͂�����������邱�Ƃɂ���ĂȂ���Ă���Ƃ������Ƃł���D����́C�܂��ɁuNEW �w�v�̏��ňȗ��̊�{���j�ł���u�����̖�̕W�I�͎��a�ɂ�艽�炩�ٕ̈ς������������̓����`�B�ł���C���Â̌����̗����ɂ͏��`�B�̍זE�����w�̎��_���s���v�Ɉ�v�C���t������̂ł���D����̉����́C�u�w�́C��Ɛ��̂Ƃ̑��ݍ�p����͂��āC�q�g�̎��Êw�̊�b�ƂȂ�w��ł���v�Ƃ����F���Ɋ�Â��C��L�̐i����傫��������C����܂ł̖w�̑̌n�ƍ��킹����I�Ȏ��_�ƂƂ��ɍ���̈�w�Ƃ��܂��܂ȃ��_���e�B�[�̐i�W�ւ̓W�]�����^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����D
�@��T�͑��_�ɂ����āC��������V���ȍ��ڂƂ��ĉ����C�R�̈��C�j�_���C�זE���̌����C�Z�p�C�������T�������D
�A��U�́@���̓����`�B�@�\�C��V�́@�`���l���ƃg�����X�|�[�^�[�C��W�́@�������������͖{���̓����Ƃ��ׂ������ł���D�e�͂œ��e���A�b�v�f�[�g����ƂƂ��ɁC�I���L�V���CPAMPs/DAMPs ���R�Ɖu��V���ȍ��ڂƂ��ĉ������D
�B���Êw�ɂȂ���e�_�ł́C���q�W�I���Ɖu��p��𒆐S�ɁC��p���C���炩�ɂȂ����a�Ԃ̕��q���J�j�Y���Ɗ֘A�Â��邱�Ƃ�S�������D���̂悤�Ȗ̕��q���x���ł̗Տ��֘A���͍���܂��܂����炩�ɂȂ��Ă������̂Ǝv���C�����̂��тɃA�b�v�f�[�g����\��ł���D
�@�Ҏ҂�́C�{���ɍŐV�̏��荞�ނ��Ƃ�S���������C�ŋ߂̈�w�̔����I�Ȑi�W������X���X�ƐV�K�̈�w�m���C�V�������a�����Ă���D�{���́C�ǎ҂̊F���������t�H���[�ł���w���Ղ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����D����ɂ��ēǎ҂̊F��������݂̂Ȃ��ӌ������������K���ł���D�uNEW �w�v�́C�n���ȗ�35 �N�ԁC���Â̊�b�Ƃ��Ă̖w�ɉ����āC���ʂ��Đ��̂̓�����T������Ȋw�Ƃ��Ă̖w���w�Ԋw���E�����ҁE�Տ���ɂƂ��Ă̕W���I�ȋ��ȏ��Ƃ��Đ������Ă����D�������ꂽ�{�����C����Ƃ����̖������ʂ����Ă������Ƃ��ł���C�Ҏ҂�ɂƂ��đ傫�Ȋ�тł���D
�@�����ɁC�����ɂ����葽�Z�̂Ȃ����M�̘J������Ē��������搶���C����̂��w�͂�����]���̏����ɐS�����\���グ�����D
2024 �N�~
�Ҏ҂�
�y���ł̏��z
�@�����ؔ�Ȃǂ̐A��������p���Ă̎����̎��Â̓M���V����Ñ㒆���̎��ォ��s���Ă������C�w���ߑ�Ȋw�Ƃ��Ēa�����Ă��炢�܂�100 �N���o���Ă��Ȃ��D
�@�w�Ƃ͓K���ȖÖ@�̊�b�ƂȂ�Ȋw�ł���C�܂��V������̊J���̊�b�ƂȂ�Ȋw�ł�����D����C��������̎�i�Ƃ��ėp���邱�Ƃɂ��C���̂̒��ߋ@�\����薾�炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ł���D���������Ėw�͖�Ɛ��̂Ƃ̑��ݍ�p�̌��ʋN���錻�ۂ��������C���̋@�\�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����Ȋw�ł���Ƃ����悤�D����䂦�C�����̑��ݍ�p�q���x���C�זE���x���C�̃��x���Ō������邱�Ƃ��K�v�ł���C���̂��߂ɂ͖�Ɛ��̗̂��ʂ��\���ɗ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D
�@�{���́C�w�����ŐV�̖w�I�v�l��g�ɂ��C�����C���Ȋw�I�ȖÖ@�C�w�I�����̐i�����W�Ɋ�^����菕���ƂȂ�悤�����ꂽ���̂ŁC�]���̋��ȏ��ƈقȂ�C���_�I�ȍ��ڂɑ����̕ł������C���ɖ�̍�p�𗝉����邤���Ŋ�b�ƂȂ鐶�����������ɂ��ďڂ����q�ׂ邱�Ƃɂ����D�܂��C�Տ��ɂ�����Ö@�ɕK�v�ȗՏ��w�̊�{�I�����ɂ��Ă��L�q�����D
�@�X�̖�ɂ��ẮC���݂��܂�g�p����Ă��Ȃ���Ȃǂ͂ł������폜���C�w���Ƃ��Ēm���Ă����˂Ȃ�Ȃ��ŏ����ɂƂǂ߂邱�Ƃɂ����D
�@�����̐}�\�����C��{�I�����̐�����d�v�ȍ�p�@���̗����̏����ƂȂ�悤�z�������D����C���j�I�Ȏ����͈݂͂Ŏ����C�Q�l�ɂȂ鐶���w�C�����w�C��U�w�I������ŐV�̐��I�m���͏������ŋL���C��{�I�����Ƌ�ʂ��Ă���D
�@�Ȃ��C�{���ɂ����ẮZ�Z�܂Ƃ������t��p�����Z�Z��ɓ��ꂵ���D�{���C�u�܁v�Ƃ͐��܂��ꂽ���̂��������̂ł���C���̖{�̂́u��v�ł����āC�w�Ƃ��Ċw�Ԃ��͖̂�ł��邩��ł���D�������C�Տ��Ƃ����^�����́Z�Z�܂ł��邪�C���̂ɓ����p����̂́Z�Z��ł���D
�@�{�����C�䂪���̖w�̋���C�����C�Ö@�̌���ɏ����ł��v���ł���C�ҎҁE�M�҂�̖]�O�̊�тł���D
�@�I���ɁC�{���̍Z���Ɉ���Ȃ�ʂ��s�͂������������c��`�m��w��w���w�������ىf�v�u�t����ѐ_�ˑ�w��w���w���������ɐS��芴�ӂ������D�܂��C�{���̏o�łɑ���̌�w�͂�������������]�������ɐS��肨��\�����������D
1988 �N�H
�Ҏ҂�

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)