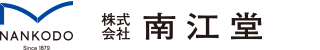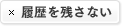日本整形外科学会診療ガイドライン
大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン2021改訂第3版
| 監修 | : 日本整形外科学会/日本骨折治療学会 |
|---|---|
| 編集 | : 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会/大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン策定委員会 |
| ISBN | : 978-4-524-22913-0 |
| 発行年月 | : 2021年3月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 176 |
在庫
定価4,180円(本体3,800円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

高齢者に頻度の高い、大腿骨近位部(頚部および転子部)骨折の基本的知識を網羅し最新の臨床上の疑問に答えるガイドライン。Mindsの指針に沿って全面改訂し、病態から診断・治療、二次骨折の予防など整形外科医のみならず高齢者診療に携わる一般臨床医や理学療法士にも役立つ知識を体系的に解説。また、実地診療に直結したClinical Questionを設け、診断・治療のレベルアップにつながる知識を提供する一冊。
前文
第1章 大腿骨近位部骨折の分類
解説1 大腿骨頚部骨折と転子部骨折
解説2 大腿骨頚部骨折の分類
解説3 大腿骨転子部骨折の分類
解説4 大腿骨転子部骨折のCT分類
第2章 大腿骨頚部/転子部骨折の疫学
解説1 日本における発生数・発生率
解説2 発生率の諸外国との比較
解説3 骨折型別発生率
解説4 発生数の予測
第3章 大腿骨頚部/転子部骨折の危険因子
3.1 骨に関連した危険因子
解説1 骨密度
解説2 骨密度測定部位
解説3 脆弱性骨折の既往
解説4 骨代謝マーカー
解説5 骨代謝マーカー以外の生化学検査
解説6 既往症・疾病・家族歴
解説7 大腿骨の形態
3.2 骨に関連しない危険因子
解説8 転倒
解説9 転倒以外
第4章 大腿骨頚部/転子部骨折の予防
解説1 薬物療法
Clinical Question 1運動療法は転倒・骨折予防に有用か
解説2 ヒッププロテクター
解説3 その他の予防法
第5章 大腿骨頚部/転子部骨折の診断
解説1 画像診断(単純X線写真,CT,MRI)
第6章 大腿骨頚部骨折の治療
6.1 入院から手術までの管理と治療
解説1 早期手術の有用性
解説2 術前MRIによる骨頭壊死予測
6.2 治療の選択
6.2.1 初期治療の選択
解説3 非転位型骨折に対する保存治療
Clinical Question 2転位型大腿骨頚部骨折に対して骨接合術と人工物置換術のどちらを選択するか
Clinical Question 3転位型大腿骨頚部骨折に対し人工骨頭置換術と人工股関節全置換術(THA)のどちらを選択するか
6.2.2 非転位型骨折に対する骨接合術の術式選択と後療法
Clinical Question 4大腿骨頚部骨折の内固定材料としてスクリューとSHS(sliding hip screw)のどちらを選択するか
解説4 荷重制限の必要性
6.2.3 転位型骨折に対する人工物置換術式選択と後療法
Clinical Question 5転位型大腿骨頚部骨折に対してセメント使用と非使用のステムのどちらを選択するか
解説5 Bipolar型とUnipolar型人工骨頭置換術の違い
6.3 骨接合術の合併症
解説6 骨癒合率
解説7 骨頭壊死,late segmental collapseの発生率
解説8 その他の合併症
6.4 内固定材料抜去
解説9 適応
6.5 人工物置換の合併症
解説10 術中合併症の発生率
解説11 脱臼発生率
解説12 その他の術後合併症(感染,インプラント周囲骨折)
6.6 予後
解説13 歩行能力回復に影響する因子
解説14 生命予後と影響する因子
6.7 Occult fracture(不顕性骨折)
解説15 治療
第7章 大腿骨転子部骨折の治療
7.1 入院から手術までの管理と治療
解説1 早期手術の有用性
7.2 外科的治療・保存的治療の適応
解説2 入院期間
7.3 外科的治療の選択
解説3 整復位
Clinical Question 6骨接合にはどのような内固定材料を用いるべきか
Clinical Question 7不安定型転子部骨折の初回手術において骨接合術と人工物置換術のどちらを選択するか
7.4 早期荷重
解説4 早期荷重
7.5 骨接合の合併症
解説5 術中合併症
解説6 ラグスクリュー至適挿入位置
解説7 内固定材料の破損
解説8 偽関節の発生率
解説9 骨頭壊死の発生率
7.6 内固定材料抜去
解説10 適応
7.7 予後
解説11 歩行能力回復に影響する因子
解説12 生命予後に影響する因子
解説13 予後不良因子
7.8 Occult fracture(不顕性骨折)
解説14 治療
第8章 大腿骨頚部/転子部骨折の周術期管理
8.1 術前管理
解説1 疼痛管理
解説2 術前牽引
8.2 麻酔方法
解説3 全身麻酔と区域麻酔(脊椎・硬膜外麻酔)
解説4 抗血小板薬・抗凝固薬投与中の患者の手術時期・麻酔法
8.3 術後管理
解説5 疼痛管理
解説6 酸素投与
解説7 電解質異常とその意義
解説8 輸血の適応
8.4 感染
解説9 手術部位感染(SSI:surgical site infection)の発生率
解説10 抗菌薬の予防投与
8.5 導尿カテーテルと尿路感染率
Clinical Question 8大腿骨頚部/転子部骨折周術期の尿路カテーテル留置は推奨されるか
8.6 術後全身管理
解説11 死亡率と術後全身合併症発生率
Clinical Question 9大腿骨頚部/転子部骨折周術期の栄養状態の改善は有用か
解説12 せん妄の予防と治療
8.7 多職種連携(multidisciplinary approach,orthogeriatric co-management)
Clinical Question 10大腿骨頚部/転子部骨折で入院中の多職種連携診療は有用か
第9章 リハビリテーション医療
Clinical Question 11入院中の多職種連携によるリハビリテーション(multidisciplinary rehabilitation)は推奨されるか
Clinical Question 12急性期施設退院後のリハビリテーション継続は推奨されるか
解説1 地域連携パスの経緯と現状
解説2 多職種によるリハビリテーション医療の意義
第10章 退院後の管理
Clinical Question 13大腿骨頚部/転子部骨折後の二次骨折予防は推奨されるか
Clinical Question 14骨吸収抑制薬の術後早期投与は骨癒合の障害になるか
解説1 骨折リエゾンサービス(FLS)
索引
改訂第3版の序
大腿骨頚部/転子部骨折は、日本では年間約20万例発生している最も一般的な骨折で、今後さらに増加すると推測されています。本骨折は機能障害を生じやすく、生命予後を不良にし、本骨折を起こした患者は次の骨折を起こすリスクが高くなります。
『大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン』は、2005年に初版が発刊され、さらに2011年には第2版が発刊されました。第2版が発刊されてから随分と時間が経ち、その間に高齢者大腿骨頚部/転子部骨折は発生数が増加するとともに、受傷年齢も高齢化しました。現在では多職種による早期治療、周術期管理、二次骨折予防が重要視されるようになっています。
初版では論文の研究デザインをもとに階層化してエビデンスレベルを決定しました。第2版では各Clinical Question(CQ)に関して論文内容を吟味して、そのCQに対してどのような研究デザインで検討されているかに基づいてエビデンスレベルを決定しました。しかしその後、ガイドライン策定手法は世界的に大きく進展しました。診療ガイドラインは、「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマティックレビューとその総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書」と定義されるようになりました。以前のガイドラインで用いられたようなエビデンス単独で評価するのではなく、それに加えて「益と害のバランス」を考量することが重要視されるようになりました。診断、治療、予防などの介入を行った際の有効性とともに、それに伴う有害面も考慮することが求められています。
本改訂第3版ガイドラインは、これに従って策定しました。そのためCQの設定やエビデンスの評価が、前版までとは大きく異なっています。CQは主にメタ解析が可能なものとし、それ以外は「解説」として記載しました。またCQはアウトカムを設定してそれに重みづけをしたのち、メタ解析などのエビデンス評価を統合してエビデンス総体を決定しました。推奨策定にあたっては、介入の有効性と同等に介入がもたらす有害事象にも注意を払い、介入の益と害の差、すなわち“有用性”を重視しなければなりません。患者にとっての不利益としては、害としての患者アウトカムのほかに、費用負担の増加や身体的あるいは精神的な負担なども考慮しました。本ガイドラインが臨床の場で活用され、患者と医療者の意思決定に大いに役立つことを願っています。
本ガイドライン策定にあたっては、策定委員の先生方、システマティックレビューを担当いただいた日本骨折治療学会評議員各位には、忙しい中、多くの時間を割いていただいたことに深謝申し上げます。またガイドライン作成方法論をご担当いただいた国際医療福祉大学、日本医療機能評価機構の吉田雅博先生には、策定作業の各段階で多くの助言をいただいたことに心から感謝申し上げます。
2021年1月
日本整形外科学会
大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン策定委員会
委員長 澤口毅
診療ガイドライン(CPG)は,患者と医療者の協働の意思決定を支援し,根拠に基づく医療(EBM)を実践するための資料である.日本整形外科学会では2005年からCPGの発刊を開始し,今日までに18のCPGが出版済みないしは策定中である.私も変形性股関節症CPGの策定に初版から携わっているが,CPGの考え方は改訂のたびにかわっている.初版作成時は,文献のエビデンスレベルと数が各clinical question(CQ)に対する回答文の推奨度設定における最重要根拠であった.しかしながら今日では,CPGは「健康に関する重要な課題について,エビデンスのシステマティックレビューとその総体評価,益と害のバランスなどを考量して,患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書」と定義されている.つまり,エビデンスレベルの高い研究結果をそのまま重視するのではなく,システマティックレビューならびに可能であればメタ解析を加え,患者意見も入れ,益のみならず害も考慮する.たとえば,大規模無作為化対照試験で有効性が示された治療法でも,合併症はもとより医療コストなどによっても推奨度が下がる.このように,CPGの考え方は時代とともに変化し,さらに当然ながら新たな研究結果も加わることから,CPGの寿命は5年程度といわれている.
大腿骨頚部/転子部骨折CPGが10年ぶりに改訂された.少なからず変更されていることが想像されるが,たとえば第2版ではすべての項目がCQとされ回答文が提示されたのに対し,第3版では主にメタ解析可能な項目がCQとされた.その結果,CQは14のみに絞られ,それ以外の65項目は推奨文の明示されない「解説」とされた.また,CQに対する推奨文には,推奨度(1:推奨,2:提案・条件付き推奨),合意率(70%以上の合意まで再投票),エビデンスの強さ(A「強い」からD「非常に弱い」までの4段階)が付記されるようになった.たとえば,「転位型頚部骨折に対して骨接合術と人工物置換術のどちらを選択するか」というCQに対して,第2版では「人工物置換術を推奨する.ただし,全身状態,年齢を考慮して選択すべきである(Grade A)」とされたが,第3版では推奨文は同じであるものの,「推奨度1,合意率92.3%,エビデンスの強さB」と付記された.すなわち,中程度の確信があるエビデンスをもとに9割方のコンセンサスの得られた推奨とわかる.また,種々のアウトカムに対するメタ解析結果も載せられており,上記推奨が死亡率や合併症率からではなく,主として再手術率から導かれたものであることが理解できる.
推奨文自体が変更されたCQもある.「転位型頚部骨折に対する人工物置換術においてセメント使用と非使用どちらを選択するか」に対し,第2版では「症例に応じていずれを用いても良い(Grade C)」とされていたが,第3版では「骨脆弱性やステム適合不良例に対してはセメント使用を提案する(推奨度2,合意率73.3%,エビデンスの強さB)」とされた.ただしこれは,術中・術後の骨折や弛みをアウトカムとしたメタ解析結果を根拠にしており,死亡や術中出血,脱臼,感染は有意差がない.さらに,肺塞栓症と臨床スコアの点ではむしろセメント非使用のほうが手術時間の短さとともに有利であった.これらは解説文を読んではじめてわかることで,推奨文だけ読んで早合点してはいけない.また,本改訂版でCQとはされなかった多くの項目には解説文しか設けられていない.わかりやすくサマリーを示したほうが親切では,とも思ったが,CQの場合と同様に解説文をしっかり読んで個々の場面に適したEBMを実践するように,という意図と理解すべきであろう.
CQとされなかった事項には,CPGで採り上げるべき重要な課題であったにもかかわらずエビデンスが不十分であったものも含まれる.その課題について質の高い研究を行えば,次のCPGで採択される.すなわち,CPGは単なる診療補助ツールではなく,研究ニーズを示す指針にもなる.患者アウトカムの改善というCPGの目標が,その改訂のたびに達成されることが期待される.
日々の診療や臨床教育に必須であるだけでなく,研究にも有用といえる本書は,大腿骨頚部/転子部骨折にかかわる全整形外科臨床医ならびに研究者に必携の書といえるであろう.
臨床雑誌外科72巻11号(2021年10月号)より転載
評者●神野哲也(獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科主任教授)