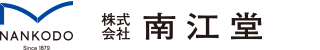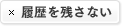慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024
| 監修 | : 日本神経学会 |
|---|---|
| 編集 | : 「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン」作成委員会 |
| ISBN | : 978-4-524-21528-7 |
| 発行年月 | : 2024年6月 |
| 判型 | : B5判 |
| ページ数 | : 192 |
在庫
定価4,620円(本体4,200円 + 税)
正誤表
-
2024年11月20日
第1刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

日本神経学会による慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP),多巣性運動ニューロパチー(MMN)のオフィシャルなガイドラインの改訂版.前版刊行以降に蓄積されたCIDP・MMNの臨床・基礎研究の進歩や最新の国際ガイドラインの内容を盛り込みつつ,日本におけるCIDP・MMNの実臨床に即して策定.臨床上重要となるクリニカルクエスチョン(CQ)について,その回答・推奨グレード,背景・目的,解説をエビデンスに基づいて詳述しているほか,疾患に関する基本的な内容やQ&Aも掲載し,臨床医の日常診療を支援する必携の一冊である.
第1章 CIDPの診療における基本情報
1. 疾患概念
1.1. CIDPとはどのような疾患か
1.2. 類縁疾患(抗MAGニューロパチー,自己免疫性ノドパチー)
2. 疫学
2.1. 疫学(有病率・発症率・好発年齢・性差)
3. 病態
3.1. 病態
4. 診断・評価
4.1. 診断プロセス
4.2. 診断基準(歴史的変遷を含め)
4.3. 臨床病型
4.4. 重症度評価(disability scale,impairment scale)
4.5. QOL評価
5. 検査
5.1. 電気生理学的検査(電気診断基準を含む)
5.2. 脳脊髄液検査
5.3. 画像検査
5.3.1. 超音波検査
5.3.2. MRI
5.4. 神経生検
6. 治療
6.1. 総論
6.2. 副腎皮質ステロイド薬
6.3. 免疫グロブリン療法
6.4. 血漿浄化療法
6.5. 免疫抑制薬など
6.6. リハビリテーション
7. 公的制度,患者会情報
7.1. 公的制度
7.2. 患者会情報
第2章 CIDPの診療におけるCQと推奨
CQ 1 CIDPの診断において,電気生理学的検査は推奨されるか?
CQ 2 CIDPの治療において,副腎皮質ステロイド薬治療は推奨されるか?
CQ 3 CIDPの治療において,免疫グロブリン療法は推奨されるか?(導入・維持療法)
CQ 4 CIDPの治療において,血漿浄化療法は推奨されるか?
CQ 5 CIDPの治療において,免疫抑制療法は推奨されるか?
第3章 CIDPの診療におけるQ&A
1. CIDPの病態に関連するQ&A
Q&A 1.1 CIDPの発症に関連する因子・疾患はあるか?(糖尿病,先行感染を含む)
Q&A 1.2 CIDPの増悪に関連する因子・疾患はあるか?(妊娠,感染症,ワクチン)
2. CIDPの診断におけるQ&A
Q&A 2.1 鑑別診断にはどのようなものがあるか?(臨床病型ごと)
Q&A 2.2 自己抗体を検査する意義はあるか?
Q&A 2.3 単クローン性免疫グロブリン血症を検査する意義はあるか?
Q&A 2.4 遺伝子検査の意義はあるか?
3. CIDPの診療におけるQ&A
3.1. 治療選択肢
Q&A 3.1.1 導入療法として,免疫グロブリン静注療法と副腎皮質ステロイド薬はいずれが有効か?
Q&A 3.1.2 維持療法として,免疫グロブリン療法( 静注,皮下注) と副腎皮質ステロイド薬はいずれが有効か?
Q&A 3.1.3 維持療法として,免疫グロブリン静注療法の用量・間隔をどのように決めるか?
Q&A 3.1.4 維持療法として,免疫グロブリン療法の静注と皮下注のいずれが有効か?
3.2. マネジメント
Q&A 3.2.1 治療効果をどのように判定するか?
Q&A 3.2.2 外科手術および麻酔薬は病勢に影響するか?
Q&A 3.2.3 予後不良因子は何か?
Q&A 3.2.4 高齢患者をどのように治療するか?
Q&A 3.2.5 小児患者をどのように治療するか?
Q&A 3.2.6 挙児希望の患者,妊娠した患者をどうマネジメントするか?
Q&A 3.2.7 疼痛をどう治療するか?
Q&A 3.2.8 ワクチン接種は可能か?
Q&A 3.2.9 長期例のマネジメントで気をつける点は何か?
3.3. 類縁疾患の診断・治療
Q&A 3.3.1 パラプロテイン(M蛋白)陽性のニューロパチーをどのように診断するか?
Q&A 3.3.2 抗MAG 活性を有するIgM 型パラプロテイン陽性のニューロパチーをどのように治療するか?
Q&A 3.3.3 自己免疫性ノドパチー(抗NF155抗体,抗CNTN1抗体,またはランビエ絞輪部・傍絞輪部に対するIgG4自己抗体陽性のニューロパチー)をどのように診断するか?
Q&A 3.3.4 自己免疫性ノドパチー(抗NF155抗体,抗CNTN1抗体,またはランビエ絞輪部・傍絞輪部に対するIgG4自己抗体陽性のニューロパチー)をどのように治療するか?
第4章 フローチャート
4.1. 診断のフローチャート(EAN/PNSガイドライン2021に準じる)
4.2. 治療のフローチャート(EAN/PNSガイドライン2021に準じる)
第5章 MMNの診療における基本情報
1. 疾患概念
1.1. MMNとはどのような疾患か
2. 疫学
2.1. 疫学(有病率・発症率・好発年齢・性差・遺伝的背景)
3. 病態
3.1. 病態
4. 診断・評価
4.1. 診断プロセス
4.2. 診断基準
4.3. 重症度評価
5. 検査
5.1. 電気生理学的検査(電気診断基準を含む)
5.2. 抗ガングリオシド抗体検査
5.3. 脳脊髄液検査
5.4. 画像検査
6. 治療
6.1. 免疫グロブリン療法
6.2. リハビリテーション
6.3. 免疫抑制薬
第6章 MMN の診療におけるCQと推奨
CQ 1 MMNの診断において,電気生理学的検査は推奨されるか?
CQ 2 MMNの治療において,免疫グロブリン療法は推奨されるか?(皮下注,維持を含む)
CQ 3 MMNの治療において,免疫抑制療法は推奨されるか?
第7章 MMNの診療におけるQ&A
Q&A 1 MMNの発症や増悪に関連する因子・疾患はあるか?(薬剤,先行感染,ワクチン,悪性腫瘍)
Q&A 2 鑑別診断にはどのようなものがあるか?
Q&A 3 難治例をどのように治療するか?
Q&A 4 補助的な治療にはどのようなものがあるか?
Q&A 5 治療効果をどのように判定するか?
Q&A 6 治療の継続・中止をどのように判断するか?
Q&A 7 挙児希望の患者,妊娠した患者をどうマネジメントするか?
Q&A 8 ワクチン接種は可能か?
Q&A 9 長期例のマネジメントで気をつける点は何か?
索引
日本神経学会を中心として関連学会( 日本神経治療学会,日本神経免疫学会,日本末梢神経学会) と厚生労働省研究班( 神経免疫班) の協力のもとに本邦における慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー( chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy:CIDP) ・多巣性運動ニューロパチー( multifocal motor neuropathy:MMN) の診療ガイドラインは2013年に初版が出版され,広く利用されてきた.以後の診断・治療法の進歩を受けて,今回,2024 年に改訂版( 第2版) CIDP・MMN診療ガイドラインが発刊・公表の運びとなった.一方,国際的なCIDP・MMN 診療ガイドラインは2005 年にEFNS/PNS (European Federation of NeurologicalSocieties/Peripheral Nerve Society) により策定され,以後2010 年,2021 年に改訂版が公表されている( 2021年改訂版はEFNSがEAN[European Academy of Neurology]と改称されたためにEAN/PNS ガイドラインと称されている).本ガイドラインと国際ガイドラインの基本的骨格は同様であるが,欧米各国と日本における医療体制,承認薬,保険医療制度,行政制度( 指定難病制度) などには異なる面があり,これらを踏まえて本邦におけるCIDP・MMN の実臨床に即して策定されたものが本ガイドラインである.
CIDP・MMN は代表的な免疫介在性ニューロパチーであるが,末梢神経疾患の診療に関しては各脳神経内科医あるいは施設によって経験・専門性にやや差があることも現実である.本ガイドラインは脳神経内科医全般に対して,実臨床を行ううえで参考となり,ひいては患者の利益に貢献するべく作成されている.CIDP・MMN は適正な治療により確実に症状改善が認められ,しばしば劇的な回復がみられる疾患であり,また寛解維持療法の導入により長期予後も改善している.したがって,CIDP・MMN が見逃されて治療の機会が失われることがあってはならない.一方,原因が特定できないニューロパチーに対して特にCIDP はoverdiagnosis されることもしばしば起こりうるため正確な診断が必要となる.本ガイドラインの作成にあたっては,診断・治療からリハビリテーション,ワクチン接種,手術,妊娠・出産なども含めて最新の知見に基づいた至適診療を促進し,臨床現場で予想される疑問にわかりやすく答えられるよう心がけた.
近年の診療ガイドラインはGRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development,and Evaluation) システムに基づいて作成されていることから,本ガイドラインではCIDPに対して5項目,MMNに対して3項目の診断・治療に関するClinical Question( CQ) を設定し,それぞれGRADE に基づくシステマティックレビューを行い,エビデンスレベルと推奨度について作成委員によるパネル会議での討議により設定した.また,近年のガイドラインにおいて推奨されている患者の価値観・嗜好を取り入れるために,日本神経学会監修のガイドラインとしてははじめて患者会( 全国CIDPサポートグループ) から作成委員としての参加をいただいた.
本ガイドラインの作成にかかわる経費は日本神経学会が負担した.また,作成にかかわる委員長以下各委員からはCOI 申告書の提出および日本神経学会による承認を得た.膨大な時間を費やしてガイドライン作成にかかわった作成委員,研究協力者,評価・調整委員の方々に深謝したい.本ガイドラインが広く臨床現場における診療の参考になることを期待するとともに,刻々と進歩を続ける医療技術・新規治療に対応して定期的なガイドラインの改訂も継続していく必要性も感じている.
2024 年5 月
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会 委員長
桑原 聡
難しい病気の,しかし役に立つガイドライン
本書は,「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー,多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2013」の改訂版である.旧版の刊行から約11年が経過したが,この間,国際的に汎用されているEAN/PNSガイドラインが2021年に改訂され,Ranvier絞輪近傍蛋白に対するIgG4自己抗体を有する症例がノドパチーとして慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)の概念から外れ,維持療法としての免役グロブリン皮下注療法(SCIg)がほぼ確立するなどの変化があった.本改訂版の内容はEAN/PNSガイドラインの内容から大きく外れるところはないが,本ガイドライン作成委員会委員長の桑原聡先生が「序」に書かれているように,欧米とは医療体制,承認薬,保健医療制度,指定難病制度などに関して異なるところが多数あり,それを踏まえて本邦での診療にしっかりと配慮した記載が貫かれている.また,今回の診療指針は欧米の診療指針と異なり,CIDP,多巣性運動ニューロパチー(MMN)の疾患概念について,その確立の歴史から記載している.これらの疾患になじみの少ない読者にとっては非常に有意義なことと理解できる.
評者は初版で委員としてCIDP治療の項を担当したが,この約11年の間で「Minds診療ガイドライン作成の手引き」が改訂を重ねて進化・複雑化していったなかで,本改訂版の委員の先生方やシステマティックレビューに協力された先生方は,採用すべき論文の選定とランクづけ,過不足のない推奨文の作成などで大変な苦労をされたと思う.本ガイドラインの作成時期はCOVID—19のパンデミックの真っ直中であり,対面での綿密なディスカッションもままならなかったことと想像する.「完成ご苦労様」と労い,心からお祝いを申し上げたい.あえてここで一言付け加えるとすれば,医療経済の面からの記載が乏しいことであるが,この記載の充実は次回の改訂に期待したいと思う.
さて,読者の皆様には作成担当者の苦労とは関係なく,本書をフルに活用していただきたいと念願する.希少疾患であることを反映して,Clinical Question(CQ)はCIDPが五つ,MMNが三つに限定されている.この八つのCQに関しては綿密な文献レビューと合議によるランクづけがなされて本来のガイドラインとしての体裁が整っており,作成者が最も時間を費やした部分であると思う.しかし,本書の一番の美点はここではなく,そのほかの項目のナラティヴな記載である.過不足のない大変丁寧な記述が続いており,明日の実臨床への応用に十分な内容となっている.とは言っても,CIDP,MMNともに,治療介入可能な神経疾患のなかでは,飛び抜けて診断・治療が難しい疾患であると評者は考えている.この二つの疾患に対して苦手意識をもっておられる,あるいはあまり診たことがない脳神経内科の先生方にも十分役に立つ内容のガイドラインを世に出してくれた執筆者の先生方には多大なる感謝を申し上げたいが,本書にはもう一つ重要な情報がある.それは作成委員,協力者のリストである.診断・治療に困られたら,ぜひ,ここに書かれた先生方に直接相談されることをお勧めする.きっと懇切丁寧な回答が返ってくると信じてやまない.
臨床雑誌内科135巻2号(2025年2月号)より転載
評者●神田 隆(脳神経筋センターよしみず病院 院長,山口大学 名誉教授)