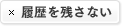�Ɖu���_�o�����n���h�u�b�N������2��
| �ҏW | : ��i/�C�c���� |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-21176-0 |
| ���s�N�� | : 2025�N5�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 384 |
��
�艿12,100�~(�{��11,000�~ �{ ��)
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

�������d���ǁCGuillain-Barré�nj�Q���͂��߂Ƃ����Ɖu���_�o�����Ɋւ���ŐV�̗Տ����тƌ������ʂ��C���l�҂������ڂ�������D���L�������̉u�w�C�a���E�a�ԁC�_�o�w�I�����C�f�f�C���Â�ԗ��D�����ł͂��̊Ԃɉ𖾂��ꂽ�a�Ԃ�V��Ȃǂ̐V�m�����݁C�K�C�h���C���̉����ɂ��Ή��D���H�ɑ��𗧂G�b�Z���X���ڂŁC�K�ǂ̈���D
��T�́@���@�_
�@�` �Ɖu���_�o�����ƍזE���Ɖu
�@�@1�D�_�o�Ɖu�w�̔��W
�@�@2�D�זE���Ɖu�̊�b
�@�@3�D�_�o�Ɖu�w -��b����ŋ߂̓����܂�
�@�a �Ɖu���_�o�����Ɖt���Ɖu
�@�@1�D�Ɖu���_�o�����Ɖt���Ɖu�̊ւ��
�@�b ���t�]�֖�iBBB�j�ƌ��t�_�o�֖�iBNB�j
�@�@1�D�\���Ƌ@�\
�@�@2�D�Ɖu���_�o�����ƃo���A�̌����E�Տ����p
�@�c �Ɖu���_�o�����Ɗ��זE�iiPS �זE�̊��p���܂ށj
�@�@1�D�_�o���ǂƊ��זE
�@�@2�D�_�o�Ɖu������iPSCs ����
�@�d �Ɖu���_�o�����ƒ��ǖƉu
�@�@1�D�����ۂ��_�o���ǂ𐧌䂷�郁�J�j�Y��
�@�@2�D�����ۑp�����̗Տ����p
�@�e �Ɖu���_�o�����̓������f��
�@�@1�D�������d���ǁ^���_�o�Ґ����X�y�N�g������Q
�@�@2�D���ȖƉu�������_�o���iGuillain-Barre�nj�Q�C�������ǐ��E�����������j���[���p�`�[�j
�@�@3�D�d�Njؖ��͏�
�@�@4�D���ǐ��~�I�p�`�[
�@�f �Ɖu���_�o�����̃o�C�I�}�[�J�[
�@�@1�D���t�o�C�I�}�[�J�[
�@�@2�D�������o�C�I�}�[�J�[
�@�g �Ɖu���_�o�������ÊT�_�i�X�e���C�h�C�Ɖu�}����C���q�W�I��j
�@�@1�D�}��������
�@�@2�D����������
�@�@3�D���q�W�I�Ö@
�@�@4�D�����ǂ̍Ċ�����
�@�@5�D�����ƃ��C�t�C�x���g
�@�@6�D����̉ۑ�
��U�́@�Ɖu�������_�o����
�@�` �������d���ǁiMS�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�a ���_�o�Ґ����X�y�N�g������Q�iNMOSD�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D���@��
�@�b MOG �R�̊֘A�����iMOGAD�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a�ԂƔ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�c �}���U�ݐ��]�Ґ����iADEM�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���ƕa��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�d ���ȖƉu��ݐ��]���E�]�ǁiAE�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I�����i�����������܂ށj
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D�f�@�f
�@�@5�D���ÂƗ\��
�@�e �Ɖu�������_�o�����̊ӕʐf�f
�@�@1�D�Տ��o�߂�Ǐ�̊ӕ�
�@�@2�D�����̐i�ߕ�
�@�@3�D�ӕʂ�v�����Ɖu������
�@�@4�D���ۂ̐f�Âɂ�����ӕ�
��V�́@�Ɖu�������_�o����
�@�` Guillain-Barre �nj�Q�iGBS�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�@7�D����̓W�]
�@�a Miller Fisher �nj�Q�Ɗ֘A�����iBickerstaff �]���]�����܂ށj
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a�ԂƔ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�b �������ǐ��E�����������j���[���p�`�[�iCIDP�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a�ԂƔ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�c �������^���j���[���p�`�[�iMMN�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���ƕa��
�@�@4�D�f�f�Ɗӕʐf�f
�@�@5�D���ÂƗ\��
�@�d IgM �p���v���e�C�����ǂ��j���[���p�`�[�i�RMAG �j���[���p�`�[���܂ށj
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�e ���ȖƉu���m�h�p�`�[�iAN�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a�ԂƔ����@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�f �N���E�E�[���iPOEMS�j�nj�Q
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I�E���ȓI����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
��W�́@�Ɖu���؎���
�@�` �d�Njؖ��͏ǁiMG�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a�ԂƔ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�a Lambert-Eaton �ؖ��͏nj�Q�iLEMS�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�b ���ǐ��~�I�p�`�[
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D�摜����
�@�@5�D��������
�@�@6�D�f�@�f
�@�@7�D���ÂƗ\��
��X�́@���̑��̖Ɖu���_�o����
�@�` �_�oBehcet�a�Ɛ_�oSweet
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D�摜����
�@�@5�D��������
�@�@6�D�f�@�f
�@�@7�D���ÂƗ\��
�@�a �P���a�ɔ����_�o��Q�i���lj��nj�Q���܂ށj
�@�@1�D�P���a�Ɛ_�o��Q
�@�@2�D���lj��nj�Q
�@�@3�DSjogren�nj�Q
�@�@4�DIgG4 �֘A����
�@�b ���{�]��
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�c �T��ᇐ��_�o�nj�Q�iPNS�j
�@�@1�D�Տ��u�w
�@�@2�D���ȍR��
�@�@3�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@4�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�d Isaacs �nj�Q��Morvan �nj�Q
�@�@1�D�Տ���w
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�e stiff-person �nj�Q�iSPS�j
�@�@1�D�Տ��u�w�ƕa�^
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
�@�f ���ȖƉu�������_�o�ߏ�Q�iAAG�j
�@�@1�D�Տ��u�w�ƕa�^
�@�@2�D�Ǐ�Ɛ_�o�w�I����
�@�@3�D�a���Ɣ��Nj@��
�@�@4�D��������
�@�@5�D�f�@�f
�@�@6�D���ÂƗ\��
��Y�́@�_�o�ϐ������C�]���Ǐ�Q�ɂ�����Ɖu�̊ւ��
�@�` �_�o�ϐ������ƖƉu
�@�@1�D�_�o�ϐ������ɂ�����O���A�זE�̊������Ɛ_�o����
�@�@2�D�u��זE�������_�o�זE���v�Ƃ����V���ȕa�Ԃ̊T�O
�@�@3�D�_�o���ǂɂ�����~�N���O���A�̕��q�a��
�@�@4�D�_�o���ǂɂ�����A�X�g���T�C�g�̕��q�a��
�@�@5�D�_�o�ϐ������ɂ�����l���Ɖu�̖���
�@�@6�D�_�o�ϐ������ɂ����鎩�R�Ɖu�����̖���
�@�a �]���Ǐ�Q�ƖƉu
�@�@1�D�]�[�Nj}�����Ǝ��R�Ɖu
�@�@2�D�]�[�ǖ������Ǝ��R�Ɖu
��Z�́@�g�s�b�N�X
�@�` ���ȖƉu���^�T��ᇐ����]�����ǂɊ֘A����V���Ȏ��ȍR��
�@�@1�Dmetabotropic glutamate receptor�imGluR�j2�R��
�@�@2�Dglutamate kainate receptor subunit�iGluK�j2�R��
�@�@3�Dseizure-related 6 homolog like 2�iSez6l2�j�R��
�@�@4�DNeurochondrin�R��
�@�@5�Dadaptor protein-3B2�iAP3B2�j�R��
�@�@6�DSeptin5 �R��
�@�@7�Dregulatory of G-protein signaling�iRSG�j8�R��
�@�@8�DHomer3�R��
�@�a �RPlexin D1�R�̂Ɛ_�o��Q
�@�@1�D���ȍR�̉�ݐ��_�o��Q���u��
�@�@2�D�RPlexin D1 �R��
�@�Ɖu���_�o�����́C�]�_�o���Ȃ̎���͈͂ł����]�E���]�E�]���E�Ґ��E�����_�o�E�_�o�ؐڍ����E�ɂ�����C�Ɖu�w�I�@���ɂ������N������鎾���ł���D�]�_�o���Ȃ̎����ɂ͂��������������������C�Ɖu���_�o�����͖Ɖu�@�����R���g���[�����鎡�Âɂ���ĖڂɌ�������ʂ���������̂������C�_�o���Ȑ���ɂƂ��Ęr�̌����ǂ���ƂȂ�̈�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��낤�D
�@���̂悤�ȖƉu���_�o�����̍Ő�[�̒m�����C�킩��₷���Љ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āC2013�N�ɖƉu���_�o�����n���h�u�b�N�����s���ꂽ�D���ꂩ��10�N�]�肪�o�߂������C���̊Ԃ̂��̕���̌����̐i���͖ڊo�܂������̂�����C����f�Âɂ����Ă����q�W�I��Ȃǂ̑����̐V�K��܂���������Ă����D�܂���\�I�ȖƉu���_�o�����ł��鑽�����d���ǁCGuillain-Barré�nj�Q�C�������ǐ��E�����������j���[���p�`�[�iCIDP�j�C�d�Njؖ��͏ǂȂǂɂ��āC�K�C�h���C���̉������s��ꂽ�D���������w�i���ӂ܂��āC����Ɖu���_�o�����n���h�u�b�N�̑�2�ł����s����邱�ƂƂȂ����D
�@�S�̂̍\���͏��łƓ��l�ɁC���_�Ƃ���ɑ����e�_�Ƃ������ԂƂ��āC���_�ł͍ŋ߂̘b��ł���L���S��������Ă��銲�זE�⒰�ǖƉu��V���ȍ��ڂƂ��Ď��グ���D�e�_�ł͒����_�o�����ɂ����āC �V���������T�O�ł���myelin oligodendrocyteglycoprotein�iMOG�j�R�̊֘A�����iMOGAD�j���������D�����_�o�����ł́C�]����CIDP�̒��Ɋ܂܂�Ă����T�i�֕��`���ɑ���R�̗z���̃j���[���p�`�[���C���ȖƉu���m�h�p�`�[�Ƃ��ĐV����1 �̍��ڂƂ����D�܂��̖Ɖu�������ɂ��ď��łł͑����؉��E�畆�؉��E�����̋؉��Ƃ��Ă������C���ǐ��~�I�p�`�[�Ƃ��Ă܂Ƃ߂ċߔN�̐V�����l�������Љ�Ă����������D����ɂ�����Ɖu�������ɂ͕��ނ���Ȃ��_�o�ϐ�������]���Ǐ�Q�̖Ɖu�Ƃ̊֘A�ɂ��ẮC���łƓ��l�ɍŋ߂̐i�����L�ڂ����������ƂƂ����D
�@�Ɖu���_�o�����ɂ��ẮC��L�̂悤�ɂ��܂��܂ȐV�K���Â���������C����ɍ��������ɂނ��Ă̎�����Տ��������s���Ă���D�܂����̊�ՂƂȂ��b�������傫���i�����Ă���D���̂悤�ȖƉu���_�o�������Ƃ�܂����N���N�����C�{����ʂ��Ė�����Ă���������ƍl���Ă���D
�@�Ō�ɉ�����2�ł̊��s�ɂ������āC�f���炵�����e���Ă��������������̐搶���C����ё�ςȂ��s�͂�������������]���ҏW���̕��X�ɁC�����ʼn��߂Č���\���グ�����D
2025�N5��
��@�@�i�C�C�c����

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)