杏林大学ICIBD直伝! IBD腸管エコーマニュアル[Web動画付]
| 編集 | : 久松理一/三好潤 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-20703-9 |
| 発行年月 | : 2024年5月 |
| 判型 | : B5判 |
| ページ数 | : 172 |
在庫
定価7,480円(本体6,800円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

IBDの病勢・治療効果モニタリングを行う上で近年有用性が再評価されている腸管超音波検査(腸管エコー)について,前処置・事前準備といった検査の実際や基本操作手順など機器の扱い⽅を簡潔に解説した入門書.潰瘍性⼤腸炎やクローン病の代表的な画像・動画を豊富に掲載したほか,評価・スコアリングについても解説.さらに豊富な症例も提⽰している.IBD腸管エコーを⽇常臨床に導⼊するために必携の⼀冊.
第1章 炎症性腸疾患における腸管エコー
1 炎症性腸疾患診療において腸管エコーが注目される理由
A IBDのマネジメント─T2T strategyにおける内視鏡検査の位置付け
B 疾患活動性モニタリングツールとしてのIUSの利点と弱点
C IBD-IUSの課題と展望
2 超音波検査の概要
A 超音波検査の基礎
B 超音波診断装置
C 超音波ビームの走査方式
D 超音波画像の表示法
E Bモード画像の調節法
F ドプラ法
G 消化管の超音波検査で知っておきたいアーチファクト
第2章 検査の実施
1 検査を始める前に
A 超音波診断装置の設定
2 検査の実際
A 前処置・検査準備など
B 基本の操作手順
C 正常例
D 潰瘍性大腸炎(UC)の代表的画像
E クローン病(CD)の代表的画像(腸管合併症を含む)
F 経会陰超音波検査の代表的画像(腸管合併症を含む)
第3章 炎症性腸疾患の評価
1 炎症性腸疾患腸管エコーにおける評価項目
A IBD-IUSにおける主要な評価項目
B IBD-IUSにおける主要な評価項目の信頼性
C その他のIBD-IUS評価項目
D IBD-IUSレポートの書き方
2 炎症性腸疾患腸管エコーで提唱されているスコアリングシステム
A 潰瘍性大腸炎(UC)
B クローン病(CD)
第4章 症例提示
1 潰瘍性大腸炎(UC)
症例1 抗TNFα抗体製剤による加療を行ったUC全大腸炎型
症例2 抗α4β7インテグリン抗体製剤が無効であり抗IL-12/23p40抗体製剤に治療を変更したUC左側大腸炎型
症例3 過敏性腸症候群の併存と再燃の鑑別に内視鏡検査を行わずにIUSを用いたUC全大腸炎型
症例4 ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬の中での薬剤変更が有効であったと考えられたUC左側大腸炎型
症例5 IUSによる繰り返しの病勢評価が実施できている小児UC全大腸炎型
症例6 抗TNFα抗体製剤を導入中に肛門周囲膿瘍を併発したUC全大腸炎型
症例7 内科的治療に抵抗性で外科的手術が検討されたUC全大腸炎型
症例8 病勢評価としてIUSを実施したUC合併妊娠
症例9 服薬アドヒアランス不良による増悪に対して抗α4β7インテグリン抗体製剤を導入したUC全大腸炎型
症例10 抗TNFα抗体製剤が無効かつ穿孔リスクが高いとIUS所見から判断した重症UC全大腸炎型
2 クローン病(CD)
症例1 内視鏡的バルーン拡張術を繰り返す小腸大腸型CD
症例2 小腸狭窄に伴う腸閉塞を繰り返す小腸大腸型CD
症例3 肛門周囲膿瘍の評価にIUSが有用であった大腸型CD
症例4 肥満体型であったが経腹・経会陰IUSで病勢を評価しえた大腸型CD
症例5 大腸狭窄により内視鏡的活動性の評価が不可能であり,疾患活動性評価にIUSが有用であった小腸大腸型CD
症例6 IUSでパテンシーカプセル滞留と崩壊を確認しえた小腸型CD
症例7 IUSを用いて治療効果判定を行った小腸型CD
症例8 IUSで小腸病変を指摘され,診断にいたった小腸大腸型CD
症例9 IUSの併用で妊娠中にも疾患活動性を評価しえた小腸大腸型CD
症例10 回腸多発病変を呈する小腸型CD
このたび『杏林大学ICIBD直伝!IBD腸管エコーマニュアル』が発刊されたことを非常に嬉しく思います.
炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:IBD)は主にクローン病と潰瘍性大腸炎からなり,両疾患ともに原因不明の難治性炎症性腸疾患で厚生労働省の難病に指定されています.現在,わが国の患者数は右肩上がりに増加しており,クローン病7万人超,潰瘍性大腸炎22万人と推定されています.IBDは20〜30歳代に多く発症し慢性の経過をたどるため,就学,就労,結婚,妊娠,出産とさまざまなライフイベントに影響します.
杏林大学医学部付属病院に通院するIBD患者数は,約250人(2015年4月)から約1,350人(2024年2月)に急増しています.この間,国際共同治験や多施設共同研究にも積極的に参加し,当院は東京西部の拠点となりました.IBDは慢性疾患であり,チーム医療やshared decision makingといった診療コンセプトやストラテジーが薬剤選択と同じくらい患者の予後に影響します.これらを背景に,2019年に念願の杏林大学医学部付属病院炎症性腸疾患包括医療センター(Interdisciplinary Center for
Inflammatory Bowel Disease:ICIBD)を設立しました.消化器内科医,外科医,産科医,小児科医,看護師,栄養士,薬剤師が協力しながらチーム全体で包括的に(Interdisciplinary)患者中心の医療を提供することを理想としています.
IBD診療における腸管エコーの有用性は,なんといっても低侵襲でいつでも気軽に施行できることで,まさにtreat to target strategyにはうってつけのモダリティです.腸管エコーは薬剤の短期的な有効性を評価する客観的指標として非常に有望であり,クリニックでも行えるため,実地医家の先生方にも最適だと思います.全層性の炎症や腸管蠕動を評価することができるので,内視鏡とは違った病態が見えてくるかもしれません.そして何より実感しているのが,若手医師の育成にこれほど適した検査はない,という点です.センターの重要な役割の一つが人材の育成であり,ICIBDの目標は全人的なIBD診療が可能なエキスパートを育成することですが,そのためには外来や病棟で多くの診療経験を積むことが必要です.腸管エコーを施行するということは,まさに患者さんと話をしながら腹部診察をすることなので,コミュニケーション能力を磨くこともできます.
今後わが国のIBD診療に腸管エコーが本当に定着するかどうかの最大の難関は“一般化”にあると感じています.「これから入門する人たち向けにポケットマニュアル的なものがあれば便利だろうなぁ」という雑談で始まったのが本企画です.中心となった三好潤准教授や技師の米澤広美氏をはじめとする腸管エコーグループメンバーに大変感謝しています.また,腸管エコーを診療に導入するにあたり,超音波診断学の基本からご指導いただいた森秀明教授に深謝いたします.本書の執筆者の若手医師たちも,もともとはゼロからのスタートでしたので,第4章の症例検討のところを読むと感慨深いものがあります.初学者の視点をよく理解した内容になっていると思います.そして最後に,消化器内視鏡とは違い“IBD診療における腸管エコー”というニッチなこの企画を快諾し,出版まで支えてくれた南江堂にも心からお礼を述べたいと思います.
とにかくベッドサイドで使ってほしいと思います.本書がきっかけとなりIBD腸管エコーがますます盛り上がってくれればこの上ない喜びです.
2024年2月吉日
編者を代表して
久松 理一
未来のIBD治療に向けた最先端の道標:腸管エコーがT2T戦略を支える
超音波検査(エコー検査)は,非侵襲的・安全で,臓器の動きや構造をリアルタイムで観察できるという大きな利点を有する.腸管エコーは,病変の描出や評価が術者の技量と患者の条件(体型やガスの存在など)に影響されるという弱点をもちながらも,その手軽さとリアルタイムでの観察が可能なことから,消化管領域における重要な検査法として注目されている.とくに炎症性腸疾患(IBD)領域では,腸管エコーを活用した疾患活動性のモニタリングが広まっている.
このたび,杏林大学消化器内科のグループが先駆的に取り組んでこられたIBD領域における腸管エコーについて,その基本から描出のコツまでをまとめた『杏林大学ICIBD直伝!IBD腸管エコーマニュアル』が出版された.その特徴としては,リアルタイムでの描出のコツや病変の画像をWeb動画で実際に経験できることがあげられる.これは,腸管エコーにこれから取り組もうとする医師にとって非常に有用なリソースであり,IBD診療における腸管エコーの普及とtreat to target(T2T)戦略の実践に貢献することが期待される.
IBDの病態に関わるさまざまな免疫異常(サイトカインの発現異常など)が明らかになり,数多くの分子標的治療薬が開発されて臨床の現場に導入されている.これらの治療法はIBDの予後や自然史に大きな変化をもたらし,T2Tという治療戦略が取り入れられている.T2Tは治療目標(target)を設定し,計画的なモニタリング結果に基づいて適宜治療を強化・緩和する治療戦略である.治療目標としては,短期的には臨床的寛解,中期的にはバイオマーカー的寛解,長期的には内視鏡的寛解が提言された.IBD治療薬の効果判定や疾患活動性モニタリングのゴールドスタンダードが内視鏡検査であることは間違いない.IBD寛解導入時の治療効果は内視鏡によって判定することが基本で,臨床的寛解を維持している患者でも,内視鏡的な活動性病変が残存していることも経験される.ただ,内視鏡検査は前処置を含めて侵襲性が問題となるため,頻回に施行できないのが現状である.その点において,腸管エコーは手軽に施行でき,リアルタイムで病変を観察できるcross—sectional imagingとして,T2Tの実践において非常に重要になってくると思う.本書の登場により,これからのIBD診療に腸管エコーが広く取り入れられ,多くの施設でT2Tの実践に貢献することを期待している.
臨床雑誌内科134巻6号(2024年12月号)より転載
評者│安藤 朗(滋賀医科大学 名誉教授)

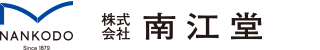

![杏林大学ICIBD直伝! IBD腸管エコーマニュアル[Web動画付]](https://d1gwi3e1mfwx7l.cloudfront.net/img/goods/L/9784524207039.jpg)
