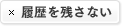���N�E�h�{�Ȋw�V���[�Y
�Տ��h�{�w������4��

| �ďC | : ���������J���@�l ����ՁE���N�E�h�{������ |
|---|---|
| �ҏW | : ��������/�쓇�R�N�q/�O�R����/�Ћˋ`�� |
| ISBN | : 978-4-524-20419-9 |
| ���s�N�� | : 2025�N3�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 484 |
��
�艿4,400�~(�{��4,000�~ �{ ��)
����\
-
2025�N10��10��
��1��
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

��v�Ȏ����̕a�ԂƁC���҂ɑ���K�ȉh�{�A�Z�X�����g�E�h�{�P�A�ɂ��ďڍׂɉ�������e�L�X�g�D���_�ʼnh�{�}�l�W�����g�̗���C�H���Ö@�E�h�{�⋋�@�̊�b�C��Ƃ̑��ݍ�p�Ȃǂ𑍍��I�ɗ������C�e�_�Ŋe�����̉h�{�}�l�W�����g�̎��ۂW�I�Ɋw�ׂ�悤�\���D�u�ߘa4�N�x�Ǘ��h�{�m���Ǝ����o���v�́u�Տ��h�{�w�v�ɑ������鍀�ڂ�ԗ����C�e�펾���K�C�h���C���̕ύX�ɂ��Ή��D
��1�́@�Տ��h�{�w�̊�b
�@A�@�Ӌ`�ƖړI
�@B�@�����Ɖh�{
�@�@�@���a�̐����Ƃ��Ẳh�{
�@�@�A���������i�����K���a�j
�@�@�B���X�N�}�l�W�����g
�@�@�C�����̌��ʂƂ��Ẳh�{�s��
�@�@�D�h�{�s�ǂ̓�d����
�@C�@��ÁE��쐧�x�̊�{
�@�@�@��Õی����x
�@�@�A���ی����x
�@D�@��ÂƗՏ��h�{
�@�@�@���Âɂ�����h�{�}�l�W�����g�̈Ӌ`
�@�@�A�N���j�J���E�p�X�Ɖh�{�Ǘ�
�@�@�B�`�[����ÁC�`�[���P�A�C�h�{�T�|�[�g�`�[���C���E��Ƃ̘A�g
�@�@�C�Ǘ��h�{�m�̖����ƃ��[�_�[�V�b�v
�@�@�D��̗ϗ��C�����ϗ��C���`��
�@�@�E���ҁE��Q�҂̌����E�S��
�@�@�F�C���t�H�[���h�E�R���Z���g
�@E�@�����E���ƗՏ��h�{
�@�@���K���
��2�́@�`�[�����
�@A�@�`�[����ÂƂ�
�@�@�@�`�[�����
�@�@�A�Ǘ��h�{�m�̖���
�@B�@�e��`�[����Â̎���
�@�@�@�h�{�T�|�[�g�`�[��
�@�@�A���`�[��
�@�@�B�ېH�E�����`�[��
�@�@���K���
��3�́@�h�{�P�A�E�}�l�W�����g
�@A�@�h�{�P�A�ƃ}�l�W�����g�Ƃ�
�@�@�@�h�{�P�A�E�}�l�W�����g�̒�`�ƍ\��
�@�@�A�}�l�W�����g�E�T�C�N��
�@B�@�h�{�P�A�E�}�l�W�����g�Ɛ��x
�@�@�@��Õی����x
�@�@�A�f�Õ�V�ɂ�����h�{�P�A�E�}�l�W�����g
�@�@�B���ی����x�ɂ�����h�{�P�A�E�}�l�W�����g
�@�@�C�h�{����
�@C�@�N���j�J���E�p�X
�@�@���K���
��4�́@�h�{�A�Z�X�����g
�@A�@�Ӌ`�ƖړI
�@B�@�h�{�X�N���[�j���O�ƃA�Z�X�����g
�@�@�@�h�{�X�N���[�j���O�̈Ӌ`
�@�@�A�h�{�X�N���[�j���O�̕��@
�@C�@�Տ��f��
�@�@�@���E���o�Ǐ�̊ώ@
�@�@�A�������C���a���C�Ƒ���
�@D�@�Տ�����
�@�@�@�h�{��Ԃƕa�Ԃ̕]���w�W
�@E�@�g�̌v��
�@�@�@���荀��
�@F�@�H������
�@G�@�h�{�K�v�ʂ̎Z��
�@�@�@�G�l���M�[�K�v�ʂ̎Z��
�@�@�A����ς����K�v�ʂ̌�����@
�@�@�B�����K�v�ʂ̌�����@
�@�@�C�����K�v�ʂ̌�����@
�@�@�D�r�^�~���E�~�l�����K�v�ʂ̌�����@
�@H�@�G�l���M�[����щh�{�f�̃A�Z�X�����g
�@�@�@�G�l���M�[�̃A�Z�X�����g
�@�@�A����ς����̃A�Z�X�����g
�@�@�B�����̃A�Z�X�����g
�@�@�C�����̃A�Z�X�����g
�@�@�D�r�^�~���E�~�l�����̃A�Z�X�����g
�@�@�E���̃A�Z�X�����g
�@�@�F�����I�ȉh�{�A�Z�X�����g
�@�@���K���
��5�́@�h�{�P�A�v��
�@A�@�h�{�P�A�v��Ƃ�
�@B�@�h�{�P�A�v��쐬�̎菇
�@�@�@�h�{�P�A�v��̍쐬
�@�@�A�J���t�@�����X�̊J��
�@C�@�h�{�P�A�v��̎��{
�@�@���K���
��6�́@�h�{�E�H���Ö@�C�h�{�⋋�̕��@
�@A�@�h�{�E�H���Ö@�Ɖh�{�⋋�@
�@�@�@�h�{�E�H���Ö@�Ɖh�{�⋋�@�̗��j
�@�@�A�h�{�E�H���Ö@�Ɖh�{�⋋�@�̓���
�@�@�B�h�{�⋋�@�̑I��
�@B�@�o���h�{�⋋�@�i�h�{�E�H���Ö@�j
�@�@�@���ÐH�Ɖ��H
�@�@�A���ÐH�̎��
�@�@�B���ÐH�̎��a�ʕ��ނƎ听���ʕ���
�@�@�C�H��
�@�@�D�H�i�I���ƌ����쐬
�@C�@�o���h�{�⋋�@
�@�@�@�ړI
�@�@�A�K���Ƌ֊�
�@�@�B���^���[�g
�@�@�C�o���h�{�܁E���i�̎�ނƐ���
�@�@�D���^���@
�@�@�E�h�{�⋋�@�ɕK�v�ȗp��C�@�B
�@�@�F���j�^�����O�ƍĕ]��
�@�@�G�o���h�{�@�̍����ǂƑΉ�
�@�@�H�ݑ�o���h�{�T�|�[�g
�@D�@�Ö��h�{�⋋�@
�@�@�@�ړI
�@�@�A�K��
�@�@�B�����Ö��h�{�@�ƒ��S�Ö��h�{�@
�@�@�C�A�t�̎�ނƐ���
�@�@�D�h�{�⋋�ʂ̎Z����@
�@�@�E�h�{�⋋�@�ɕK�v�ȗp��C�@�B
�@�@�F���j�^�����O�ƍĕ]��
�@�@�G�Ö��h�{�@�̍����ǂƑΉ�
�@�@�H�ݑ�Ö��h�{�T�|�[�g
�@�@���K���
��7�́@�h�{����
�@A�@���a�҂̉h�{����
�@�@�@�Ӌ`�ƖړI
�@�@�A�K�v�ȋZ�p
�@�@�B�����Ɠ���
�@B�@�f�Õ�V���x�ł̉h�{����
�@�@�@�h�{�H���w��
�@�@�A�h�{�Ǘ�
�@C�@�v�x���ҁE�v���҂̉h�{����
�@�@�@�Ӌ`�ƖړI
�@�@�A�Ώێ҂ƃT�[�r�X�̌n
�@�@�B�����Ɠ���
�@D�@����V���x�ł̉h�{����
�@E�@�h�{����̉^�p�V�X�e���ƋL�^
�@�@�@�^�p�V�X�e��
�@�@�A�h�{�H���w���L�^
�@F�@�h�{����̃}���p���[
�@�@�@����ÐE��
�@�@�A�Ƒ�
�@�@�B���҉�
�@�@���K���
��8�́@�h�{�P�A�̎��{�Ɖh�{���j�^�����O
�@A�@�h�{���j�^�����O
�@B�@�]��
�@�@�@���ʁi���ʁj�̕]��
�@�@�A�o�߁i�ߒ��j�̕]��
�@�@�B�\���̕]��
�@�@���K���
��9�́@�h�{�Ǘ��̋L�^
�@A�@�h�{�Ǘ��L�^�̈Ӌ`
�@�@�@�h�{�Ǘ��L�^�̈Ӌ`
�@B�@���u���^�V�X�e���iPOS�j�̊��p
�@�@�@POS�̗��O�ƍ\��
�@�@�APOS�̊T�O
�@�@�B���u���^�f�Ø^�iPOMR�j�̍쐬
�@�@���K���
��10�́@�h�{�Ǘ��v���Z�X
�@A�@�h�{�Ǘ��v���Z�X�Ƃ�
�@B�@�h�{�Ǘ��v���Z�X�̎��H
�@�@�@�h�{�X�N���[�j���O
�@�@�A�h�{�]���i�h�{�A�Z�X�����g�j
�@�@�B�h�{�f�f�iPES�j
�@�@�C�h�{����v��
�@�@�D�h�{���j�^�����O
�@�@�E�h�{�Ǘ��L�^
�@�@�F�h�{�Ǘ��v���Z�X�Ƒ��E��A�g
�@�@���K���
��11�́@��Ɖh�{�E�H���̑��ݍ�p
�@A�@���i���h�{�E�H���ɋy�ڂ��e��
�@�@�@�h�{�f�ێ�ʂ̌����E����
�@�@�A�h�{�f�̋z���̌���
�@�@�B�h�{�f�̋z���E�K�v�ʂ̑���
�@�@�C�h�{�f�r���̕ω�
�@B�@���i�ɂ��d�����̕ω�
�@�@�@�i�g���E���iNa�j
�@�@�A�J���E���iK�j
�@�@�B�����iP�j
�@�@�C�}�O�l�V�E���iMg�j
�@�@�D�J���V�E���iCa�j
�@C�@�h�{�E�H�i�����i�ɋy�ڂ��e��
�@�@�@��̋z��
�@�@�A��̐����w�I�L����
�@�@�B��ɂ�鐶�̓��ω�
�@�@�C��̔r��
�@�@�D��ɂ��N����h�{�f�̒��Njz����Q
�@�@�E��̍�p�ɉe�����y�ڂ��H�i�C�h�{�f
�@�@���K���
��12�́@�h�{��Q
�@A�@������E�G�l���M�[�h�{��Q�iPEM�j�C�h�{������
�@B�@�r�^�~�����R�ǁE�ߏ��
�@C�@�~�l�������R�ǁE�ߏ��
�@�@���K���
��13�́@�얞�Ƒ�ӎ���
�@A�@�얞�C���^�{���b�N�V���h���[��1
�@B�@���A�a
�@C�@�����ُ��
�@D�@���A�_���ǁC�ɕ�
�@�@���K���
��14�́@�����펾��
�@A�@�������C�㉊
�@B�@�ݐH���t����
�@C�@�ݒ�ᇁC�\��w�����
�@D�@�`���R�o���ݒ���
�@E�@���ǐ�������
�@�@E-1�@�N���[���a
�@�@E-2�@��ᇐ��咰��
�@F�@�ߕq�����nj�Q
�@G�@�����C�֔�
�@�@G-1�@��������
�@�@G-2�@�����֔�
�@H�@�̉�
�@I�@�̍d��
�@J�@���b�́CNAFLD�ENASH
�@K�@�_�ΏǁC�_囊��
�@L�@�X��
�@�@���K���
��15�́@�z�펾��
�@A�@��������
�@B�@�����d����
�@C�@���S�ǁC�S�؍[��
�@D�@�S�s�S
�@E�@�s�����G�S�[�ד��C�S���ד��C�S���p��
�@F�@�]�o���C�]�[�ǁC�N�������o��
�@�@���K���
��16�́@�t�E�A�H����
�@A�@�����̐t��
�@B�@�l�t���[�[�nj�Q
�@C�@���A�a���t���a
�@D�@�}���t��Q
�@E�@�����t��Q�E�t���a
�@F�@���t���́C��������
�@G�@�A�H���Ώ�
�@�@���K���
��17�́@�����厾��
�@A�@�b��B�@�\���i�ǁE�ቺ��
�@B�@�N�b�V���O�a�E�nj�Q
�@�@���K���
��18�́@�_�o����
�@A�@�F�m��
�@B�@�p�[�L���\���a�E�nj�Q
�@�@���K���
��19�́@�ېH��Q
�@A�@�_�o���₹��
�@B�@�_�o���ߐH��
�@C�@�ނ���H����Q
�@�@���K���
��20�́@�ċz�펾��
�@A�@COPD�i�����ǐ��x�����j
�@B�@�C�ǎx�b��
�@C�@�x��
�@�@���K���
��21�́@���t�n�̎����E�a��
�@A�@�n��
�@�@A-1�@�S���R���n��
�@�@A-2�@���ԉ苅���n��
�@�@A-3�@�n�����n��
�@�@A-4�@�Đ��s�ǐ��n��
�@�@A-5�@�t���n��
�@B�@�o��������
�@�@���K���
��22�́@�E���i����
�@A�@���e頏�
�@B�@����ǁC����a
�@C�@�ό`���ߏ�
�@D�@�T���R�y�j�A
�@E�@���R���e�B�u�V���h���[���i�^����nj�Q�j
�@�@���K���
��23�́@�Ɖu�E�A�����M�[����
�@A�@�H���A�����M�[
�@B�@�P���a�C���ȖƉu����
�@C�@�Ɖu�s�S
�@�@���K���
��24�́@������
�@A�@�H����
�@B�@�s����
�@C�@�@��������
�@�@���K���
��25�́@����
�@A�@�����ǂ̂���
�@�@A-1�@�H������
�@�@A-2�@�݂���
�@�@A-3�@�咰����i��������E��������j
�@B�@�����LjȊO�̂���
�@�@B-1�@�x����
�@�@B-2�@�̂���
�@�@B-3�@�X����
�@�@B-4�@�����a
�@C�@���w�Ö@�C���ː��Ö@�C�ɘa�P�A
�@�@C-1�@���w�Ö@
�@�@C-2�@���ː��Ö@
�@�@C-3�@�ɘa�P�A
�@D�@�I������Ái�^�[�~�i���P�A�j
�@�@���K���
��26�́@��p�E���p��
�@A�@��p�E���p���̉h�{�P�A�E�}�l�W�����g
�@B�@�����ǂ̏p�O�E�p��
�@�@B-1�@�H���؏�
�@�@B-2�@�ݐ؏�
�@�@B-3�@�����؏�
�@�@B-4�@�咰�؏�
�@C�@�����LjȊO�̏p�O�E�p��
�@�@���K���
��27�́@�N���e�B�J���E�P�A
�@A�@�W������
�@B�@�O��
�@C�@�M��
�@�@���K���
��28�́@�ېH�@�\�̏�Q
�@A�@�E������Q
�@B�@���o�E�H����Q
�@C�@�����ǒʉߏ�Q
�@�@���K���
��29�́@�v���C�g�́E�m�I��Q
�@A�@�g�̏�Q
�@B�@�m�I��Q�i���_�x�j
�@C�@���_��Q
�@�@���K���
��30�́@���c���E��������
�@A�@�����s�Ǐǁi���������ǁj
�@B�@�������q�f��
�@C�@�A�����M�[����
�@D�@�����얞
�@E�@��V����ӈُ�
�@�@E-1�@�t�F�j���P�g���A��
�@�@E-2�@���[�v���V���b�v�A��
�@�@E-3�@�K���N�g�[�X����
�@�@E-4�@�����a
�@�@E-5�@�z���V�X�`���A��
�@F�@���A�a
�@�@F-1�@1�^���A�a
�@�@F-2�@2�^���A�a
�@G�@�t����
�@�@G-1�@�l�t���[�[�nj�Q
�@�@G-2�@�}�������̐t��
�@�@���K���
��31�́@�D�Y�w�E�����w����
�@A�@�얞�C��̏d�i�₹�j
�@�@A-1�@�얞
�@�@A-2�@��̏d�i�₹�j
�@B�@�S���R���n��
�@C�@�D�P���A�a�C���A�a�����D�P
�@�@C-1�@�D�P���A�a
�@�@C-2�@���A�a�����D�P
�@D�@�D�P�������nj�Q
�@�@���K���
��32�́@�V�N�nj�Q
�@A�@�뚋�C�]�|�C���ցC���
�@�@A-1�@�뚋
�@�@A-2�@�]�|
�@�@A-3�@����
�@�@A-4�@���
�@B�@�t���C��
�@C�@�������������l�������h�{�P�A
�@�@���K���
�Q�l�}��
���K����
����
�R����
�@�@GLIM��ɂ��h�{�Ǘ�
�@�@�h�{����
�@�@�h�{����Ƒ��E��A�g
�@�@���E��A�g
�@�@�X�����A�a
�@�@�ېH��Q�ɑ���F�m�s���Ö@�uCBT–E�v
�@�@�ېH��Q���҂̕K�v�G�l���M�[
�@�@COPD�̔F�m�x
�@�@�i���̊Q
�@�@�n���ƃs������
�@�@�S���R���n���Ɓg�X������h
�@�@�n���Ƃ���
�@�@�n���ƃv���[��
�@�@�ݑS�E��̕n��
�@�@�Ȃ��s�����ۂɊ�������ƈ݂���ɂȂ�₷���̂��H
�@�@ERASⓇ�v���g�R�[��
�@�@�]������҂̐H���̒��ӁF����������ƃ`�����X�������H
�@�@���_�^�����B�x�؊��҂̐H���̒���
�@�@����\�͈ȊO�̗v���Ƃ́H
�@�@�S�̕⋋��H�������ōs����
�@�@�D�P�������nj�Q�̕���ɂ͐����������K�v�H
�@�@�����̎�����L���鍂��҂̐���G�l���M�[�K�v�ʂ̌v�Z
�����N�E�h�{�Ȋw�V���[�Y〞�ďC�̂��Ƃ�
�@�����h�{�Ɋւ���w���̓���ƓO���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��C�h�{�m�̐g���Ƃ��̋Ɩ������ƓI�ɒ�߂�ꂽ�̂́C1945�i���a20�j�N�̉h�{�m�K���Ǝ����h�{�m�{�����w��K�����z�ɑk��D�����̗{���{�݂�14�Z�ł���C���Ɛ��͑S���h�{�m�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�D���̌�1947�i���a22�j�N�̉h�{�m�@���z���o�āC�Ǘ��h�{�m���x��1962�i���a37�j�N�ɐ݂���ꂽ�D�����āC2000�i����12�j�N4���̉h�{�m�@�����ŁC�Ǘ��h�{�m�͈�Ð��E�̍��Ǝ��i�Ƃ��Ē�߂�ꂽ�D�Ǘ��h�{�m�Ƃ́C�����J����b�̖Ƌ����āC���a�҂ɑ���×{�̂��߂ɕK�v�ȉh�{�w���C�l�̐g�̂̏C�h�{��ԓ��ɉ��������N�̕ێ����i�̂��߂̉h�{�w���C���тɓ��葽���l�ɑ��Čp���I�ɐH������������{�݂ɂ����闘�p�҂̐g�̂̏C�h�{��ԁC���p�̏��ɉ��������ʂ̔z����K�v�Ƃ��鋋�H�Ǘ��C�y�т����̎{�݂ɑ���h�{���P��K�v�Ȏw�������s�����Ƃ��ƂƂ���҂ƒ�`����Ă���D�h�{�m���x�̊J�n�����ƈقȂ�C�����̌��N�ۑ���H�ƕs���ɂ���h�{����C2�^���A�a�⎉���ُ�ǂ��͂��߂Ƃ��������K���a�ւƈڍs�����D�܂����q����Љ�ɂ��l�X�ȎЉ�I�ۑ肪�����Ă���C�Ǘ��h�{�m�ɋ��߂���m����Z�p�̍��x�����K�{�ł���D
�@�{�g���N�E�h�{�Ȋw�V���[�Y�h�́C���̂悤�Ȕw�i�ɉ����C�������N�E�h�{�������̊ďC�Ƃ��āC�������� �c�����O�搶�̂��Ƃɗ����グ��ꂽ�D�����č��Ǝ����o�������̋��ȏ��Ƃ��āC�Ǘ��h�{�m�{������ɑ傫�Ȗ������ʂ����C�D�]�ƐM���ɉ����������d�˂Ă����D
�@�Ǘ��h�{�m���Ǝ����o����2023�i�ߘa5�j�N1���C�w�p�̐i���₱�̊Ԃ̖@���x�̉����Ɠ����ɑΉ����C�u�Ǘ��h�{�m�Ƃ��Ă̑����ݏo���C���̐E�����ʂ����̂ɕK�v�Ȋ�{�I�m���y�ыZ�\�v��₤���̂Ƃ��ē��e���������肪�Ȃ��ꂽ�D�����Ŗ{�V���[�Y������܂ł̉����ɏd�˂ĉ��荑�Ǝ����o���������p�����邩�����ŏ����������Ă���Ƃ���ł���D�e�Ȗڂ̏d�v�����������������ȏ��C���Ǝ����C����ɖƋ��擾��̍��E�̏��Ƃ��čŗǂ̐}���ł���Ɗm�M���C��������D���C�{�V���[�Y�̓����ł���C�@�o���̑區�ځC�����ځC�����ڂ̂��ׂĂ�ԗ�����C�A�œK�̕ҏW�҂Ǝ��M�҂����I����C�B�o�����ڂ̂����d�v�����͏[��������C�C�ŐV���ɑ�������C�Ƃ����]���̕ҏW���j�́C�����������P�����D
�@�Ǘ��h�{�m��ڎw���F���C�{�V���[�Y�����p���ĊǗ��h�{�m���Ǝ��i���擾���C���H����ɂ�����l�X�ȉh�{�j�[�Y�ɉ�����ׂ����r��ς݁C�ی��E��Ð��E�Ƃ��Ă̒m�������C������QOL�i�����̎��C�l���̎��j�̕ێ����i�ɍv�����邱�Ƃ��F�O����D
2024�N2��
���������J���@�l ����ՁE���N�E�h�{������
�����@��{�@�G��
������4�ł̏�
�@�ߔN�C�Տ��h�{�w�͒������i�����Ă���D2019 �N�Ɋ��s���ꂽ�{���̉�����3 �łł́C�e��h�{�⋋�C�h�{�Ǘ��V�X�e���C����Ɏ������Ƃ̉h�{�E�H���Ö@���̐i���ɏ]���āC�V���Ȓm���荞�D���̌�C��w�E�h�{�w�̐i���ȊO�ɁC�ΏۂƂȂ鏝�a�҂̍�����ÁE��쐧�x���̕ω���w�i�Ƃ��āC�Տ��h�{�w�ŏK�����ׂ����I�Ȓm����Z�p���ω�������D
�@�Ⴆ�C�h�{�Ƃ̊֘A�����������A�a�C�����ُ�ǁC�������C�t���a�C���̔��������iNCDs�j�C�����鐶���K���a�ɑ��ẮC���P���ׂ��h�{��H���݂̍�����Ȋw�I�ɖ��炩�ɂȂ��Ă����D�ߔN�̈�Â̐i��������CNCDs �̊��҂͒����ƂȂ�C���x�̈�Â��Ȃ��������l�Ɠ��l�ɐ����ł���悤�ɂȂ����D�������C����҂̕a�ԂƉh�{��Ԃ͑��l�ŁC���G�ŁC�����̎������������Ă��邱�Ƃ������C�]���̂悤�ȓ���̎����ɑ������̉h�{�E�H���Ö@�͌��ʂ����ɂ����Ȃ��Ă���D
����҂́C�������邱�Ƃ̂Ȃ����������Ǝ��ʂ܂ŕt�������C�����̎������݂��Ɋ֘A���Ȃ��瑝�����钆�ŁC�h�{�E�H���Ö@��i�߂Ă������ƂɂȂ�D
�@�܂��C���A�a��t���a�̍���҂ɂ����āC�₹�C�n���C�T���R�y�j�A�C��^���p�N�����ǁC���e頏ǁC���܂Ȃǂ̒�h�{�������o��������D�Ö@��O�ȗÖ@�̕���p�ɂ�閡�o��H�~�̒ቺ�ɂ���h�{�ɂȂ郊�X�N�͑��傷��D���������a�����ɂ��C�h�{�f�̍����E����\�͂��ቺ���āC�ɂ����Ԃ�v�����߂ɉh�{�f�̕K�v�ʂ����傷�邱�Ƃ��v���ƂȂ��Ă���D����ɉh�{�E�H���Ö@�́C�h�{�o�����X�̎�ꂽ���N�ȐH���Ɣ�ׂ�ƁC������A���o�����X�H�ɂȂ��Ă���̂ŁC�����Ɏ��{����Ήh�{��Q���N�����댯��������D
�@����҂��a�C�̎��ÂƓ����ɉ��K�ɐ�����S���ł���h�{�E�H���Ö@�́C�ǂ̂悤�ɍs����ׂ��Ȃ̂��H�@�Տ��h�{�w���V���Ȏ���̉ۑ�ɑΉ��ł���悤�ɍ���̉�����Ƃ����{�����D
�@�Ǘ��h�{�m��ڎw���C�Տ��h�{�w���w�Ԑl�X���C�Տ��h�{�Ɋւ����b�������w�ԂƓ����ɍŐV�̒m���ƋZ�p���K�����邽�߂ɁC�{�������p����邱�Ƃ�S�������Ă���D
2025 �N2 ���g��
�ҏW�҂��\����
��������
���ł̏�
����̐H����H�i�ƕa�C�Ƃ̊W���Ȋw�I�ɉ𖾂����̂́C18 ���I�㔼�C���[���b�p�Ŕ��W�����h�{�w�ł���D�h�{�w�͐H���Ɋ܂܂��G�l���M�[�Ɗe��h�{�f�̍�p�𖾂炩�ɂ��C���̒m�������Ƃɂ��܂��܂Ȏ����ɑ���H���ɂ��\�h�@�⎡�Ö@�����������D
�@�ߔN�C�Ƃ��ɖ��ɂȂ��Ă���̂������K���a�ł���D�����K���a�Ƃ́C�s�K���Ȑ����K�������X�N�t�@�N�^�[�ƂȂ蔭�ǂ��鎾�a�Q�������C���̑�ɂ́C����҂�n�C���X�N�҂ւ̈ꎟ�\�h�i�ی��j�C���nj�̑������h�~��ړI�Ƃ����\�h�i��Áj�C����ɔ��nj�ɋN����e��g�̏�Q��\�h����O��
�\�h�i���j������C�H�����̉��P��H���Ö@���d�v�Ȗ������ʂ����D
�@�܂��C���Ăł�1970 �N��CHospital Malnutrition ���傫�Ȓ��ڂ𗁂т��D�a�@�̓��@���҂╟���{�݂̓����҂̖����h�{������Ԃɂ���C���̂悤�ȏ�Ԃ���u���Ă����ƁC��p��Ö@�̎��Ì��ʂ̒ቺ�C���@�E���������̑����CQOL �̒ቺ����������D���̌��ʁC��Ô�������債�C
�h�{��Ԃ̉��P���d�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă����D
�@���a�҂ւ̉h�{���́C���a�̗\�h�⎡�ÂƂ��Ă̐H���Ö@�Ɠ����ɁC�K���ȉh�{��Ԃ��ێ��C���P���邱�Ƃ��d�v�ł���C���̎��{�ɂ́C��蕡�G�ō��x�Ȓm���ƋZ�p���K�v�Ƃ����D���a�҂̕a�ԂƉh�{��Ԃ𑍍��I�ɕ]���C���肵�C�����Ƃ��d�v�ȉ��P�ڕW��ݒ肵�C�H���Ö@�Ɗe��h�{�⋋�@�𑍍��I�Ɍ������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�������ł���D�g�p����H�i���C����̐H�i�݂̂ł͂Ȃ��a�җp���ʗp�r�H�i�C�ی��@�\�H�i�i���ʕی��@�\�H�i�C�h�{�@�\�H�i�j�Ȃǂ�����C�J�e�[�e����p�����o���h�{��o�Ö��h�{�ɂ��e��o���h�{�H�i�C�h�{�܂�����D
�@�ȏ�̂��Ƃ���C�K���ȉh�{�Ǘ����s�����߂ɉh�{�P�A�E�}�l�W�����g�̊T�O�ƕ��@����������C2003�i����15�j�N�C�����J���Ȃ́C�Ǘ��h�{�m�{���̂��߂ɐV���ȃJ���L�������ƊǗ��h�{�m���Ǝ����̃K�C�h���C�����������D�u�Տ��h�{�w�v�ł́C���a�҂̕a�Ԃ�h�{��ԂɊ�Â��������I�ȉh�{�Ǘ�
�𗝉����C�h�{��Ԃ̕]���E����C�h�{�⋋�C�h�{����C�H�i�ƈ��i�̑��ݍ�p�ɂ��ďC�����C��ÁE��쐧�x���Ã`�[���ɂ�����h�{�Ǘ���Ǘ��h�{�m�̖����𗝉����邱�Ƃ����߂��Ă���D
�@�{���́C���̂悤�ȐV�����Ǘ��h�{�m�{������ɂӂ��킵�����ȏ��Ƃ��ĕҏW�����̂ŁC�����̋���@�ւŋ��ȏ���Q�l���Ƃ��Ċ��p����邱�Ƃ���]����ƂƂ��ɁC�ǎҏ��Z�o�̊��݂̂Ȃ����ᔻ�C�����������������C���悢���ȏ��ƂȂ��Ă������Ƃ�����Ă���D
�@�Ō�ɁC���e�����������Ȃ���C�����Ԃ�v�����ɂ�������炸�C�܂������̐���̒��ł����M�������������M�ҏ��搶���ɐ[�r�Ȏӈӂ�\���鎟��ł���D
2008 �N5 ��
�ҏW�҂��\����
��������

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)